���E���l�����ʐ^�� �y�d������������ Version�z
���l�R�[�i�[�o�`�q�s�U�i�����A�����đ��j
�i�Ñ�`�����j�@�i�퍑�����E�e���M���j�@�i���y���R�E�L�b�̉h���j�@�i�փ����A���̐w�`�]�˒����j�@�i�����j�@�i�����{�R�j�@�i�փ����j�ցj
23��
������ ��/Hitoshi Imamura 1886.6.28-1968.10.4 �i�{�錧�A���s�A�։��� 82�j2012
 |
 |
 |
| ���������R�����Ă̖��� | �����Ƃ̕�� | �։����̕�n�͍L��I��͎O�d���ɋ߂� |
 �@ �@ |
 |
| �����叫�̂悤�Ȑl���肾������ǂ�Ȃɗǂ��������I | �����Ɍ��w�����ϗݑ�V��x |
|
���{���R�ɂ������������I�Z���e�����i�V�I�l���h�����鍡���ρi1886-1968�j���R�叫��S�͂ŏЉ�����B�����叫�̑��݂͋����̑����R��w���̒��ŎW�R�ƋP���Ă���I
1886�N�A��䐶�܂�B���͍ٔ����B���w����Ȃő��Ƃ��A�ꍂ�i����j�ւ̐i�w�����҂��ꂽ���A�������E���o�ϓI�� �������Ȃ藤�R�m���w�Z�ցB1907�N�i21�j�A���R�������тɔC���A20�㔼�ɗ��R��w�Z�ɐi�w�����B�c��������A�ǂɂ鐇���s���ɋꂵ��ł������������Ȃő��Ƃ��A�É����牶���̌R��������B1918�N�i32�j�A�C�M���X��g�ٕ������⍲���Ƃ��ēn�p�B1922�N�i36�j�A���R���������ɏ��i�B
1927�N�i41�j�A�C���h���g�ٕ������Ƃ��ēn��B1935�N�i49�j�A���R�����ɏ��i�B1941�N�i55�j�A��16�R�i�ߊ��Ƃ��ĊJ����}���A�T���T��̕��͂ŗ��̃C���h�l�V�A���U������B�����q�͂����ʓI�Ɋ��p���A�킸���X���ԂŖ�Q�{�̓G�������R��X���R��A�p���R��T������~�������A�ŏd�v�헪�ڕW�̃p�����o�����c�n�т𐧈������B���̐킢�ŃI�����_���ɗ��Y����Ă����C���h�l�V�A�Ɨ��^���̎w���҃X�J���m��n�b�^�琭���Ƃ��u���ꂩ��M�a�����͎��R���v�Ɖ�����A����Ɏ������������������B
�R���w���҂Ƃ��Ă��r��U�邢�A�Ζ������{�݂����ĐΖ����i���I�����_��������̔��z�ɂ�����A���R����v���������Ŋe�n�Ɋw�Z�̌��݂��s���A�W��̎��R��ۏ��A���O�ɂ̓I�����_�������ŋ։̂ƂȂ��Ă����Ɨ��́u�C���h�l�V�A�E�����v�����ւ����B���{���ɂ͗��D�֎~�𖽂��A��ʃI�����_�l�ɂ͊O�o�̎��R��F�߁A�ߗ��R�l�̑ҋ����悭���e�ȌR�����s�����B
��{�c���W�����Y���ؖȁi������߂�j����{�֑�ʗA������悤���߂Ă������A�����i�ߊ��́u���n�l���甒�ؖȂ����グ��Γ��퐶������������v�Ƃ��ċ��ۂ����B���n����ᔻ�̐����N���A1942�N�A�R���ō��ږ�E���ʏG�Y���W�����֕��C�����Ԓ������s�����B���ʂ́u�����A�Y�Ƃ̕����A�R�������̒��B�ɂ����āA�W�����̐��ʂ����ʂ��ėǂ��v�u���Z���͓��{�l�ɐe���݂��悹�A�I�����_�l�͓G��f�O���Ă���v�� �������i�ߊ��̌R�����^�����B
�����A�R��������̍����i�ߊ��ւ̈��͂͑����A���R�ȌR���ǒ��E�����͂�l���ǒ��E�x�i�����́A�V���K�|�[���̔@�������I�ȌR���ɓ]������悤���߂��B����ɑ��A�����i�ߊ��͗��R�Q�d�{���N�Ắw��̒n�����v�j�x�ɏ����ꂽ�u�����ȈГ��Ŗ��O���x�������v�Ƃ����ꕶ���o���ĕ��j�ύX�ɒ�R�����B���N11���A�����i�ߊ��͂킸���ݔC10�����ő�16�R�i�ߊ�����C����A�V���ɑ�W���ʌR�i�ߊ��Ƃ��ăj���[�M�j�A�̃��o�E ���i�j���[�u���e�����j�ɍ��J���ꂽ�B
�������i�ߊ��̌�C�ŃW�������������c�F�g�����́A�����i�ߊ��Ƌt�ɋ����I�ȌR�����s�������߁A�W�����ł͍R���Q�����̓����������ɂȂ����B
1943�N�i57�j�A���R�叫�ɏ��i�B���N�S���ɋ��m�̎R�{�\�Z�C�R�叫�i�������Q�ΔN��j�����Ă���Q���߂��ށB���̍��A�K�^���J�i�������ח�����ȂǑ����m�̊e���͎��X�ƕČR�ɐ�̂���Ă����B �����叫�̓��o�E�����{�y�⑼������⋋������邱�Ƃ�\�����A���������̐����m�����邽�ߓ����ɑ�ʂ̓c������点�A����_�������J�������B�����ɕČR�㗤�┚���ɔ����邽�߁A���S�Ȓn���v�ǂ��\�z�B�v�Ǔ��ɂ͒������������Œe�Y�H��܂ŕۗL���Ă����B�}�b �J�[�T�[�̓��o�E���㗤��f�O���A���ƍU�߂�_�����I��i���E��ѐ����s�����A�����̐��������[���ɕ��������~���ꂽ���o�E���Ɍ��ʂ͂Ȃ��A�ČR���͌��ɂ����ďI��܂œ��{�R�����������B
1945�N�i59�j�A���{�~���B�����叫�̓��o�E����ƎҎ��e���Ɏ��e����A���B�R�̍ٔ�����B���n�Z���̍D�� �I�ȏ،��Ȃǂ������10�N�ƂȂ����B�W����������̐ӔC��₤�ٔ��ł͖��߂ƂȂ�B1950�N�i64�j�A�����̑����S�u���Ɉڂ���邪�A�����u�i���� �͓���̊č��Ȃ̂Ɂj�������������ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƃj���[�M�j�A�E�}�k�X���ŕ������鎖����]�B�}�b�J�[�T�[���킭�u���͍������R����������Ƃ� ���ɕ�������ׁA�}�k�X���s������]���Ă���ƕ����A���{�ɗ��Ĉȗ����߂Đ^�̕��m���ɐG�ꂽ�v���������v�B�R�����}�k�X���Y�����ɂĕ����B1953�N �i67�j�A�Y�������ɂ������̑����S�u���Ɉڂ����B68�A�Y�����I���o���B���̌�͎���̕Ћ��Ɍ��Ă��ސT���Ɏ��g��H���A�푈�ȁB���f�Ȑ����̒��Łu��ژ^�v���o�ł��A��ł����ׂĐ펀�҂��ƌY���҂̈⑰�ׂ̈ɗp�����B�o������14�N��A1968�N10���S����82�ő��E�B�����Ȑl���ŕ����������A�w�����Ƃ��Ă������̖����I��܂Ŏ�蔲���A���̐^���ȍs�������ɗ��h�B���˖Ґi�A���ӔC�Ȏw�����������R���ɂ����āA�ʊi�̑��݂� ������B
�����o�E�������R��������������搶���킭�u�i�����叫�́j���̉�����l�̒��ň�ԉ�������������l�������v�B�펞���̐V���͍����叫���u���{�ɕx�ݕ����������錪���ȕ��i���鏫�R�ł���v�u�l��R�v�ƏЉ�Ă���B ���嗤�ł̓�J���i1939�j�ł͑�T�t�c���Ƃ��Ďw��������A���\�{�̐�͂�L�������������}�R�̑�U���𐔏\���Ԃ����̂��������B
���W�������U���̍ہA�d���m�́u�ŏ�v�̋�����˂œ���͂���������A�^�钆�ɏd���̊C���R���ԉj���ŋ~�������o�������Ă���B
����14�R�i�ߊ��E�{�ԉ됰�����̓t�B���s���E�o�^�[���U���ɓ�q�����B������{�c����莋�����ہA�����叫�͖{�� �����ɓ���A���R�Q�d�����ɑ�{�c�ᔻ���s�����u�o�^�[���̋��͑�{�c�̏�F�Ɉ���Ƃ��낪�����A���͕s���̏�ԂŐ�̂��}�����ꂽ�{�Ԃɂ̂ݐӔC��킹��Ƃ����͍̂�������v�B
����j�����Œm�����ƁE�����ꗘ�i�͂�ǂ��E�����Ƃ��j�́A�g�����h�Ƃ��č����ρE�R�{�\�Z�A�I�ђ����A�Ό���
���E�i�c�S�R�A�ē������E�R�������A�R���E�����́A�ɓ�����E���O�Y�A�{��ɎO�Y�E���쎛�M�������A�g�����h�Ƃ��Ė��c������E�������O�A������
�l�Y�E�Ґ��M�A�ΐ�M��E���h���A���U���ӔC�҂̑吼�뎟�Y�E�y�i�����E�����ʑ�������Ă���B
���X�J���m�i1901-70�j�c�C���h�l�V�A���a������哝�́B�ݔC1945�`67�N�B�W�������X���o���o�g�B�݊w�����疯���^���ɎQ�����A1929�N�i28�j�ɃI�����_���ǂɑߕ߂����B�Q�N��Ɏߕ��ƂȂ������A1933�N�i32�j�ɍđߕ߂��ꗬ�Y�ƂȂ����B�X�N ���1942�N�i41�j�A�����ϒ����i�����j�ɂ���Ďߕ�����A�Γ����͂̂����ɐ����w���҂̒n�ʂ�F�߂�ꂽ�B1945�N�W��17���i44�j�A���{�~������ɃC���h�l�V�A�Ɨ���錾������哝�̂ɏA�C�B�ĐA���n����_���I�����_�Ɛ킢�A1949�N�i48�j�ɓƗ������F�������B���̌�A1955�N �i54�j�ɃW�������E�o���h���ő�P��A�W�A�E�A�t���J��c���J�Â���Ȃǔ��鍑��`�^�������[�h�B1965�N�i64�j�A�V�����Ƃ̎w���҂Ƃ��Ĕ��ĐF����苭�߂č��A��E�ށB1967�N�A�R���g�b�v�̃X�n���g�ɑ哝�̌�����D���A���N��Q��哝�̂ƂȂ����X�n���g�ɂ���ĊċցB�Q�N��i1970 �N�j�ɓ�֏�Ԃ̂܂ܕa�v�����B
|
|
�C�R���w�Z�c��������s��܂ő��������C�R�̏����m���{����ړI�Ƃ�������@�ցB������������i�҂̓G���[�g���̃G���[�g�B���ӂ͂Ȃ��O�H�t���B
�\�ȗ��i�C�R��s�\�ȗ��K���j�c�C�R�����w�Z�����ȑ��Ɛ���Ώۂɏ��N�q��{�������@�ցB
|
���R�� ��/Tomoyuki Yamashita 1885.11.8-1946.2.23 �i��ʌ��A�������s�A�t�� 60�j2010
 �@ �@ |
 |
| �g�}���[�̌Ձh�ƌĂꂽ�R���叫 | ��O�̊�B���Ԃ��瑐�����������͂������� |
�������쉀�̕�
 |
 |
 |
| �����쉀�̕��i2010�j | ���ʂɁu�R����v�A�����ʂɁu�ȃq�T�v�Ƃ��� | �R���叫�̒Ǔ��� |
���t���̕�
 |
 |
 |
| �R���叫�̂��߂ɍ��ꂽ�t�� �i�����{�ōŏ��̖��c��n�j |
�T��11��ɖ���i2019�j |
���ʂɁu���R�叫�R����v |
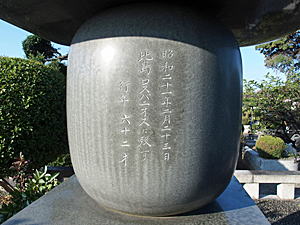 |
 |
 |
| �E���ʂɁu�䓇���X�o�j�I�X�ɟf���v |
�����ʂɎ����u�܂Ă����M�̂����� �䂫���F ���ƂȂ������ĉ���䂫�Ȃށv |
�w�ʂ́u���� ���a���N�\����\�O�� �R�����R���Âԉ�v�u�t���������v |
| ���R�叫�B�}���[�̌ՁB���m���o�g�B1916�N�i31�j���R��w�Z�𑲋ƁA�Q�d�{�����Ƃ��ēn�����A�X�C�X�A�h�C�c�ɒ��݁B�I�[�X�g���A��g�ٕt�������o�āA�A����ɗ��R�ȌR���ے��A�R�������������C�����B1936�N�i51�j�A��E��Z�������u�����A�����R�̍c���h�N���Z�Ɛe�����������R���͓V�c�̕s�����A���O�Ζ��Ɉڂ���A������40���c���i���N�j�A�k�x�ߕ��ʌR�Q�d���i�k���j�Ȃǂ߂��B1940�N�i55�j�A�q�ĂɏA�C���A�R�����@�c���Ƃ��ēƈɂ�K��A�q�g���[�Ɩʒk����B 1941�N12��8���i56�j�A�����m�푈�̊J��ɓ�����A��25�R�i�ߊ��Ƃ��ă}���[�����㗤�����w���B���N�Q���ɁA�C�M���X�R�̓��A�W�A�ő�̋��_�V���K�|�[�����U���A�p�R�p�[�V�o�����R�ɖ������~���𔗂�A�J�킩���R�J���Ŋח��������i�p�R�~�����A�R���͒ʖ�ɑ��āu�C�G�X�E�I�A�E�m�[�v�ƌ��������A���ꂪ����ăp�[�V�o���Ɍ��������́��s�҂ɍ����I�Ɠ`����ꂽ�j�B�V���K�|�[���ח����A�i�ߕ��Q�d�̒Ґ��M�ɂ��؋��s�E�����i�]���҂U��l�j��h���Ȃ��������Ƃ��A��N�̐�ƍٔ��ŕs���ƂȂ����B�R���̓}���[�����ɂ�������i���ɂ�荑���I�p�Y�ƂȂ������A��E��Z�����̉e���ōŌ�܂ŏ��a�V�c�ɔq�y������Ȃ������B�܂��A���R�����h�E�����p�@�͎R����a��Ń}���[���疞�B�ɔz�������B 1943�N�i58�j�A�叫�ɏ��i�B��1944�N�X��26�� �A�t�B���s������ׂ̈ɎR���̍˔\���K�v�ƂȂ�A��14���ʌR�i�ߊ��Ƃ��ăt�B���s���h�q���S���B10��20���A�}�b�J�[�T�[���R��650�ǂ��̊͑���10���T��l�̕ĕ��𗦂��ăt�B���s���E���C�e���ɍď㗤�����B ����ɑ��đ�{�c�͌���i��p���q���Ő�ʂ��ߑ�]���j�Ɋ�Â������𗧈āB���~�X���w�E�����R���̒��i���Ȃ�����R���i�ߊ��E��������̖��\���������ē��{�R�͔s�k���d�˂��B�ČR���}�j����i���郋�\�����ɏ㗤����ƁA�R���������14���ʌR�͎��v���I�юR�x�n�тɂ��������B����A�⟺�O������������}�j��������͕ČR�ƂR�T�Ԃɂ킽���Đ킢�ʍӁB���{�R�̎��Җ�P���Q��l�A�ČR�펀��1010�l�A�������܂ꂽ�t�B���s���s���̋]���҂͖�10���l�ɂ̂ڂ����B ���{���{�͂W��15���ɍ~�����A�R������X���R���Ƀt�B���s���E�o�M�I�ɂč~���B�~�����ɗ���������̂́A���ăV���K�|�[���ō~�������p�[�V�o�����R�ƁA���B�̕ߗ����e������~�o����A�����p��~�Y�[�����̍~�����ŏ��������W���i�T���E�E�F�C�����C�g�����������B 10�����{�����ƍٔ����n�܂�A12���Ɏ��Y����������B1946�N�Q��23���A�R���̓V���K�|�[���ł̉؋��s�E�����A�t�B���s���ɂ�����ߗ��s�҂Ȃǂ̐ӔC�����A�}�j���x�O�ła�b����ƂƂ��či��Y�ɂȂ����B���N60�B�����̋�u�܂Ă����M�̂����Ă䂫���F ���ƂȂ������ĉ���䂫�Ȃށv�i���炭�҂��ė~�����A���M���c���Đ������F��B�N�̌�����Ď���������ɍs������j�B�Ȃւ̎����u�����Č�������Ɠ܂�ɂ����ǂ� �Ƃ�ɍႦ���ޑ��̌��v�B �����쉀�̑��ɂ���ʌ��������s�́u�t���v�ɎR���叫�̕悪����B���n�͐����{�ōŏ��̖��c��n�ł���A�R���̂��߂ɍ��ꂽ�B�i�{��͐t���Ƃ̂��Ɓj �k�R���叫�̈⌾���l���v��̂��ߔ����A�����ɒu�������Ă��܂��B�������R�`���̃u���O�ɁB �u�V���{���݂ɂ́A���B�̂悤�ȉߋ��̈╨�ɉ߂��Ȃ��E�ƌR�l���邢�͈�懒Ǐ]�i��������傤���ւ炢�j���閳�ߑ��Ȃ鐭���ƁA�N���푈�ɍ����I��b��^����Ƃ�����p�w�ғ���f���ĎQ�������Ă͂Ȃ�܂����v�B �u���{�̑O�r���v���̗]��ꌾ�\���Y�������Ǝv���̂ł���܂��B���܂�Ă��A�Ă���Ă������ɐB�͂��������G���͏t������Ή�𐁂��܂��B�����Ƃ��Ƃ��j��ĎR�݂͂̂ƂȂ������{�ɂ������Ȃ锭�W�̈ӎu�����������{�̊F�l�́A�Ăѕ����̍��荂�����{������1863�N�̒��Ɛ푈�i�h�C�c�E�f���}�[�N�푈�j�ɂ���ĖL���Ȃ�V�����X���b�q�A�z���X�^�C�����B��D��ꂽ�f���}�[�N���Ăѕ���p���鎖��f�O���A�s�т̍��y�𐢊E�Ɋ����鉢�B����̕������Ƃɍ��グ���悤�Ɍ��݂����ł��낤����M���ċ^���܂���B���ǂ��S���̓k�͒��S�i���イ����A�S��j����̜����Ƌ��Ɉٍ��̒n��������{�������F�O�������܂��B�V�ɌR����`�҂ǂ���Ǖ��������̓I����ɑ��ꂽ���{�������N�A�r���ꂽ��Ђ̒�����Y�X�������オ���Ē��������B���ꂪ�����̔O��ł���܂��v �u���̌Y�̎��s�͍��X�ɔ����ĎQ��܂����B����40����������܂���B����40���������ɋM�d�Ȃ��̂ł��邩�A���Y���ȊO�ɂ͋��炭���̋C���̉���l�͂Ȃ��ł��傤�B���͐X�c���r�t�ƌ�邱�Ƃɂ���āA�����͓`���ł��낤�����v���A�F����ɓ`���Ē������Ƃɒv���܂��B�����Ē��������c�v �s�V�������{�ɕK�v�ȂR�_�t �i�P�j�����������Ɋ�Â����`���̗��s �u���R�Ȃ�Љ�ɂ����܂��ẮA����̈ӎu�ɂ��Љ�l�Ƃ��āA�ہA���{���鐢�E�l�Ƃ��Ă̍��M�Ȃ�l�Ԃ̋`���𐋍s���铹���I���f�͂�{�����Ē��������̂ł���܂��B�����ϗ����̌��@�Ƃ��������M�i�M�p�j�𐢊E�Ɏ����X���i���A�i���j�Ɏc���Ɏ�������Ɨe�^�҂𑽐��o���Ɏ��������{�I�����ł���Ǝv���̂ł���܂��B�l�ދ��ʂ̓��`�I���f�͂�{�����A���Ȃ̐ӔC�ɉ��ċ`���𗚍s����Ƃ��������ɂȂ��Ē��������̂ł���܂��v�B �i�Q�j�Ȋw����̐U�� �u��x�C�O�ɏo���l�Ȃ���ɋC�̂����́A���{�l�S�̂̔�Ȋw�I�����Ƃ������Ƃł���܂��B�������������Ȃ��r���I�ȓ��{���_�Ő^����T�����悤�Ɗ�Ă邱�Ƃ́A�����������ɂ���ċ������߂�Ƃ��邪�@�����̂ł���܂��v �u��X�͗D�G�Ȃ�ČR�������~�߂邽�߁A�S�����ɂĂ������Ȃ����Ȃ������̓��̂���e�Ƃ��ĂԂ��鎖�i�_�����U�j�ɂ���ď����悤�Ƃ����̂ł���܂��B�K�E���e�U���E�̓��蓙�̐�ɂ��ׂ���������@������܂����B�i���j��X�͎��ނƉȊw�̕n����l�Ԃ̓��̂������ĕ₨���Ƃ���A���\�L�̉ߎ���Ƃ����̂ł���܂��B���̈ꎖ�������Ă��Ă��A��X�E�ƌR�l�͖����ɉ�������̂�����܂��v �u���̍L���A����ɓ������ꂽ���q���e�͋��|�ɂ݂������̂ł���A����͒����l�ԋs�E�̗��j�ɂ����āA�����������̐l�Ԃ��������K�͂ɁA��������u�̒��ɒD��ꂽ���Ƃ͂Ȃ������̂ł���܂��B�����ɂ����Č����̗]�n�͂���܂���̂ł������A���炭���̌��q���e��h�䂵���镺��́A���̕����E�ɂ����Ĕ�������Ȃ��ł��낤�Ǝv���̂ł���܂��B�i���j���̋���ׂ����q���e��h�䂵����B��̕��@�́A���E�̐l�ނ����Č��q���e�𗎂Ƃ��Ă�낤�Ƃ����悤�Ȉӎu���N�������Ȃ��悤�ȍ��Ƃ�n������ȊO�ɂ́A��͂Ȃ��̂ł���܂��v �u�������̊��ɂ̂���Ő\���グ��Ȋw�i�̐U���j�Ƃ́A�l�ނ�j��ɓ����ׂ̉Ȋw�ł͂Ȃ��A�����p�����̊J�����邢�͐�����L�x�ɂ��邱�Ƃ����a�I�ȈӖ��ɂ����āA�l�ނ�������s�K�ƍ������������邽�߂̎�i�Ƃ��ẲȊw�ł���܂��v�B �i�R�j���q���� �u���{�w�l�̎��R�́A����킢��������̂ł͂Ȃ���̌R�̌��ӂ��鑡�^�ł����Ȃ��Ƃ������Ɋ뜜�̔O����̂ł���܂��v�B �u�]���ƒ�߁A����͓��{�w�l�̍ō������ł���A���{�R�l�̂���ƂȂ��ς鏊�̂��̂ł͂���܂���ł����B���̋������ꂽ��������āA���Ȃ��咣���Ȃ��l��受�ƌĂђ��E�Ȃ�R�l�Ǝ]�����Ă��܂����B�����ɂ͂Ȃ��s���̎��R�A���邢�͎����������������̂͂���܂���ł����B�F����͌Â��k�𑬂��ɒE���A��荂�����{��g�ɕt���A�]���̕w���i�ӂƂ��j�̈ꕔ����Ɋ܂�ŁA����������s��������V�������{�w�l�ƂȂ��Ē����x���Ǝv���̂ł���܂��B���a�̌����͕͂w�l�̐S�̒��ɂ���܂��B�F����A�F���V�Ɋl������܂������R��L���K�ɔ������ĉ������B ���R�͒N������Ƃ���D�͂����̂ł͂���܂���B�F��������̂Ă悤�Ƃ��鎞�ɂ̂ݏ��ł���̂ł���܂��B�F����͎��R�Ȃ�w�l�Ƃ��āA���E�̕w�l�Ǝ���q���ŕw�l�Ǝ��̔\�͂����ĉ������B���������łȂ��Ȃ�Η^����ꂽ���ׂĂ̓����͖��Ӗ��Ȃ��̂Ɖ�����ɈႢ����܂���B �Ō�ɂ�����w�l�ɐ\���グ�x�����́A�F����͊��ɕ�ł���A���͕�ƂȂ�ׂ����X�ł���܂��B��Ƃ��Ă̐ӔC�̒��Ɏ���̐l�ԋ���Ƃ����d��Ȗ{���̑����邱�Ƃ�؎��ɔF�����Ē����x���̂ł���܂��B�i���j���̂�������͗c�t���A���邢�͏��w�Z���w���������Ďn�܂�̂ł͂���܂���B�����Ԃ����ɐV����������^����M���J�n�̎��������Ďn�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B�i���j��͎q���̐�����ێ����邱�Ƃ��l���邾���ł͏\���ł͂Ȃ��̂ł���܂��B��l�ƂȂ������ɁA���Ȃ̐�����ێ�����������ɑς��E�сA���a���D�݁A�����������l�ނɊ�^���鋭���ӎu���������l�ԂɈ琬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B�F���q���ɓ��[��M�i�فj�܂������̍K���̜��������A�P�Ȃ铮���I����Ɏ~�߂邱�ƂȂ��A����ɒm�I�ȍ��M�Ȋ���ɂ܂ō��߂Ȃ���Ȃ�܂���B��e�̑̓����삯���鈤��͓��[���炱��Ɠ����̑̓��Ɉړ������ł��傤�B�i���j����Ȍ��t���K�����ǂ����A���ƂłȂ����ɂ͕���܂��A���͂�����u���[����v�Ƃł����������̂ł��B�ǂ������̕����肫�����P���ɂ��ĕ��}�Ȍ��t���A�F����̐S�̒��Ɏ~�߂ĉ������܂��悤�B���� ���F����̎q����D�������̍Ō�̌��t�ł���܂��v�B |
���R�{ �\�Z/Isoroku Yamamoto 1884.4.4-1943.4.18 �i�V�����A�����s�A������ 59�j2002��10��12��13
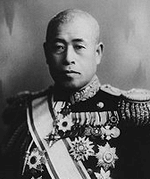 |
 |
| ���������q��@�𗘗p | �̋��E�����s�̎R�{�\�Z�L�O�� |
�������s�{���s�A�����쉀�̕�
 |
 |
 |
| 2002�@�����쉀�ɂď�����w�����C�R�叫 ���O�ʑ�M�ʌ��ꋉ�R�{�\�Z��x |
2010�@�[��ꎞ�B�ē���������Ɋ��| |
��O���璭�߂鈩�F�̋� |
 |
 |
 |
| 2012�@����҂ň�ꂩ�����Ă���I | �f���ĂȂ����ljE�ׂ����������A�����É�叫 | ���̎��͕�O�ɉ����A�ؔ����I |
���V���A�����s�̕�
 |
 |
 |
| �R�{�Ƃ̕�E�������i2013�j | �u�R�{�\�Z�揊�v�̈ē��B�����ɉ��� | �R�{�Ƃ̕��S�i�B�R�{�����ɘA�Ȃ閼�� |
 |
 |
| �E����R�Ԗځi�����j�̕���\�Z�B�����Ŗ��� | �u��`�@�a�������ˑ勏�m�v |
|
�u�A�����J�Ɛ푈���邱�ƂɂȂ�A���̓��{�͂Q�x�R�x���œy�Ɖ������낤�v�i�R�{�\�Z�j
��26�A27��A���͑��i�ߒ����B���C�R�ɂ����ĕē������A��㐬���i�����悵�j�Ƌ��Ɂu�m�āE���h�v�Ƃ��Ēm����B�V�����o�g�B���z�㒷���ˎm�E�����g�̘Z�j�B����56�̎��ɐ��܂ꂽ���Ƃ���g�\�Z�h�Ɩ��t����ꂽ�i��45�j�B���w�R�N�̂Ƃ��ɓ�ւ̊C�R���w�Z�ɓ��Z���悤�Ǝu�𗧂āA���H���ςނƒ��тƔӔїp�ɑ傫�Ȉ���т��S�����ĕ������ɂ��������B1901�N�i17�j�A�C�R���w�Z32����200�����Q�Ԃœ��Z�B�������͉���K��i���тP�ԁj�A���c�ɑ��Y�A�g�c�P��A�x��g�i�Ă�����/���тR�ԁA���Ǝ��͎�ȁj�ȂǁB�x��g�͐��U�ɂ킽�閳��̐e�F�ƂȂ����B1904�N�i20�j�A���I�푈���u���B���N�A�C�R���w�Z���ƁB���N�A���ь��Ƃ��ď��m�́u���i�v�ɏ�D���A���{�C�C��Ńo���`�b�N�͑��ƑΌ��B�C�e���y��ō���̐l�����w�ƒ��w�������E�������������ꂽ�B�C��R����A�����ەa�@�ɓ��@�B���a�@�ɂ͕��������o���`�b�N�͑��i�ߒ������W�F�X�g�x���X�L�[����ߗ��Ƃ��Ď��e����Ă����B�މ@��A���m�́u�{���v�A��́u�����v�A�C�h�́u�����v�A�쒀�́u�z���v�ŊC��Ζ��B1908�N�i24�j�A���тƂ��ď��m�́u���h�v��u�@�J�v�i�͒��E��؊ё��Y�j�ɏ�D���A�@�J�ň�㐬���A�����C��A���O�Y����w�������B1911�N�i27�j�A�C�R�C�p�w�Z�ƊC�R�o���w�Z�̋����ɏA���A�����łS�ΔN��̕ē������Ɛe�������ԁB
1913�N�i29�j�A���e���������ŕa���B���X�N�A31�̂Ƃ��ɋ������ˉƘV�E�R�{�ѓ��i���Ă킫�j�Ƃ̗{�q�ƂȂ�B�R�{�Ƃ͕��c�M���̌R�t�E�R�{�����̌����B���N�A�R�{�̓t�����X�A��̖x��g�ƈꏏ�ɕ�炵�n�߂�B
����e�F�̖x��g��1913�N�Ƀt�����X�ɕ��C�B���̗��N�A�x�͑�ꎟ���E����ڂ̓�����ɂ��A�ߎS�ȑ��͐�A�ŃK�X��ɐ�傷��B�x�͋A����A�w�푈�P���_�x���܂Ƃ߁u������ꍇ�ɂ����č��Ƃ��s���푈�F���đP���ƂȂ��ׂ��炸�B�푈�Ȃ�s�ׂ͏�ɁA���A���A���Ȃ�v�Ə������B�x�́A�C�R�͐푈���d�|���邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A���a�ێ������̂��߂ɂ���ƐM�O�����B
1916�N�i32�j�A�R�{�͊C�R��w�Z�𑲋ƁB����ɒ��`�t�X�A�������a�A�������������B���N�A�R�{�Ɩx�͋��Ɍ������A�V���������R�ɍ\���ĉƑ�����݂̕t���������n�߂��B���N�A�R�{�͊C�R�Z�p�{���ɏ������R�������ɖv�����Ă����B
1919�N�i35�j�A�č��ɂĒ��ĕ����ƂȂ�{�X�g���̃n�[�o�[�h��w�ɂQ�N�ԗ��w�B�č��ł̓f�g���C�g�̎����ԍH��A�e�L�T�X��J���t�H���j�A�̑�K�͖��c�A���{��10�{�ȏ�̍H�ꐶ�Y�ʁA�L���Ȑ��������Ɉ��|���ꂽ�B�����A�����Y�o�ʂ͓��{��741���o�����A�č��͂S��4293���o�����Ɩ�60�{�̍�������A���{�ł͒��������������Ԃ��A�č��ł͔N��200��������Y����Ă����B�����A��s��NC-4���吼�m���f�ɏ��߂Đ������Ă���A�R�{�͍q��@�̐i���ɍł��S�����B
��1921�N�A�x��g�̓��V���g���C�R�R�k��c�ɐ����Ƃ��ďo�ȁB���{�͌R�͌����ׂ̈ɍ��Ɨ\�Z�̂R���̂P���₵�Ă���A��ȑS���̊C�R��b�E�����F�O�Y�Ɩx�͌R�k��]��ł����B���{�C�R�͐�͕ۗL�ʂ�Ήp�ĂV�����咣���Ă������U���ō��ӂ����B
1922�N�i38�j�A���B�E�č������@�B����̐푈�ɂ�����q��@�̏d�v�������������������A�A����ɍq����̋����������ƂȂ�B1925�N�i41�j�ɒ��đ�g�ٕt�����Ƃ��čĂѓn�Ă��A���X�N�A�����h�o�[�O�̑吼�m�g�������h���f��s�����̔M���ɐڂ���B���Ă���O�Ɍ��������R�{�́A���ۓI�Ȏ�������R�l�ƂȂ����B
1928�N�i44�j�A���m�́u�\��v�͒��A���u�ԏ�v�͒����C�B���N�A�����ɂȂ����R�{�͕⏕�͂ۗ̕L�������߂郍���h���C�R�R�k��c�i1929-30�j�Ɏ��Ȑ����Ƃ��ĎQ������i�R�{�𐄑E�����͖̂x�j�B���{�C�R�͂��̂Ƃ����Ήp��7�����咣�������A����X���Y�S����10�F10�F6.975�Œ��������B�����܂ł��V���ɂ���������ɖҔ������C�R�������R�{���u�R�l�͏オ���߂���R�I�𗐂��悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A���d����v�ƂȂ��߂��B
�������h���R�k���͊C�R�̑g�D�ɋT��ށB���Ɏ^�������g���h�h�͉����F�O�Y�𒆐S�Ƃ����x��g�A�R�����V�i��u�C�R�ȁv�B�������g�͑��h�h�͉��������Ȃǁu�R�ߕ��v�B
1930�N�i46�j�A�C�R�q��{���Z�p�����ɏA�C���A�q�͂̋�����ϋɓI�ɍs���A���Ԋ�ƂɁu���Ă�葬�x�ŏ���q��@���J������v�Ɣ��j���������B
1931�N�i47�j�A���{���R�����B�E�����œ얞�B�S���j���Ē����R�̂��킴�ƋU��A�U�����J�n��������Ύ������u���B���R�͂T�J���Ŗ��B�S�y�𐧈������B�R�{�͂��̌R���s���œ��{�����ۓI�ɌǗ����邱�Ƃ����O���A�嗤�ɂ�����g���헪�ɔ������B��C�ɔh�����ꂽ�x�́A���{���̍U�������Ԑl�ɔ�Q��^���Ȃ��悤���ӂ���Ǝw���B������͑��h�́u�퓬�ɏ��ɓI�v�Ɣᔻ�����B
1933�N�A���{�͍��ۘA������̒E�ނ�ʍ��B���N�A�C�R�ł͑�p�����i�݂˂��j�C�R��b��͑��h�i�R�g�h�j�ɂ��A���h�i�R�k�h�j�Ǖ��l������p�l�����n�܂�A�ŏ��ɏ��h�̒��S���������C�R�����E�R�����V�i�叫���R��ǂ��A�O�R�ߕ����E�J�����^�叫���\�����ɂ��ꂽ�B�R�{�͖x����邽�߂ɊC�R�g�b�v�A�͑��h�̒��S�l���E�����{�������i�Ђ�₷�����j�Ɂu�x��v�E�ɂƂǂ߂ė~�����v�ƒ��i�����B
1934�N�A������h���C�R�R�k��c�̗\�����̓��{��\�ɔC�����ꂽ�R�{�͓n�q�B���̌�A�p���ɖx��g���R��ǂ��\�����ɕғ����ꂽ�Ƃ̒m�点���͂��B�R�{�́u���m��1����Ɩx�̓��]�́A�ǂ��炪�d�v���������Ă���̂��B�C�R�̑�n���l�����v�ƕ������B�R�{�̖x���̎莆�u�N�̉^�������m�B�C�R�̑O�r�͐^�Ɋ��S�̎���Ȃ�B���̂悤�Ȑl�����s���鍡���̊C�R�ɑ��A�~�ς̂��߂ɓw�͂�����������v����v�i1934�N12���X���j�B1935�N�Q���ɋA�������R�{�́A�̋��̒����Ɉ��������莸�ӂ̓��X���߂����B�ޖ��܂ōl�����R�{���A�x���u���O�܂ŋ��Ȃ��Ȃ�����C�R�͂ǂ��Ȃ�v�Ɛ������R�����ɖ߂����B12���A�C�R�q��{�����ɏA�C�B���Y�q��@�̊J���ɐ��͂𒍂��B�R�{�͖x����炷�啪�̔_���܂ʼn��x���K��A�ďA�E��̔�s�@������Ђ��Љ���B
1936�N�i52�j�P���A���{�̓����h���C�R�R�k���̒E�ނ�ʍ��A�ȍ~�A�������R���g���̓���˂��i�ށB���N�Q��26���Ɂg��E��Z�����h���u�����A�����h�̊C�R�N�m�������������߂Ă����Ƃ�����ꊅ���Ēǂ��Ԃ��Ƌ��ɁA���c�[�����b�̋~�o�ɐs�́A�܂��e�e�R���𗁂т���؊ё��Y���]���̂��߂Ɉ�҂���z�����B12���A�i��C�g�C�R��b���琭����r���ĊC�R�����i�C�R�i���o�[�Q�j�ɏA�C�B
1937�N�i53�j�A�嗤��ḍa���������������Ė{�i�I�ɓ����푈���n�܂�B�����E�C�쓇�̌R����̂ɂ��ĎR�{�͕ĉp�Ƃ̊W���������O���Ĕ����������͋��s���ꂽ�B
1939�N�i55�j�A���R�𒆐S�Ƀ\�A���̂��߃h�C�c�A�C�^���A�Ƃ̌R�����������߂鐺��������B�����̓t�@�V�Y�����Ƃł���A�R�������͕ĉp�Ƃ̑Η����Ă�ł��܂��B�R�{�͒��Čo��������Ă̈��|�I�ȍ��͍���Ɋ����Ă����B�u���݁A���E�����n���āA��s�@�ƌR�͂ł͓��Ă��擪�ɗ����Ă���Ǝv�����A�������A�H�Ɨ͂̓_�ł͑S����r�ɂȂ�ʁB�č��̉Ȋw�����ƍH�Ɨ͂����킹�l���A�܂��A���̐Ζ��̂��Ƃ����Ƃ��Ă݂Ă��A���{�͐�ɕč��Ɛ키�ׂ��łȂ��v�B
�c�����댯�ɂ��炷�R��������j�~���邽�߁A�C�R�����̎R�{�A�C�R��b�̕ē������i�Q�N�O�A�R�{�������������C�R��b�ɏA�C�j�A�C�R�R���ǒ��̈�㐬���i�����悵�j�̂R�l�ŗ��R�ɒ�R�����i�ē��͘I�E�����ɁA���̓X�C�X�E���E�ɂɒ��o�����������j�B�ē��͗��R����ΕĐ푈�̏��Z�����u���Ă錩���݂͂���܂���v�ƒf���������A���_�͓��I�푈�̏�������u���{�C�R�͐��E�ŋ��v�u�A�����J�����ɑ��炸�v�ƕ����������Ă����B����ɂ́A�C�R��������������^���̐����N�����B�C�R�Ɨ��R�͗\�Z�̎�荇���ł��̂�������Ă������߁A�R�͌����ő��z�̗\�Z�Ă����C�R���A���ɂȂ��āu�푈�͂ł��Ȃ��v�ƌ����Ȃ����������炾�B
�R�{�A�ē��A���́g���h�R�l�O�h�́u�������v�Ɣᔻ����A�R���ǂɁu�ĉp�����o�ϓI�����𐬂����Ƃ��R����̂��v�Ɩ₢������R�{���A�E���́g�����h�ƌĂB�R�{�̈ÎE�v�悪�\�����Ȃ��A�O���������ɖ��������錈�ӂ������R�{�͈⏑���L�����B�u����ŌN���i�����j�ɕ�͕̂��l�̖{�������A���ꂪ���ł��낤���Ȃ��낤���ς��͂Ȃ��̂��B����A���Ŏ��ʂ��Ƃ������_�i�O�������^���_�j�ɒ�R���A���`���т��Ď��ʕ����{���͓����ςȂ��ƂȂ̂��v�i1939�N�T��31���j�B�����̌�q���t���A����ɋ@�֏e��������ꂽ�B���̌�A���{�Ƃ̌����i�܂ʂ��Ƃ���q�g���[�̓\�A�Ɠƃ\�s�N��������B���R�́u�\�A���̂��߁v�Ƃ�����`�������A�O�������̌��͑ł���ꂽ�B�����ɔ����Ă������a�V�c�́u�C�R���悭����Ă��ꂽ�������ŁA���{�̍��͋~��ꂽ�v�Ɗ�B
���N�W���A�C�R��b�E�ē������́A�g����ȏ�A�R�{�����R�ƑΗ�����Ζ{���ɎE�Q�����h�Ɛg�̈��S��S�z���A�R�{�𐭎��̕��䂩�牓�����邽�ߊC��Ζ��ƂȂ�A���͑��i�ߒ����i���́g����h�j�ɔC������B���̂Q����A�i�`�X�h�C�c���|�[�����h�ɐN�U���A���B�ő���E��킪�u�������B
1940�N�A�g56�h�ő叫�ɏ��i�B���N�U���A�h�C�c���t�����X�����������ĉ��B�̑唼���x�z����ƁA�R���ł́g�h�C�c�͉p����|���ɈႢ�Ȃ��A�h�C�c�ƌ��Ԃׂ��h�ƍĂюO���R�������̋C�^�����܂�B���R�͓����푈�ɍs���l�܂��Ă���A�ŊJ�̂��ߓ��������߂��B�����p���Ɛ���Ă����h�C�c�Ǝ�����߂A�ĉp�Ƃ̊W������I�Ɉ������푈�͔������Ȃ��B�������̎R�{�͘A���͑��ɐg��u���������f�̏�ɂ��Ȃ������B���R�Ƃ̋������d��C�R��b�E�y��Îu�Y�́A���R��b�E�����p�@�ɉ������A���ƈɎO�������̒��������肷��B���̕�����R�{�͌���y���b�ɋl�ߊ�����u���������߂Ă��������̐��{�̕����v��́A���̂W���܂ʼnp�Č��̎��ނł܂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���܂����B������ɎO�������̐������������ł́A�p�Ă��̎��ނ͕K�R�I�ɓ���ʂ͂��ł���܂����A���̕s���������Ȃ����߁A�ǂ������v��ύX�����ꂽ�̂��������Ē��������v�u�������ق��Ă���v�u���قł��ނ��I�v�B
�R�{�͋߉q��������u�������{���A�����J�Ɛ푈������ǂ�Ȍ��ʂɂȂ�Ǝv�����v�Ɩ���A�����������u���Ɍ��ꓹ�f�B�����͐�͂Ŗ��𗎂Ƃ����낤�B�����ē������゠����͎O�x���炢�ۏĂ��ɂ���Ă��܂����낤�v�B
1940�N�X��27���A���ƈɎO����������������R�{�͋L���B�u�����ł͍��͖łтȂ��B���A�푈�ł͍����łт�B����������邽�߂ɁA�푈�ɓq����Ƃ́A��q�]�|�i���ォ���Ă�Ƃ��j���͂Ȃ͂������v�B�����ĎR�{������Ă����ʂ�A�č��͗��N�W���A���{�ւ̐Ζ��֗A�ɓ��݂������B�Ζ��̂W����č��ɗ����Ă������{�͒ǂ��l�߂��A�Ζ������邽�߂ɓ���̉p�ė��̐A���n��D�����j�𗧂Ă�B
���u�č��ȂǑ�a���̑O�ł͂ЂƂ��܂���Ȃ��v�Ƃ������_�ւ̎R�{�̓����B�u�č��l���ґƂ��ア�Ƃ��v���Ă���l������������{�ɂ͂���悤�����A����͑�ԈႢ���B�č��l�͐��`���������A�̑�Ȃ铬���S�Ɩ`���S�������ł���B���������E����̗��t�����鎑���ƍH�Ɨ͂�����B���{�͐�ɕč��Ɛ키�ׂ��ł͂Ȃ��v�B
1941�N�i57�j�ɓ���Ɠ��{�͑ΕĊJ��ւƓ˂��i�݁A����Ȃ��ƂɑΕĐ푈�������ׂ��w�͂��Ă����R�{���U�����𗧈Ă��闧��ɂȂ��Ă��܂��B�߉q��������ΕĐ푈�̌��ʂ����ꂽ�R�{�͂����������B�u������ƌ�����Ώ��ߔ��N��1�N�̊Ԃ͐����\��Ă����ɓ����B�������Ȃ���A�Q�N�R�N�ƂȂ�ΑS���m�M�͎��ĂʁB�O����o�����̂͒v�����Ȃ����A�����Ȃ肵��͓��Đ푈���������l�A�ɗ͌�w�͊�Ђ����v�B
���N10��11���̖x��g�ւ̎莆�u�吨�͊��ɍň��̏ꍇ�Ɋׂ肽��ƔF�ށB�l�Ƃ��Ă̈ӌ��i�J�픽�j�Ɛ����̌��ӂ��ł߁A���̕����Ɉ�r簐i�̊O�Ȃ����݂̗���͂܂��ƂɕςȂ��̂Ȃ�B��������i�V���j�Ƃ������̂��v�B�T����A���ďՓ˂�������悤�Ƃ��Ă����߉q���t�͑ސw���A10��18���A������t�����������B
�č�������ƂȂ�ƒʏ�̍��ł͏����̌����݂��Ȃ����߁A�R�{�́u�^��p��P���v���v��B�J��Ɠ����ɐ搧�U���ő�Ō���^���A�č����̐�ӂ��������Ĉ�C�ɐ푈�I���ւƓ������Ƃ����B����A���ł��^��p�U���𒆎~���Ĉ����Ԃ��̐����g�B11��13���A�C�R�w�������W�߂āu�i�푈����́j�ΕČ������������Ȃ�Ώo�������Ɉ����g���𖽗߂���B���߂���̂����Ȃ�Α����P�ނ���v�ƌP���B�����̎w�������u���͂��̎����ɂ͊��ɓG���ɔ�э���ł���A�����I�Ɏ��s�s�\�v�ƈًc��������ƁA�u���̖��߂��ċA�ҕs�\�ƐM����w�����͑������\���o���v�Ɣ������B
1941�N12���Q���A�Ō�܂Ő푈����̖]�݂��̂ĂȂ������R�{�́A���a�V�c�̒�ł���C�R�Q�d�E�����{��m�e���ɗ��ݍ��݁A�Z�i�V�c�j�ɊJ��������悤���i���Ă�������B������ēV�c�͓�����S�l�ɑ��k�������A�J��H���ɕύX�͖��������B���̓��A�x��g�͎R�{�ɋɔ�ŌĂяo���ꂽ�B�u�ǂ������v�u�Ƃ��Ƃ����܂�����v�u�������c�v�u�����x���c�����Ƃ��A���������Ì�������l�Ȃ��ƂɂȂ�A�o�������͂��������Ԃ������̎蔤�͂��Ă��邪�c�ǂ����ˁv�B�Q����A�x�͉��l�w�ŎR�{�ƈ�������킵�Č�����B�u����A���C�Łv�u���肪�Ɓc�������͋A���ȁv�B���ꂪ�Q�l�̍Ō�̕ʂ�ƂȂ����B
��S�͑��i�ߒ����E��㐬���̊J�팈���̉�z�u�R�{����A��ςȎ��ɂȂ�܂����˂ƌ����Ɓg����h�ƌ����Ă܂����B��́A���c�C�R��b�͂����������ƂɂȂ������Ƃ��A���Ƃ̑厖���Ƃ������Ƃ����Ă�ł��傤���˂ƁA���Ɏ��͕s���ł����ƌ������̂��A�R�{�����������ł���A�g����͂��߂ł����j������ȁh���āB������R�{������g�����A�����܂ŗ������ǂ��A�����h�ƍl������Ȃ��ł����v�B
1941�N12���W���A�����U���i���n���ԂV���ߑO�U�����j�A�U�ǂ̋����܂�30�ǂ̊͑����^��p���ɓ����B��ꂩ��350�@�̐퓬�@�A�����@�A�}�~�������@����ї������B�č��͓��{���R���s�����N�����Ȃ�}���[�������t�B���s���ɏ㗤����Ɠǂ�ł������߁A���S�ɋ���˂��ꂽ�B�V��53���A�u������P�j�����Z���v��\���u�g���E�g���E�g���v���œd����S�@�ˌ��B�u�A���]�i�v�Ȃǐ�͂T�ǂ𒾖v�����X�ǂ��j���A188�@�̔�s�@�������H�Ŕj��A�đ��͖�3600�l�����������i��������2400�l�j�B�������A�ő�̕W�I�������G���͉��K�̂��ߍ`���ɂ��Ȃ������B��Q�g�U���̕K�v�����������U�����w�������͑��h�̓�_����E�i�ߒ����͍q���ł͂Ȃ��A�͒��̏��Ղ�����Ĉ����Ԃ��Ă��܂����B
���̐킢�ɓ������ꂽ�[����i�뎮�͏�퓬�@�j�͋@�̂��y���A�����̏펯��ł��j��q�������Ɛ��E�ō��̉������ւ����B�q��@���������������͂�������50m�قǒ���ł���G�Ɍ������ĕ��サ�Ă������A�^��p�͐��[����14m�����Ȃ����߁A���n�ȃp�C���b�g�ł͋������C��ɓ˂��h�����Ă��܂��B�R�{�̓p�C���b�g���������x���P�������Đ��ʃM���M�����瓊�������邱�Ƃɐ��������B�P���ɌP�����d�ˁA�s�\���\�ɂ����B
�^��p�U���̂P���ԑO�ɁA���{���R�̓}���[�����̏㗤�ɂ������B�����A���{�C�R�q������t�B���s���E���\�����̃A�����J�R�q���n�����q��@�𑽐��j���B
���̊�P��A�R�{�͜��R�Ƃ���B�u��P�ł����Ă����z���O�ɍU�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ۓI���[�������邽�߁A�R�{�͌R�ߕ��ɑ��A�^��p�U���̑O�ɐ��z�����s�����Ƃ����x���O�������Ă����B�Ƃ��낪�����I�ȃ~�X�Ő��z���͕đ��ɓ͂��Ă��Ȃ������B����ɂ��R�{�͕��m�̒p�J�ł���g���܂������h�̉�����w�������ƂɂȂ�B���[�Y�x���g�哝�͕̂č����Ɂu��x�Ƃ��̂悤�Ȕ������s�ׂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɖ������A�č����́u�������o�[�E�p�[���n�[�o�[�v���������t�ɒc���B�R�{�͎��g���`���Ă����푈�̑����I���Ƃ͐^�t�ƂȂ�S�ʏՓ˂ɕđ��̑ǂ�点�Ă��܂����B�č��͈�N��ɂ͔N�ԂQ���T��@�ȏ�̍q��@�Y����B
1942�N�i58�j�A�^��p�U���̗��������A�����͐폟�C���ɕ����Ԃ��Ă������A�R�{�͌É���ꈶ�̎莆�Ɂg�^��p�͉p�Ăɂ��Ă݂�Ύ������ɂ�����Ǝ����܂ꂽ���炢�Ȃ��́h�Ɨ�ÂȌ������L���A�u�����̌y���Ȃ鑛���͐��ɊO���������ƂɂāA���̗l�ɂĂ͓����̈ꌂ�ɂĂ����܂��k�ݏオ��̂ł́v�u���߂ăn���C�ɂċ��̎O�Ljʂ������ߒu���Ǝc�O�v�i1942�N�P���Q���j�ƒԂ��Ă���B�Q���A���͂��u��a�v�ɕύX�B
�U���T���A�č��̍��͂��l���đ��������ɂ���������R�{�́A�^��p�U���Ŏ�蓦�������ċ������ł��ׂ��A�q���͂S�ǂ���Ƃ���47�ǂ̑�@�������ŁA�����m�~�b�h�E�F�[�����̕ČR�����n���U�������B�����A�Í������O�ɉ�ǂ���đ҂������U�����A�����S�ǂ����߂��i�ԏ�A����A�����A�j�A�d���m�͂P�ǁA�q��@��300�@�A������3000���ȏ���u���ԂɎ������B�Ђ�č��͋��1�ǁA�q��@��150�@�̔�Q�ɂƂǂ܂�A���̑�s�����ɐ푈�̎哱�����A�����J�Ɉڂ��Ă��܂��B���{���ɂ̓��[�_�[���Ȃ��������Ƃ����s�̕�����ڂƂȂ����B���q�����i�ߊ��̎R�����������͒��v����u�v�Ɖ^�������ɂ����B
1943�N�Q���A�K�_���J�i�����ŌǗ����Ă������{���i���ɐ펀�Q���A�����쎀�҂P���T��l�j���~�o���邽�߁A������쒀�͂�S�ē�������P�����̋~�o�ɐ����B���̂Q�J����A�S��18���ɎR�{�̓��o�E���ŏ��������サ�A�����čőO���̃u�[�Q���r�����o������n�֕��������������ߎ��@��s���A�Í��d�����ǂ����ČRP-38�퓬�@18�@�̑҂����������B�R�{����q����퓬�@�͂U�@�B���̍U���̑O�A�����m�͑��i�ߒ����E�j�~�b�c�́g�R�{�����D�G�ȌR�l����C�ɂȂ�Ȃ�U������T���˂h�Ɩ{���Ɏf���𗧂Ă��B�́u�R�{�ɑ���悤�ȌR�l�͎R�����������A�ނ͐�̃~�b�h�E�F�[�C��Ő펀���Ă���̂ŎR�{�@�����Ă��č\��Ȃ��v�B�R�{�@�͂V��45���Ɍ��Ă���A�S�[�͓��I�푈�Ŏ���ꂽ����̎w�Ŗ{�l�m�F�����ꂽ�B�R�{�͉E��ŌR�����������܂ܐ▽���Ă����B���N59�B�R�{�̓��o�E���Ɍ������O�ɁA�┯���ɓ���Ėx�ɑ����Ă����B
�U���T���A�����Ƃ��č����B�����ψ�����ē����������߁A�i�Ւ��͊C�R���w�Z�����̉���K�ꂪ���߂��B�����������ɂ��ꂽ�̂́A��O�ł͎R�{�����P�l�ł���B�����͑�`�@�a�������ˑ勏�m�B���O�ʁE��M�ʁE���ꋉ�B�l�X�̊ԂŎR�{�͐_�i�����ꂽ���A�R�{���g�͌R�l�̐_�i����ь������Ă������Ƃ���A�g�R�{�_�Ёh�̌����̘b���o��ƁA�u�R�{�����f����v�ƁA�ē������A�x��g�A��㐬���炪���������A�_�Ђ͍���Ȃ������B
��͓����̑����쉀�̃��C���X�g���[�g�Ƃ���������ʋ�ɂ���B��̕����͕ē����������|�B�E�ɓ��������Y�����A���ɌÉ�叫�̕悪���ԁB��N�A�⍜�͐V���������s�̒������ɉ������ꂽ����͑����쉀�Ɏc���ꂽ�B
�u�����E����āA�����������ł��l�������Ă����႟�A����ł�������v�i�C�R��v���E����叕���̎莆�j
�x��1959�N��75�Ŗv�����B�ӔN�̖x�͎R�{�̖{�S�𐢂ɓ`���邽�ߎ�L�w�ܕ��^�i���ق��낭�j�x���܂Ƃ߁A���̂悤�ɎR�{�̐^�ӂ��܂Ƃ߂Ă���B
�E�ΊO���d�_�����Ă��ċ�В��������悤�Ȍ������D�܂��肵���B
�E���ƐڋߎO�������ɂ͐g����q���Ĕ������肵���B
�E�Ήp�Đ푈�ɂ��Ă͑�`�����̏���A�y�сA���ƈ���i���j�̌ڗ��i�����j���肵�āA���{�I�ɔ������肵���B
�E���S�i���イ����/�^�S�j��莞�ǂ̕��a������M�]�����肵���B
�E�͑��i�ߒ����Ƃ��Ă͍��Ƃ̗v�����鎞�ɂ́A���Ƃ��l�Ƃ��Ă̈ӌ��Ɛ����Ȃ�Ƃ�����A���s���ڗ����邱�ƂȂ��őP��s�����Ă��̖{���Ɉ�r簐i���ׂ����̂Ȃ�ƂȂ��鎖�B
���V���������s�ɎR�{�����L�O����������R�{�̋���������B�������ɂ͐��Ƃ̍���Ƃ���������Ă���B
���R�{�͏��w�������������t�@�����^�[�ɂ����J�ɕԎ��������Ă����B
�����Ă��ꂽ����@�̍����������̎R�{�\�Z�L�O�قŌ��J����Ă���B
���R�{�͏����ɂ��āu�\�����ɂȂ����烂�i�R�ɏZ�݁A���[���b�g�Ő��E�̊Րl�̋��������グ�Ă��v�ƌ���Ă����B
���R�k��c�œn�Ē��A�R�{���R�[�q�[�ɑ��ʂ̍��������邽�߁A���Ȏ҂��u�����Ԃ�Ó}�ł��ˁv�Ɛ���������ƁA�u�ł��邾���A�����J�̕������g���Ă��v�ƃW���[�N�B
���u�����͐�ɉR���]���Ă͂Ȃ�ʁB�R���]���l�ɂȂ�����A�푈�͕K��������v�i1942�N�R���j�B
���u�G�͂����ċ��ꂴ����A�����ɂ͋��ꂢ�邱�Ƃ�����B�������X�i�ӂ�Ղ�/�ŗ�j�Ƃ��ӂׂ����v�i1942�N11���j
���R�{�͒����̕����w�i�n�@�x�ɂ��鎟�̈�߂ɋ������Ă����u���i���Ɂj��Ȃ�Ƃ����ǂ��킢���D�߂ΕK���S�ԁB�V�������Ƃ����ǂ��킢��Y���ΕK���낤���v�B
���u�ꏫ��F����������ɂ��ނ̂Ƃ��ɂ��炸�B�����A���̐l�����āA�Ăт��̐l�Ȃ��v�i�x��g�j
�k�Q�l�����l�w�R�{�\�Z�̂��Ƃx�i��얾�Y�j�A�G���J���^������S�ȁA�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T�A�w�R�{�\�Z�̐^���x�iNHK�j�A�wTHE���j��`�x�iBS-TBS�j�A�E�B�L�y�f�B�A�B
|
����� ����/Shigeyoshi Inoue 1889.12.9-1975.12.15 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 86�j2011
 �@
�@ �@
�@
 |
 |
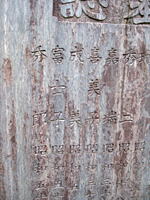 |
| �����쉀�̉��܂����ꏊ�ɖ����Ă��� | �u���ƔV��v�B�����̊C�R�叫�I | ������R�ԖڂɁu�����v |
| �Ō�̊C�R�叫�B�{�錧�o�g�B�R�{�\�Z�A�ē�������Ɠ��ƈɎO�������ɔ������B��͋��C��`��ᔻ���A�C�R�̋�R����͐��B�R���ǒ��E��l�͑������E�C�R�����Ȃǂ��C�B�C�R�R�ߕ����哱�����u�R�ߕ��ߋy�яȕ��ݏK������āv�ɋ��������A��_���ꂪ�u���O�̂悤�ȓz�͎E���Ă��܂����v�ƌ��V����ƁA�p�ӂ��Ă����⏑���o���āu�������Ȃ���B����ł��ӎu�͕ς��Ȃ��v�Ƃ͂˂����Ƃ����B�R���ǒ��E��l�͑������E�C�R�����Ȃǂ��C�B�J�팈�莞�A��������u�J�킨�߂łƂ��������܂��v�ƌ����A�u�����߂ł������o�J�����E�v�Ǝ�������Ƃ����B ����㐬����^ �E�u�q�b�g���[�͓��{�l��z���͂̌��@���������A�������h�C�c�̎��Ƃ��Ďg���Ȃ�A����p�ŏ������Ŗ��ɗ������ƌ��Ă���B�ނ̋U�炴��Γ��F���͂���ł���A�i�`�X���{�ڋ߂̐^�̗��R�������ɂ���̂�����A�h�C�c�𗊂ނɑ���Γ��̗F�M�ƐM���Ă�������́A�O�v�O�Ȃ̗v����A���������ށv �E�u���R�̖{���́A���Ƃ̑�����i�삷�邽�߂ɂ���B�����̓����ɒy���Q���邲�Ƃ��́A���̖{���Ɉᔽ���B�O���i��ꎟ���j�ɁA���{���Q�킷����ד��Ȃ�B�C�R�������i���ƈɎO�������j�ɔ�����傽�闝�R�́A���̍��R�̖{���Ƃ������{�ϔO�ɔ�����B�����鎩���I�Q��̖��Ȃ�B���Ƃ����������A�����U������ꂽ��ꍇ�ɂ��A�����I�Q��͐�ɕs�^���ɂ��āA���̐��͍Ō�܂Ō������ď��炴�肫�v���W�c�I���q���ɔ����Ă���B |
���ē� ����/Mitsumasa Yonai 1880.3.2-1948.4.20 �i��茧�A�����s�A�~���� 68�j2012
 �@
�@ �@
�@
 |
  |
| ���ĊJ��ɔ������E�C����C�R�叫 | ��O�̈ē����ɂ́u�~���̈̐l�@�ē������V��v�Ƃ����� |
| ��37����t������b�ł�����ĊJ��ɔ������C�R�叫�B��23��A���͑��i�ߒ����B���I�푈�ɏ]�R��A���[���b�p�ɒ��݁B���O�̍��͍���Ɋ�����B�V�c�̐M���������A1940�N�A60�ŊC������ƂȂ邪�A���ƈɎO�������ɔ����A���R�ɂ�蔼�N�Ŏ��E�ɒǂ����܂ꂽ�B ����ސw��A������t�łS�x�ڂ̊C���ɕ��A���A��A���v玁A�����̊e���t�̊C��������ɗ�C���A�����m�푈�I���Ɛ�㏈���ɐs�͂����B�M�ꓙ�A�]��ʁB |

���I�� ����/Tadamichi Kuribayashi 1891.7.7-1945.3.26 �i���쌧�A����s�A������ 53�j2008
 �@
�@
 |
 |
 |
| �C�Ï��i�����j����e��������̂ŌR�������Ȃт� | �������̎R��Ɂu�G�R�[���E�h�E�}�c�V���v�̒g�� | �����ƕ���̃R���{�ɋ������i���v�ԏێR�M�H�j |

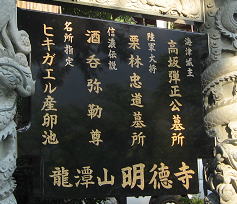 |
  |
| ���ʂ̈ē��Ɂu�I�ђ����v�̖��O���h�[���Əo�Ă��� |
�u����������̎莆�E��f�L�O�@�N�����g�E �C�[�X�g�E�b�h�ēv�ƍ��܂ꂽ�����̐Β� |
 |
 |
  |
| �[�z�𗁂т�I�ђ����̕�B���ĊJ��ɔ����Ă��� | �u���R�叫�v�Ƃ��� | �������̓��{���͐��s���ŋꂵ�̂ŁA�~�l�����E�H�[�^�[���S�{���������Ă��� |
|
�������̐킢���w���������R�叫�B���쐶�܂�B�Ⴂ���̓W���[�i���X�g���u�]���Ă����B1914�N�i23�j�A���R�m���w�Z���ƁB1923�N�i32�j�A���R��w�Z�����Ȃő��Ƃ��A�V�c���牶���i���j�̌R�������^�����B���N�������O�q�����������B
1927�N�i36�j�A�����⍲���Ƃ��ĕč����V���g��D.C.�ɒ��݂��A�n�[�o�[�h��Ŋw�ԁB1931�N�i40�j�A�J�i�_���g�ٕt�����ƂȂ�J�i�_�֕��C�B1940�N�i49�j�A���R�����ɏ��i�B���ĊԂɐ푈�̋C�^�����܂�Ȃ��A�C�O�����������č��ʂ̌I�т͍Ō�܂ŊJ��ɔ�����B1941�N�i50�j�A12���ɊJ�킷��Ƒ�23�R�Q�d���Ƃ��č��`�ցB1943�N�A���R�����ɏ��i�B������1944�N�i53�j�U���W���ɗ������̎�������i�ߊ��Ƃ��Ē��C����B
�I�т͕č��Ƃ̈��|�I�Ȑ�͍����n�m���Ă���A�������ɋ���Ȓn���w�n��z���S����v�lj����A�ČR�㗤�O�͖̊C�ˌ����g���l���ł��̂����B1945�N�Q��19���ɕČR���������ɏ㗤���J�n����ƁA�ŐV�s�̑����ł����߂��ĊC�����V���l�ɑ��A������H�����R�������{���Q���l���Q�����U���œO��R�킵���B�Q��23���ɋ��_�̐����R��ČR�ɐ�̂�������R�͑����B�I�т͕������ɖ��d�ȋʍӓˌ����ւ��A�{�y�h�q�̎��ԉ҂��̂��߂Ɏ��v��֎������B�������̖ʐς͓����s�̖ʐς�100���̂P�����Ȃ��A�ČR�i�ߕ��́u�T���ԂōU���\�v�ƍl���Ă������A���{�R�͂�����ꃖ��������肫�����B�R��16���A�I�т͑�{�c�ɍŌ�̌��ʓd���œd�B�������ɍŌ�̎w�߂��������u���c��17���鑍�U�������s���G�����ӂ���Ƃ��B�Ō�̈ꕺ�ƂȂ�������܂Ō����������ׂ��B���͏�ɏ��N�̐擪�ɂ���v�B������đ�{�c�́A�I�т𗤌R�ŔN���ƂȂ�53�ŗ��R�叫�ɏ��i�������B���ʓd���10����A�R��26���ɍs�Ȃ�ꂽ���{�R�Ō�̑��U���ɌI�т͊K���͂��O���ĉ����U�����B�I�т͓��{�R�Ŏj�㏉�߂ēG�w�֓ˌ����������R�叫�ƂȂ����B�����̋�́u���ׁ̈@�d���w���@�ʂ����Ł@��e�s���ʂā@�U�邼�߂����v�B
����22�N���o����1967�N�ɌM�ꓙ�ɏ������A��������͂����^�����B2006�N�A�I�т̍Ō��`�����f��u����������̎莆�v�i�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ēA�n�ӌ��剉�j�����J����A���̖����L���m����悤�ɂȂ����B
�������̐킢�ł́A���{�R20,933���̂����A����96������20,129�����펀�����B����A�ČR�����܂��펀��6,821���A�폝��21,865���Ƃ����c��ȋ]�����o�����B�P�����L��������1400���̗��R���m�����������́A���A���đo���������ԗ�Ղ��s�Ȃ����E�ŗB��̓y�n�ɂȂ��Ă���B
������������c�������i���������j�ɑ������莆�B�u��������́A���ƂɋA���āA���ꂳ��Ƃ���������A��Ē�������Ă��閲�Ȃǂ����X���܂����A����͂Ȃ��Ȃ��o���Ȃ����ł��B���������B��������͂�������傫���Ȃ��āA���ꂳ��̗͂ɂȂ��l�ɂȂ邱�Ƃ�����v���Ă��܂��B���炾����v�ɂ��A�������A���ꂳ��̌��������悭���A��������Ɉ��S������悤�ɂ��ĉ������B��n�̂���������v�B |
������ �K��/Kotoku Sato 1893.3.5-1959.2.26 �i�R�`���A���c��S�������A��c�� 65�j2014
 �@ �@ |
| �R���l������{�������S�����C���p�[�����B���������͂P������l�̕������쎀����~�����߁A ���R�j�㏉�ƂȂ閽�߈ᔽ�̓ƒf�P�ނ��s�����B����͌R�@��c�ɂ����鎀�Y�o��̍s�������� |
 |
 |
 |
| ��c���̓����͍���47�����Ɣ��Α��I | �R��ׂ͍�����������������{����Ă��� | ��c���̖{���B����ɐi�ނƕ�n�� |
 |
 |
| �u�����K�������Ǖ�̔�v�̖�� | �����ɂ͍��������̕�Q�҂̂��߂ɕW���� |
 |
 |
 |
| �{���e�ɖ����Ă����I | �������A��������������ł��I�I | �����ɂ�錰���肪����ɗ����Ă��� |
 |
 |
 |
| �u�����K���ƔV��v |
�����́u�`���@����K�����m�v |
�u����̂̐����~�������f�� �N�͖��ꂵ�R���̐ӂ߁v �C���p�[�����̃C���h���R�q�}�U����ɂ����ď��R�� �P�ތ��f�ɂ�萶�����ꂽ��炱���Ɋ��ӂ̐�������� ���a�Z�\�N�㌎�\�Z�� ��O�\��t�c���������L�u���V |
 |
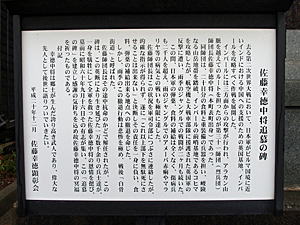 |
| ������̂���Ɍ���ɁA�����������Љ��ē��� |
�Ō�̕����u�K�������͋��y�����ւ荂�� ���l�ł���A�̑�Ȑ�l�Ƃ��Č㐢�Ɍ��p���� ���������@������\�N�\�@�����K��������v |
|
���R�����B�R�`���o�g�B�C���p�[�����ɂ����āA���{���R�j��A�O�㖢���̎t�c�ƒf�ދp���s���A�����̕����쎀����~�����B1913�N�i20�j�A���R�m���w�Z���Ɓi25���j�B1921�N�i28�j�A���R��w�Z�𑲋Ɓi33���j�B1930�N�i37�j�A���R�Q�d�{���̐�j�ۂɂQ�N�Ԕz������A�����œ����p�@�i��̑�40��j�⏬�隠���i��̑�41��j�ȂǓ����h�ƌ𗬂��A�����Ǝ�`�I�Ȕ閧���ЁE����̋K��쐬�ɂ��֗^�����B����̊���������A�����Q�d�{���ōc���h�̑����ے��E���c���i�ނ������j����ƌ��������܂ɂȂ����Ƃ����B���̖��c���Ƃ́A��15�N��ɗ��R�S�̂�h�邪������I�ȏՓ˂�����B1936�N�i43�j�A�c���h����E��Z�������N�����ƁA������U�t�c�Q�d�����������͓����h�Ƃ��Ēf�Œ������咣�����B
1938�N�i45�j�A���B������[�̍����Ń\�A�R�ƏՓ˂������ە�i���傤���ق��j�����ł́A������75�A�����Ƃ��ĎQ�킵�A���Q���T���ɒB���Ȃ�������܂Őw�n�����炵�A�����Ƃ��Ė���y����B 1944�N�i51�j�A�R��w�����r���}�i�~�����}�[�j����C���h�̃C���p�[�����U������u�C���p�[�����v���v�悷��ƁA�����͕⋋�̍�����咣���A���̂܂܂ł͕����̑唼���A���J���R���ʼn쎀����ƁA��15�R�i�ߕ��ɍ�펞�̕⋋�ʂ̊m������߂��B��15�R�i�ߊ��͈����̂��閴�c�������������B ��1944.3.8-7.3 �C���p�[����� �C���p�[�����͓��{�R�����j�I�s�k���i���A�g���d�h�s�ׂ̑㖼���ƂȂ������B1944�N�A�����m�ŃA�����J�R�Ƃ̋�킪�����Ȃ��A���{�R�͓����푈�𑁂��I��点�A�����嗤�ɔh�����Ă���100���l�̓��{�������R�Ƃ��ē�֑���K�v���������B����A�A�����̓C���h��������q�}�����z���̋�H�Œ����E�����}�R�ɌR�������𑗂�A�����̓O��R�킪�������B�s���l�܂������{�R�́A�C���h�����̓s�s�C���p�[�����U�����A�����x�����[�g���Ւf���悤�Ƃ����B ����S�������͖̂��c������i�ߊ��̑�15�R�A�W���U��l�̑啔���B��15�R�́A��15�t�c�i�R�������t�c���j�A��31�t�c�i�����K���t�c���j�A��33�t�c�i���c���O�t�c���j�ō\������Ă���B�p��R�͂��̓��{�R��{�߂�15�����̕��Ō}���������B ��헧�ē����A�R�����ł͓���킪���܂�ɕ⋋���y�������d������Ɣ��̐������������B�C���p�[���Ɏ��铹�͌������R�x�n�тŁA���ɒ����܂łɓ��{���͎Q���Ă��܂��ƍl����ꂽ�B ��j�����ҁE�g�쐳�����́u���̍�킪�@���ɖ��d�Ȃ��̂��v����₷���������Ă��遨�u�C���p�|�����Ɖ��肵���ꍇ�A�i�����̑�31�t�c���ڎw���j�R�q�}�͋���ɊY������B��31�t�c�͌y���t�߂���A��ԎR�i2542m�j�A����A�������x�i2890m�j�A���R���o�ċ���ցA��15�t�c�͍b�{�t�߂�����{�A���v�X�̈�ԍ����Ƃ���i���P�x3180m�j��ʂ��Ċ��������ƂɂȂ�B��33�t�c�͏��c���t�߂���O�i���鋗���ɑ�������B����30kg�`60kg�̏d�����œ��{�A���v�X���z���A�r���R���Ő퓬�������Ȃ���Ɍ��������̂Ǝv�����̑z���͕t���B����̕�⋊�n�i�����W�Ϗ�j�͉F�s�{�ɁA�����w������R�i�ߕ��̏��ݒn���C�~���E�͐��ɑ�������v�B �@  �@ �@ ���т�2000m���̎R�X�B�����ł����s�R�̍�����\�z����邤���A�Ԃ��Ȃ��J�G�ɓ��邱�Ƃ����肾�����i�N�ԍ~����9000�~���B���{�̕��ς͖�1700�~���j�B��̂悤�ɍ~�葱����J�œD��ɂȂ����R����啔���Ői�R�ł���̂��B�Ԃ��g���ʖ��тłǂ�����ĐH�Ƃ�⋋����̂��B����������15�R��56���g���̕⋋�������K�v�Ȃ̂ɁA�U���g����̗A���͂����Ȃ������B��15�R�����ō��ɔ����Ă����Q�d���E�����M�Ǐ����́A�A�C����͂�1�������Ŗ��c���i�ߊ��ɔ�Ƃ���A�㋉�i�ߕ��ɂ����������R�ł́A�����{�ɔ��������Q�d�����E��c�������X�R���ꂽ�B�C���p�[����픽�Ύ҂́u��a��������Ȃ��v�Ɣr������镵�͋C���R�ɕY���A���Ύ҂͎���Ɍ�������Ă������B ���c���i�ߊ��́u�����s���͓G�⋋��n���̂���ΐS�z�Ȃ��v�ƍl���A�܂��⋋�������������Ƃ��āu�W���M�X�J���v�����l�āB����́A���A���M�A�r�Ȃǂɉו���ς�ōs�R�����A�K�v�ɉ����ĐH�p�ɂ��Ă������̂������B���ʁA�r���}���R������r�A���M�������ƈړ������ɂ����i�����R�����̋��͌��n���B����Ă���A�_�Ƃ͖��̎��ɑ厖�ȋ������o���ꂽ�j�B���̑��A�瓪���̏ۂƁA�R�n�P���Q�瓪�������^���p�Ɏg�����ꂽ�B �������ĂR���W���A�C���p�[���U���킪�n�܂����B��15�t�c�Ƒ�33�t�c�͒��ڃC���p�[����ڎw���A�����̑�31�t�c�̓C���p�[���ɋ߂��R�q�}�ɐi�������B�����̍s�R�͏������������A����͉��n�֗U�����ނ��߂̘A���R��㩂������B�W�����O���̐i�R�͍�����ɂ߁A�ƒ{�̔������앝600m�̃`���h�E�B����n�͎��ɗ�����Đ����A����ɃW�����O����R�x���ŕ��m���H�ׂ�O�ɒE�����A�u�W���M�X�J���v���͏����̒i�K�Ŕj�]�����B���������r���}�̋��͒Ꮌ�n���D�݁A�����Ԃ̕��s�ɂ�����Ă��炸�A�����H�ׂ鑐���m�ۂł��Ă��Ȃ������B�R�����̉ƒ{�Ƌ��ɓk���s�R������{�R�͓G�����@�̊i�D�̕W�I�ƂȂ�A�ƒ{�������ׂ����܂ܓ����đ����̕������������B�������n�`�͏d�C�Ȃǂ̉^��������ɂ��A�����͏��Ί풆�S�ƂȂ�퓬�͂����������B �₪�Č��O����Ă����J�G���n�܂�A���������삪�s������Ղ�A�s�R���x�͂���ɒቺ����B�p�R�̑�K�͂Ȕ������n�܂�A�⋋���͐��f����A�h�{�����̓��{���͎��X�ƃ}�����A�Ɋ������Ă������B�O���ł͐키�O�ɉ쎀���镺�����o���A���{�R�ɂƂ��Ă̓C���p�[���Ő키�ǂ��납�A���ǂ蒅�����Ƃ�����]�I�ɂȂ����B ���̉ߍ��ȏō������������31�t�c�͉ʊ��ɐ킢�A�C���h�ƃr���}�̍����n�уR�q�}�𐧈�����B�Ƃ��낪�A�ꗱ�̕āA�ꔭ�̒e����͂��ʂ��߁A�R�q�}�ێ����s�\�ɂȂ����B�����͉��x���u���p������v�ƓP�ނ�i���������A���c���i�ߊ��́u�C�����̖��v�Ƌ��₵�A���p�������������B�����ĂT�����A���ɍ��������́u���{���R���v�ƂȂ�t�c���N���X�̖��߈ᔽ���g�ƒf�P�ށh��f�s����B����͗��R�Y�@��42���i�R���߁j�ɔ����Ă���A�����͌R�@��c�Ŏ��Y�ɂȂ�̂��o��̂����ŋt������B�����B�Ɂu�]�͑�31�t�c�̏������~���Ƃ���B�]�͑�15�R���~���Ƃ���B�R�͕����̍��܂ł���Ԃ�S�{�Ɖ�������A�����]�̐g�������ċ�������Ƃ��v�ƍ����A�i�ߕ��ɑ��āu�P�트��60���ɋy�сA�l�Ԃɋ����ꂽ��ő�̔E�ς��o�āA���������܂��s������B������̓��ɂ��Ăї������ĉp��ɑ��т�B��������ċ���������̂͐l�ɂ��炸�v�Ƒœd���A��31�t�c���R�q�}����⋋��n�E�N�����܂őދp�����A�����ɂ��e��E�H�Ƃ��F�����������߁A����Ɍ�ނ����B ���̍ہA�����̓r���}���ʌR���ɁA���̌������i�ߕ��ᔻ�d��𑗂����B �u�ł���߂Ȃ閽�߂�^���A���c�����̎��s���S�O������ƂāA�R�K���|�ɂ����ӂނ邪���Ƃ��́A�����ɑ��ĕs�\�Ȃ邱�Ƃ���������Ƃ���\�s�ɂ������v �u���ɂ����āA�e��i�̓������A���������S�{�̂��Ƃ����̂Ȃ�Ǝv���c�e��i�̖ҏȂ𑣂���Ƃ��錈�ӂȂ�v �u�v�쑺�Q�d���ȉ������̔\�͂́A���Ɏm�����ȉ��Ȃ�B�����������̏ɖ��m�Ȃ�v �u�i�ߕ��̍ō���]�҂̐S����Ԃɂ��ẮA���݂₩�Ɉ�w�I�f����������ׂ����@�Ȃ�Ǝv�l���v ���c���i�ߊ��͌��{���A�����t�c�����X�R�B����ƍ��x�͑�33�t�c���̖��c��������풆�~��i���������߁A���c���͖��c�������A�����Ďc���15�t�c�̎R�������i�}�����A�Ɋ����j���X�R�����B���Q���t�c�̑S�t�c�����X�R�����ُ펖�Ԃł���B�����������c���ɂ͓V�c�����ڔC�������t�c������C���錠���͂Ȃ��A���̉�C�͓�������Ƃ��s�ׂł������B�R���t�c���̐퓬�ڕ�i���n�̋L�^�j�ɂ́u���ɒe�Ȃ��A���⍋�J�ƓD�^�̒��ɏ��a�ƋQ��ׂ̈ɐ퓬�͂������Ɏ����B�������������āA����ɗ������炵�߂�����̂́A���ɌR�Ɩ��c���̖��\�ׂ̈Ȃ�v�Ɠ{�肪�Ԃ��Ă���B���{���͉p�R�A���@�����������G���̕������E���ċQ���𗽂������߁A���̕������E�����������g�D�����L�l�������Ƃ����B ���c�����l�]�����������R�ɁA�i�ߕ��ł̍s�����O���ɓ`���{����Ă��Ƃ�����B���m�������Q��ɋꂵ��ł���̂ɁA���c���͎i�ߕ��ɗ����݁B�����ߌ�T���Ɏd�����グ�A���̌�͌|�җV�тɖ������Ă����B���c���͎��g�̓��y�ׂ̈ɁA�킴�킴�|�W�A�����A�����l�A�������A�O�������A�����A�d�����A���A��ҁi�w�l�Ȍ���A��Ȉ�j���v150�l���ĂъĂ����B�u���c���t���̍D���Ȃ��́A��ɌM�́A��Ƀ��[�}�i�r���}��ŏ����j�A�O�ɐV���L�ҁi�L�҂ɑ����@���j�v�ƕ��������͕���Ă����B�u���c������̏�Ŏ��ʂ̂����͋����Ȃ��v�u�������߁v�ƌ������镺�m�������B ���J�n����S�J�����o�����V���R���A�悤�₭��풆�~�������Ɍ��肷��B�����ދp��ł��n���͑������B�H�Ƃ��Ȃ��͕ς��Ȃ��B�ԗ��A�}�����A���҈Ђ����X�ƍs�R����E�����Ă������B�ދp�H�ɂ͉쎀�҂����X�Ƒ����A�S�[�͍��J�ɒ@����A���ɐH���A�����ɔ����������B�P�ޒ��ɃW�����O���œ��������������́A�F�R�̔������㑱�����̓�����ׂƂȂ����B���{�������͂��̘H���u�����X���v�ƌĂB ���{�R�͎Q���W���U��l�̂��������҂V���S��l���펀�R���Q��l�i�唼���쎀�j�A�����҂S���Q��l�i�������Q�삩�炭���a�j�Ƃ������\�L�̋]���҂��o����ł����B ���c���͎Q�d�̓�����s�Ɏ�������킹�����A���悾���Ɠ����Q�d�͌������Ă����B �i���c���j�u���ꂾ�������̕������E���A�����̕�������������́A�i�ߊ��Ƃ��Ă̐ӔC��A���͕�����Ă��l�т��Ȃ���A����l�i���݂������ɂV�c�j��A�����̗�ɑ��ς܂�Ǝv���Ƃ邪�A�M���̕����̂Ȃ��ӌ��������c�v �i�����j�u�̂��玀�ʁA���ʂƌ������l�Ɏ����߂�������܂���B�i�ߊ����玄�͐ؕ����邩��Ƒ��k������������ꂽ��A�����Ƃ��Ă̐ӔC��A�ꉞ�`���I�ɂ��~�߂Ȃ��킯�ɂ͎Q��܂���B�i�ߊ��Ƃ��Ă̐ӔC���A�^�������Ă�����Ȃ�A�ق��ĕ�����ĉ������B�N���ז�������~�߂���v���܂���B�S�u���Ȃ�������ĉ������B����̍��i���s�j�͂��ꂾ���̉��l������܂��v ���ǁA���c���͎������Ȃ������B �V��10���A���c���͊������W�߂ċ����Ȃ���P�������u���N�A�����t�c���͌R���ɔw���R�q�}���ʂ̐������������B�H�������Ȃ�����푈�͏o����ƌ����ď���ɑށi�����j�������B���ꂪ�c�R���B�c�R�͐H�������Ȃ��Ă��킢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���킪�Ȃ��A���e�ۂ��Ȃ��A�H�������Ȃ��Ȃǂ͐킢��������闝�R�ɂȂ�ʁB�e�ۂ��Ȃ�������e�������邶��Ȃ����B�e�����Ȃ��Ȃ�A�r�ł�����B�r���Ȃ��Ȃ����瑫�ŏR��B�������ꂽ����Ŋ��݂��čs���B���{�j�q�ɂ͑�a��������Ƃ������Ƃ�Y�ꂿ�Ⴂ����B���{�͐_�B�ł���B�_�X������ĉ�����c�v�B���̌P�������X�ƂP���Ԉȏ�����������߁A�h�{�����ŗ����Ă��邱�Ƃ��o���Ȃ��������Z�����͎��X�Ɠ|�ꂽ�B�����Ė��c�����g�́A�e�t�c���A�҂���O�ɁA�u�k���P�ޘH�̎��@�v�𗝗R�Ɏi�ߕ��𗣂�Ă��̂܂܋A�������B ���c���͍����̐��_�Ӓ��v�����A�r���}�̃����O�[���Ƀ}�j���̗��R�a�@���琸�_�Ȃ̌R���сE�R�����Z�Ɠ�����R�R�㕔���������̋{�{�R�㒆�����h�����ꂽ�B�V��22���ɍ������������A24������Ӓ肪�n�܂�B�����̓}�����A���u�a�ɂ��S�g�r���̉\������������A�ʒk�Ő��_��Ԃ�f�f���ꂽ�B�R���R���тɂ��f�f���ʁu��풆�̐��_��Ԃ͐���ł������B�i���j�@���E�̂�����S�_�r���͂������A�S�_�Վ��Ԃɂ��������Ȃ�����͈͂̊��������ł���v�B�g���_�a�ł͂Ȃ��h�Ƃ����f�f�ɂ��āA�R�����킭�u�Ӓ茋�ʂ́i���_�a�ł����ė~�����Ƃ����j�ьR�i�ߕ��̊��҂ɓY���Ȃ������v�B ���������͍R���߂ɂ�鎀�Y�̐S�\���͏o���Ă���A�R�@��c�œ��X�ƍ��̋����������e������肾�������A�ŏI�I�ɏ�w���͍������g�S�_�r���h�����ɂ��đޖ������A�a�C�Ƃ������R�ŏ������Ȃ������B����͍ٔ��ɂ���č�편�s�̒Njy����w���ɋy�Ԃ��Ƃ��������Ƌ��ɁA�������Ă��܂��Ɛe��E�i�V�c���璼�X�ɔC��������E�j�ɖ��l����C�������V�c�́u�C���ӔC�v������邽�߂ł������B �C���p�[�����͕⋋���y���������d�E������ȍ��̂��߁A�����̋]�����o���ďI������B���̍�편�s�ŁA����܂ʼnp��R�Ƃ͌݊p�̌`���ɂ��������{�R�̐�������͕����B�p�R�̑�14�R�i�ߊ��X���������͉�z�^�Łu���{���R�̋��݂͏�w���ɂȂ��A���̌X�̕��m�ɂ���v�Ɖ��m�������^���B���̈���Ŏw�����ɂ��Ắu�ŏ��̌v��ɂ������A���p�̍˂��Ȃ��A�ߎ��𗦒��ɔF�߂鐸�_�I�E�C�����@�v�u���{�̍����i�ߕ��͉�X���킴�Ə��������v�Ɣ�����Ă���B 1959�N�Q��26���A������65�ŕa�v�����B�C���p�[������A���c���͗\�����i�ޖ��j�ƂȂ�A�����̎��̂V�N��i1966�N�j��77�ő��E�B���̑��V�ɂ����āA�u���͈����Ȃ��A�����������v�Ǝ������L�����p���t���b�g���A�⌾�ɂ��Q��҂ɔz�z�������B���c���̂��́g���C�h�̔w�i�ɂ́A����p�R�������u�����t�c�����̂܂ܐi�R���Ă�����R�q�}�̐�ɂ���v�Ճf�B�}�v�[���͗����Ă�����������Ȃ��v�ƌ�������Ƃɂ��邪�A���Ƃ����Ƃ���ŕ⋋���Ȃ��ێ��ł��Ȃ��͖̂����������B ���A���ČR��w���ɂ����҂͕ېg�̂��߂ɍ����̖��߈ᔽ���g���a�h�ƒ@�������A�R�`�����̒����l��ԗ������w�R�`����S�Ȏ��T�x�ɂ����̖��O���o�Ă��Ȃ��B�����̕�͌̋��������̏�c���ɂ���B�����ĕ��ɂ͍����̂������Ő��҂��������������������������肪���B���̕��ʂ͈ȉ��̒ʂ�B �w����̂̐����~�������f�� �N�͖��ꂵ�R���̐ӂ� �C���p�[�����̃C���h���R�q�}�U����ɂ����ď��R�̓P�ތ��f�ɂ�萶�����ꂽ��炱���Ɋ��ӂ̐�������� ���a�Z�\�N�㌎�\�Z�� ��O�\��t�c���������L�u���V�x �ӔN�̍�����m�铯���̏Z�E�E�������M���킭�u�i�����j���R�͈�ٖؕ����܂���ł����B�펀�҂̉Ƃɏo�����Ă͖ق��ďč����Ă������p���ڂɏĂ����Ă܂��v�B �u��{�c�A���R�A���ʌR�A��15�R�Ƃ����n���̎l�悪�C���p�[���̔ߌ������������̂ł���v�i�����K���j�B ���u���͓����Ɏ������ĂˁA���ە��̎����A�����Ƃ��Ĕh������A���x���܂���Ԉ����Ƃ���ւ�炳�ꂽ��v�i�����K���j�B ���C���p�[�����̍R���P�ނő�31�t�c�̎l���o�g�҂������~��ꂽ�B���쌧�����s�ɂ͌����m�炪�������������̌����肪����B ���E�B�L�y�f�B�A�ɂ͌R���j�����ƁE�y����������C���p�[����펞�̍��������ƕ����̋{��ɎO�Y�����Ƃ̕s����1979�N�́w���j�Ɛl���@���� ��^�E�����m�푈�x�i�������_�Ёj�ɋL�����Ƃ��� ���A�{�菭���̔����̏o�T�������璲�ׂĂ�������Ȃ��B�y�厁���������Ă��Ȃ��B���������̕揊�ɗ����Ҏ҂̊��ӂ̐Δ������ƁA�{�菭���̌��t������ۂɈ�a��������B���ǂ��ŋ{�菭���������ᔻ�����������̂��A�o�T���m�肽���B �k�Q�l�����l�w�m�g�j�X�y�V����/�h�L�������g�����m�푈 ��S�W�E�ӔC�Ȃ�����`�r���}�E�C���p�[���x�A�w���a�̖����Ƌ����x�i�����ꗘ�A�ۍ㐳�N/���t�V���j�A�E�B�L�y�f�B�A�ق��B |
������E��{�c�Ձi2008�j
 |
 |
 |
| �I�т̕�͕��ߎR�̑�{�c�Ղ̂����߂��B �푈�����A���R�͂����ɐ��{�@�ւ��ړ]���悤�Ƃ��� |
�c���̗\��n�͌��C�ے��n�k�ϑ����ɂȂ��Ă���B �p�l���Łu�V�c�̊ԁv�u�c�@�̊ԁv�����J����Ă��� |
�����̌����}�B�V�c�̊Ԃ͂P�����ɂ��B �I�펞�ɏ����{�c��75���܂Ŋ������Ă��� |
 |
 |
 |
 |
| ��B���i�n�����j�̓��� | �n����a�֑����K�i | �������~��Ă��� | �������͗����֎~�]�[�� |
|
�����m�푈�����A���{�̍��ƒ����@�\�ړ]�̂��߂ɏ���̎R���Ɍ@��ꂽ�n�����B���ߎR�A�F�_�R�A�ێR�̂R�ӏ��̒n�����̒����͌v10km�ɂ��Ȃ�B�l���K�ꂽ���ߎR�́g�V�c�̊ԁh�ȂǍc���̗\��n�������B���オ�I�ꂽ���R�͎��̂U�_�B�i�P�j�߂��ɔ�s�ꂪ����i�Q�j����ł�10t���e�ɂ��ς���i�R�j�R�Ɉ͂܂�Ă���i�S�j����͘J���͂��L�x�i�T�j����̐l�͏��p�Ō��������i�U�j�M�B���_�B�B1944�N11������@�킪�n�܂�A���̓ˊэH���ɂ͂̂�300���l�̐l���������I�ɓ������ꂽ�i�Ő����͒��N�l�V��l�A���{�l�R��l��12���Ԍ�ւœ����j�B�s�펞�͊���75���܂Ŋ������Ă����B���݂͋C�ے���1947�N������{�ő�K�͂̐����n�k�ϑ�����u���Ă���B
�����R�哱�ő���ꂽ�����{�c�ɑ��A�C�R�͓ޗnj��V���s�i��{���R�j�ɑ�{�c�̈ړ]���l���Ă����B ���l��������^�N�V�[�̃I���W����́u��{�c������O�ɐ푈���I����ėǂ������B���Ă����牽�x����������P����A�܂��T�ɂ��Ȃ��ĂȂ����������͐����Ă������ǂ���������Ȃ��v�B
|
������ �����Y/Heihachiro Togo �O��4�N12��22���i1848�N1��27���j-���a9�N�i1934�N�j5��30�� �i���������A�������s�A����R���� 86�j2002��08
 |
  |
| �����E�����쉀�̖{��B�ׂ͎R�{�\�Z�̕悾�B �s�S���痣��Ă��鑽���쉀�͕����Y�������� �������Ō��݂̂悤�Ȑl�C�쉀�ɂȂ��� |
�̋��̎������E����R�����̕�B������ɂ͈┯�������Ă���B��O�͉Ԃ������ς��I |
 |
  |
| 1879�N�A31�� �����Yin�p�� |
�������������Z�̈�p�ɂ���Δ�u���������Y�N�a���V�n�v�B �������v�ۂ������b�������ɐ��܂�Ă��� |
 |
  |
| ����ȏ�ɂ���I | ����R�������玭�����s�X�⎭�����p�A�����č�����]�ޓ��� |
 |
 |
| ��E���Ƃ̎q�A�g���Y�̕�i�R�쉀�j | ���̕��̉E���ɕ����Y�̕�v�q������ |
| �C�R�����B17�ŎF�p�푈�ɏo�w�B��C�푈�ł͌R�͏t���ۂɏ�D�B�ېV��͊C�R�̗��w���Ƃ��Ĕ��D�n���v�V���[���Ő��E�����̌����A�p���̑��D���œ��{�R�͂̌����ɗ�������ĐV�s�͂ŋA�������B���I�푈�ł͊��͂̎O�}����u�c���̋��p���̈��ɂ���B�e����w����w�͂���v�Ə���������B�����Ƀ��V�A�E�o���`�b�N�͑�����ł����A�C�O�ł��g���m�̃l���\���h�Ƃ��Ēm����B �����͏G�g�R�����N��N���������ɖh�킵���؍����̌R�t�E���w�b�i�C�E�X���V���j�h���Ă����B���w�b�͒��̖���������A�C�ݐ��̒n�`�𗘗p�����Ջ@���ςȐ�p����g���A�������E�ŋ��̓S�b�D���l�Ă����B���I�푈�I����̏j����̐ȂŁA�����́u�C�M���X�̃l���\����Ɨ��w�b�ɕ��ԁv�ƖJ�ߏ̂�����ƁA�u�i�i�|���I����j�����j�l���\����͂Ƃ������A�����͖����E�����R�ɂ͂ƂĂ��y�Ȃ��v�Ǝ^����ԏサ���B�������{���i���Ǝv���Ă��钩�N�R�̕������A�働�V�A��j�����������^�����錪�����ɐl�����_�Ԍ�����B |
���H�R �^�V/Saneyuki Akiyama �c��4�N3��20���i1868�N4��12���j-�吳7�N�i1918�N�j2��4�� �i�_�ސ쌧�A���q�s�A���q�쉀 49�j2010
 |
 |
  |
|
| �w��̏�̉_�x�̃��b�N�� �͊m���Ɏ��Ă��� |
�L��Ȋ��q�쉀�ɖ��� |
��17��X��������Ă��炭�����ƁA�E��ɏH�R�Ƃ̕悪���� |
|
 |
 |
 |
| ��������ƃV���v���ȗm���̕� |
�����ȌR�l�ł��邱�Ƃ͊O�����番���炸�A �^�V�̐^���Ȑl�Ԑ����`���悤�ōD�� |
�������疼�O ���m�F�ł��� |
�C�R�����B���R���܂�B�c���~�ܘY�B�Z�͗��R�叫�E�H�R�D�Ái�悵�ӂ�j�B���I�푈�ł͘A���͑��E���Q�d�Ƃ��Ē�����@���l�āA
�o���`�b�N�͑������ł���ȂǓ��������Y�������x�����B���{�C�C��ɍۂ��u�V�C���N�Ȃ�ǂ��g�����v�̌��t���c���B
���H�R �D��/Yoshifuru Akiyama ����6�N1��7���i1859�N2��9���j-���a5�N�i1930�N�j11��4�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 71�j2010
 |
 |
 |
| �R�쉀�̓�[�߂��ɕ悪���� | ���q�ɖ����E�^�V�ɔ�ו��͂��Ȃ�L�� | �ʐ^�̌���Ɍ�����̂͘Z�{�q���Y |
 |
 |
 |
 |
| ���{�R���̕� | �i�n�ɑ��Y�w��̏�̉_�x�ň�ʐl�ɂ��L���� | �s�S�ɂ����Q���₷�� | �D�Ái�悵�ӂ�j�m�F |
���R�叫�B���{�R���̕��B�c���M�O�Y�B�����E���I�푈�ɏo���B�R���āA�t�c���A���瑍�Ă��C�B���R�R���w�Z���Q�ςɗ����t�����X�R�l���킭
�u�H�R�D�Â̐��U�̈Ӗ��́A���B�̖�Ő��E�ŋ��̋R���W�c��j��Ƃ���������_�ɐs���Ă���v�B���I�푈�Ŋ����C�R�����E�H�R�^�V�͎���B
���k���ĎO�Y�̕悪�����߂��ɂ���B
���L�� ���v/Takeo Hirose �c��4�N5��27���i1868�N7��16���j-����37�N�i1904�N�j3��27�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 35�j2010
 |
 |
| ���I�푈�Ő펀���R�_��P���ƂȂ��� | �E�����v�B���͌Z�Œ鍑�C�R�����̍L������� |
| �u�R�_�v��P���B�����̑���{�鍑�C�R�R�l�B���啪���|�c�s�o�g�B���w�Z���t���o�ĊC�R���w�Z�ɓ��Z�B1894�N�i26�j�A�����푈�ɏ]�R�B���N�A��тɏ��i����B1897�N�i29�j�A���V�A�ɗ��w���Č�w���w�тȂ��烍�V�A�M����R�l�ƌ𗬂���i�I�C�R�卲�̖��A���A�Y�i�E�A�i�g�[���G���i�E�R�����X�J���Ɛe�����Ȃ����j�B���̂܂܃��V�A���ݕ����ƂȂ�A1900�N��31�ŏ����ƂȂ�B���N�A���B1904�N�i35�j�A���I�푈���u�����A���V�A�͑��𗷏��`�ɕ����߂�Ǎ��i�`�̓����ɈӐ}�I�Ɋ͑D�𒾖v�����`���g�p�s�\�ɂ���j�ɎQ���B��Q��Ǎ��ŕǑD����ۂ��w�����A�P�ގ��ɍs���s���ƂȂ��������i���쑷���㓙�����j���~������ׂ��D�����R�x�{���B���̌�A�~���{�[�g��œ����ɓG�C�e�����������������B���N35�B�v��A�����ɏ��i�B�������{�͍L����_�i�����A�R�_�Ƃ��Ď]���A���E�W�N��i1912�N�j�ɕ����ȏ��́w�A�������x�����ꂽ�B
���勠�q�A�������Y���Ɛe�����������B
|
���R�� ����/Tamon Yamaguchi 1892�N8��17��-1942�N6��6�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 49�j2010
 �@
�@ �@
�@
| �C�R�����B���{�C�R���\���閼��B������̊J�����w�J�Z�ȗ��̏G�˂Ƃ����A1921�N�i29�j�A�č��v�����X�g����w�ɗ��w�B1934�N�i42�j�ɂ͍ݕč���g�ٕt�����ƂȂ����B�y���m�́u�\��v�͒����o�āA1937�N�i45�j�A��́u�ɐ��v�͒��ƂȂ�B1940�N�i48�j�A���q�����i�ߊ��ɏA�C�B�R�{�\�Z���㐬���Ɠ��������Ă̍��͍����n�m���Ă���A�^��p�U���ł͑�̕K�v�����ÂɎ咣��������_�i�߂͎���Ȃ������B �~�b�h�E�F�[�C��ɑ��Ắg������̌P�����Ԃ��K�v�h�ƖҔ��������A���͌��s����Ă��܂��B�R���͋��u�v�ɏ�͂��A�G��͋��u���[�N�^�E���v���j������B�u�v����e����ƎR���͑����ފ͂𖽂��A����͊͒��E�����~�j�Ƌ��Ɋ͂Ɏc���ĉ^�������ɂ����B ���N�A�R�{�\�Z�̓���@���u�[�Q���r�������Ō��Ă����ہA�ď�́u�i���}���g������ŎR�����g�b�v�ɂȂ�Ƃ�����������j�R���͊��Ƀ~�b�h�E�F�[�Ő펀���Ă��邩����S���A���}���g�ɑ��蓾��l���͓��{�ɂ͑��ɂ��炸���ĉv�Ɣ��f�����B ���O�� �M�ꓙ���ꋉ�B�Z�̍Ȃ͑�v�ۗ��ʂ̖ÁB |
���i�c �S�R/Tetsuzan Nagata 1884.1.14-1935.8.12 �i�����s�A�`��A�R�쉀�������R��n 51�j2011
 |
  |
 |
| ���R�̐����Ȃ������h | �揊�͐R�쉀�̔�ђn�A���R��n�B�߂��Ⴍ����������I���y���O�̕悩��߂� | �u���R���� �i�c�c�R�v�Ƃ��� |
| �u�i�c�̑O�ɉi�c�Ȃ��A�i�c�̌�ɉi�c�Ȃ��v�ƌ���ꂽ���R�����Ă̈�ށB���R�����B���R��b��ʂ��č��@�I�ɍ��Ƒ��͐�̐����������邱�Ƃ�ڎw�����u�����h�v�̒��S�l���B���쌧�o�g�B���R�c�N�w�Z���Q�ʁA���R�m���w�Z����ȁA���R��w�Z���Q�ʂő��Ƃ��A�����̌R�������^�����B1920�N�i36�j�A���X�C�X��g�ٕt���ݕ����ƂȂ�A���N�A���m�����̏����q�l�Y�A�����J���A������̓����p�@��ƃh�C�c�Ŗ���A���R�ߑ㉻�̂��߂ɎF������r�����邱�Ƃ𐾂��B�i�c�̓G���[�g���Z40�l�����W������[�i���������j��̃z�[�v�ŁA�h�C�c�̍��h���ƌ��݂̎v�z���ŏ��ɗ��R�֎������B1932�N�i48�j�A���R�����ɏ��i�B���̌�A���R�ȌR���ǒ��ƂȂ�B�i�c�ɂ͂U�N�Ԃ̉��B���o��������A���{�Ɖ��Ă̍��͍��𐳊m�ɔc�����Ă����B�O���Ȃ����B���ł����ꂽ���ۊW�̏C���ɏ��o���ƁA�i�c�́u�\�r�G�g�ƕ��a�O����i�߂悤�Ƃ���O���Ȃ̍l���Ɏ^���ł��v�ƊO���Ȋ����ɐڋ߂����B�i�c�͋{���A���V�A���}�Ǝx�����L���A���R�c���h�i�}�i�h�j��ǂ��l�߂Ă����B�����Ĕߌ����B1935�N�W��12���A�����̗��R�Ȃōc���h�̑���O�Y�����Ɏa�E���ꂽ�B���N51�B�������A�����x�ɓ˂��h�����Ă����Ƃ����B �u�i�c���E����Ă��Ȃ���Γ��{�̎p����قǕς���Ă����B���邢�͑哌���푈��������ꂽ��������Ȃ��v�i�����R������ؒ��j�B �������o�g�̊�g�ΗY�i��g���X�n���ҁj�͐e�F�B �k�c���hVS�����h�l ���c���h�c�V�c���S�̍��̎����`��M�A���ڍs���ɂ�鍑�Ɖ�������Ă��}�i�h�B���\�E�����B���S�l���͍r�ؒ�v�叫�A�^��r�O�Y�叫�B �������h�c���@�I�ɗ��R��b��ʂ��č��Ƒ��͐�̐����������邱�Ƃ�ڎw�����B���p�E���āB���S�l���͉i�c�S�R�A�����p�@�B�i�c�̎���A�S�̎�`�F�̋����R���ɕϗe���Ă����B�i�c���[��I�I |
����E��Z����/��\��m�V�� 1936.2.29-8.19 �i�����s�A�`��A�������j2010
 |
 |
 |
| ���z�\�ԁA�������̒��������Q�� | �����̉��ɕ�n������ | �Ԃ��₦�邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ��� |
| ��E��Z�����ŏ��Y���ꂽ�g�c���h�h���R�l19���Ǝ�������2���A�����đ��V�O�Y�����̍�����B���V�����́g�����h�h�̗��R�R���ǒ��E�i�c�S�R�����𗤌R�ȓ��ňÎE�����l���B���������̎�@�̈�l�A�I�����G���т��������̒h�Ƃł�����������A�����ɕ揊���z���ꂽ�B ��̔w��ɒ����Ă��閄���҂̖��O�͖������� �i1936�N2��29���j�쒆�l�Y��с����� �i3��6���j�͖����с����� �i7��3���j���V�O�Y���� �i7��12���j���c�����с���@�A�����P�O��с���@�A�I�����G���с���@�A�|���p�v���сA���n���Y���сA��������сA�O���������сA��䒼���сA�c�������сA�����Ύ����сA���c�D���сA�������Y���сA�є��Y���сA�a��P���A���㌹�� �i8��19���j�����F���E��������с���@�A�镔���E���ꓙ��v����@�A�A���c�ŁE�����с���@�A�k�P���Y�i�k��P�j����@�B |
������ ���O�Y/Jizaburo Ozawa 1886.10.2-1966.11.9 �i�����s�A���c�J��A��g�� 80�j2014
 |
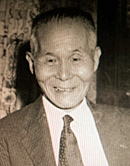 |
| �Ō�̘A���͑��i�ߒ��� | |
 |
 |
 |
| ��g���͓��}�d�S�E���c�J�w�̉w�O | �{�����̕�n�̒����̓������� | ���H�܂Ő����[�g���̏ꏊ�ɖ��� |
 �@ �@ |
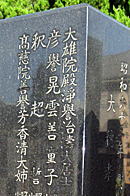 |
| �w���O�Y��x�B�q���͊C�O�ɂ���炵�� | �u��Y�@�a��_�����勏�m�v |
| �C�R�R�l�B���{�C�R�Ō�̘A���͑��i�ߒ����B1886�N�A�{��ɐ��܂��B�C�R�叫�E��㐬���͊C�R���w�Z�̓����B�_���̒B�l�ŁA�w������Ɍ�́g�_���̐_�l�h�O�D�v�����P���J�œ���������B���w�����̕��w�Z�ł͏㋉�������������ʂɉ����Ă������Ƃ���A����ɔ����ēS�����ق���߂������i���Ȃ݂ɗ��R�̓r���^�ŊC�R�̓Q���R�c�j�B���ƌ�A����͐����i�����A�@���Ȃǁj�̐��ƂƂȂ���1938�N�ɂ͐����w�Z�̍Z���܂Ŗ��߂Ă������A���������q���̏d�v�����������ƁA1939�N�i53�j�ɑ��q�����i�ߊ��ɏA�C���A�����W�߂ďW���I�Ɋ��p����@��������a��������B1940�N�i54�j�����ɏ��i�B���N�A�C�R��w�Z�Z���ƂȂ�B1941�N�̊J�펞�͓쌭�i�Ȃ�j�͑���C����A�W�߂̊͑��ŗ��R�ƘA�g���A�}���[�㗤���𐬌��������B ����͓��{�R�q��@�̍q�������̒��������A�G�̎˒��O�������I�ɍU������u�A�E�g�����W��@�v��҂ݏo���B�����A�c�O�Ȃ��珬�@���������w���ł���n�ʁi��1�@���͑��i�ߒ����j�ɏA�����̂�1944�N�i58�A�s��̑O�N�j�ł���A���̂���ɂ͂����A�A�E�g�����W��@�����s�ł���Z�ʂ̂���p�C���b�g�����ɂ��Ȃ������B�������ă}���A�i���C��ł͋��R�ǂƍq��@400�@�]�������B���̗��j�I�s�k�̍ő�̌����́A���O�ɕ����Ɂi�A���͑��Q�d���j���ߗ��ɂȂ�A�Í�������v�揑��S���D���Ă������Ƃ��i�C�R�������j�B�Í������ׂĉ�ǂ���i�Q�����镺�m�̐��A�͑D�E�q��@�̐��A�⋋�\�́A�w�����̖��O�܂őS���o���Ă��j�A��킪��������Ȃ��c�B �����āA���C�e�C��ł͚��i���Ƃ�j�����̎w���𖽂����A���l�̈��S�Ȓn����펺�i�A���͑��i�ߕ��j����w�߂��o���L�c�����i�Ƃ悾������/��29�A30��A���͑��i�ߒ����j�ɁA�u�{�C�Ő키�Ȃ�L�c�i�ߒ�������a�ɏ���ă��C�e�p�ɉ��荞�ނׂ����v�Ƒ��������B1945�N�T���A�A���͑��i�ߒ����ɏA�C�i���̂Ƃ��A����͊C�R�叫���i��f���Ă���j�B���̂R������ɔs����}����B �~����A�R���ɐؕ�����҂��o�����Ƃ���A����͎����W�߂āu�N�����͎��ʕK�v�͂Ȃ��B�݂�Ȏ���N�����{���Č�����v�Ɛ��������B���̏���́A�D�G�Ȏ�҂���������E���Ă��܂����Ƃ������ӂ̔O����A�⑰�⋌�R�l�̂��߂ɉ������x�[���Ɍ����Đs�͂��A1966�N11��9���ɑ��E�����B���N80�B���V�ɍۂ��A���a�V�c���玵��~�̍��J�����䉺�����ꂽ�B�č��̐�j�����ƃT�~���G���E�����\���͎��̒��������B�u�̑�Ȃ�헪�Ƃł���D��肾���������̎���S��蓉�ށv�B �s�k�ɂ��s�k���������A���Ȃ��Ƃ�����͏�ɑO���Ő킢�������B�u�J��̐ӔC�͉��ɂ͂Ȃ��B�������A�s��̐ӔC�͎����ɂ���v�i���O�Y�j�B ����̏h�G�A�đ����m�͑��i�ߒ����E�`�F�X�^�[�E�j�~�b�c�����̌��t�B�u�i����ɂ��āj�������w�����͖����ŁA�������w�����͋������Ƃ����̂́A�W���[�i���Y���̕]���ɂ����Ȃ��B�w�����̐��ʂ́A�ނ���A�ނ����\���ɂ���B�s���Ƃ����ǂ��A�ނɉ\�����F�߂�����薼���ł���B�I�U����̏ꍇ�A���̋L�^�͔s�k�̘A�������A���̔s�k�̒��ɋ���ׂ��\�����������킹�Ă���B�����炭�����́A�ނ̉��œ����̂���ɂ������Ȃ��v�B ���E�B�L�y�f�B�A�ɂ͏��O�Y�̕揊�����q�쉀�ɂȂ��Ă���BWHY�I�H �����R�̖����E�����ϑ叫�͏���̓`�L�Ɋ���������M�ƂȂ����B ���Q�l�����w���a�̖����Ƌ����x�i�����ꗘ�E�ۍ㐳�N/���t�V���j�A�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T�A�E�B�L�y�f�B�A�ق��B |
���x ��g/Tekichi Hori 1883.8.16-1959.5.12 �i�����s�A���c�J��A������ 75�j2014
 |
 �@ �@ |
| �e�F�̎R�{�\�Z�i���j�� | �푈���u���v�ƍl����ِF�̌R�l������ |
 |
 |
 |
| �������̎R��B��ɑ�V�̕揊�ł����� | �{�����ɍL�����ʕ�n | ��n�̒����t�߁A�������E��ɖ��� |
 |
 |
 |
| �i�q��̍�ŕ揊���͂܂�Ă��� | �ł���Q�����������R�l�̈�l�I���h�I | �w�x�ƔV��x |
 |
 |
 |
 |
| ��O�̕掏 | �ǂ������u�����@�a�v | �g���� �x��g�h�Ƃ��� | �������B���Ɍ�����т��F���˂̕揊 |
| �C�R�����B1883�N�A�啪�̌��E�n�z�s�ɐ��܂��B1901�N�i18�j�A��ւ̎m���{���w�Z�ł���C�R���w�Z�ɐ��тR�Ԃœ��Z�A����32���ɂ͋g�c�P��A���c�ɑ��Y�A����K��̂ق��A����̐e�F�ƂȂ�R�{�\�Z�������B1904�N�A���Z���g�b�v�ő��Ƃ��A����������u�_�l�̌���̂ЂƂx�̓��]�v�Ǝ]����ꂽ�B 1905�N�i22�j�A���I�푈�Ő�́u�O�}�v�ɏ�D���A���{�C�C��ɂăo���`�b�N�͑��ɏ�������B���ǂ̐�͂ŊC��o����ς݁A1913�N�i30�j����Q�N�ԁA��ꎟ��풆�̃t�����X�ɒ��݁B�����Ő��E���̌�����ڂ̓�����ɂ��A�ߎS�ȑ��͐�A�ŃK�X��ɐ�傷��B�����āA�g�C�R�͐푈���d�|���邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A���a�ێ������̂��߂ɂ���h�Ƃ̐M�O�����B�A����A�w�푈�P���_�x���܂Ƃ��u������ꍇ�ɂ����č��Ƃ��s���푈�F���đP���ƂȂ��ׂ��炸�B�푈�Ȃ�s�ׂ͏�ɁA���A���A���Ȃ�v�ƋL�����B1917�N�i34�j�����B 1921�N�i38�j�A���V���g���R�k��c�̐����ƂȂ��Ď�ȑS���̊C�R��b�E�����F�O�Y��⍲�B���{�͌R�͌����ׂ̈ɍ��Ɨ\�Z�̂R���̂P���₵�Ă���A������x�͌R�k��]��ł����B�C�R���d�h�͐�͕ۗL�ʂ�Ήp�ĂV�����咣���Ă������U���ō��ӁB1927�N�i44�j��́u�����v�͒��ɏA�C�B������1929�N�i45�j�ɊC�R�ȌR���ǒ��ƂȂ�A�����ꎟ���A��b�Ɩڂ��ꂽ�B 1930�N�i47�j�A�����h���C�R�R�k��c�ɂ����āA�x�͉p�ĂƂ̐푈������邽�ߌR�k��ڎw���B�����ď��h�i�R�k�h�j�̎����E�R�����V�i��⍲�B�⏕�͂̔䗦������A�͑��h�i�R�g�h�j���咣����u�ĉp�ɑ��V���v�̐���}�����݁A����X���Y�S���͑ΕĔ�10�F10�F6.975�̌R�k�Ă����ꂽ�B���̒����͊C�R�ɋT��݁A��Ɋ͑��h���䓪����Ɩx�͒������牓������ꂽ�B 1931�N�i48�j�A���R�����B�E�����œ얞�B�S���j���Ē����R�̂��킴�ƋU��A�U�����J�n����u�����Ύ����v���u���B���R�͂T�J���Ŗ��B�S�y�𐧈������B��C�ɔh�����ꂽ�x�́A���{���̍U�������Ԑl�ɔ�Q��^���Ȃ��悤���ӂ���Ǝw���B������͑��h�́u�퓬�ɏ��ɓI�v�Ɣᔻ�����B ��R����i�ߊ����P����i�ߊ����o�āA1933�N��50�ŊC�R�����ɏ��i�B���N�A���{���{�͍��ۘA������̒E�ނ�ʍ�����B�C�R�ł͑�p�����i�݂˂��j�C�R��b��͑��h�ɂ��A���h�Ǖ��l������p�l�����n�܂�A�ŏ��ɏ��h�̒��S���������C�R�����E�R�����V�i�叫���R��ǂ��A�O�R�ߕ����E�J�����^�叫���\�����ɂ��ꂽ�B�R�{�\�Z�͖x����邽�߂ɊC�R�g�b�v�Ŋ͑��h�̒��S�l���E�����{�������i�Ђ�₷�����j�Ɂu�x��v�E�ɂƂǂ߂ė~�����v�ƒ��i����B �����A��1934�N�i51�j�A�x���܂��R��ǂ��\�����ɕғ�����Ă��܂��B���̒m�点���A�R�{�͑�����h���C�R�R�k��c�̗\�����ő؍݂��Ă����p���Ŏ��B�R�{�́u���m��1����Ɩx�̓��]�́A�ǂ��炪�d�v���������Ă���̂��B�C�R�̑�n���l�����v�ƕ������B�R�{�̖x���̎莆�u�N�̉^�������m�B�C�R�̑O�r�͐^�Ɋ��S�̎���Ȃ�B���̂悤�Ȑl�����s���鍡���̊C�R�ɑ��A�~�ς̂��߂ɓw�͂�����������v����v�B �x�͋A����̎R�{���̋������Ɉ����������đޖ����l���Ă������߁u���O�܂ŋ��Ȃ��Ȃ�����C�R�͂ǂ��Ȃ�v�Ɛ������A�R�����ɖ߂����B���̌�A�x����炷�啪�̔_���܂ŎR�{�͉��x���K��A�ďA�E��̔�s�@������Ёi���{��s�@�j���Љ�A�x��1936�N�i53�j������В��ɏA�C����B���̔N�A���{���{�͖x���s�͂��Ē������������h���C�R�R�k���̒E�ނ�ʍ��B����ɂ��A���{�͑����m�푈�̈���ɂȂ����������R���g���̎���ɓ˓������B �A�����J�̍��͂��n�m���Ă���R�{�́A�ΕĊJ�������邽�ߓ��ƈɎO�������ɔ����邪�A���R�Ƃ̋������d��y��Îu�Y�C�R��b�������p�@���R��b�ɉ������A1940�N�ɎO�������̒��������肷��B�����ĉ^����1941�N�B�x�͐^��p�U���̂Q�J���O�ɎR�{����莆�����B���킭�u�吨�͊��ɍň��̏ꍇ�Ɋׂ肽��ƔF�ށB�l�Ƃ��Ă̈ӌ��i�J�픽�j�Ɛ����̌��ӂ��ł߁A���̕����Ɉ�r簐i�̊O�Ȃ����݂̗���͂܂��ƂɕςȂ��̂Ȃ�B��������i�V���j�Ƃ������̂��v�B12���Q���A�Ō�܂Ő푈����̖]�݂��̂ĂȂ������R�{�́A���a�V�c�̒�ł���C�R�Q�d�E�����{��m�e���ɗ��ݍ��݁A�Z�i�V�c�j�ɊJ��������悤���i���Ă�������B������ēV�c�͓�����S�l�ɑ��k�������A�J��H���ɕύX�͖��������B���̓��A�x�͎R�{�ɋɔ�ŌĂяo���ꂽ�B�u�ǂ������v�u�Ƃ��Ƃ����܂�����v�u�������c�v�u�����x���c�����Ƃ��A���������Ì�������l�Ȃ��ƂɂȂ�A�o�������͂��������Ԃ������̎蔤�͂��Ă��邪�c�ǂ����ˁv�B�Q����A�x�͉��l�w�ŎR�{�ƈ�������킵�Č�����B�u����A���C�Łv�u���肪�Ɓc�������͋A���ȁv�B���ꂪ�Q�l�̍Ō�̕ʂ�ƂȂ����B12���W���A���ĊJ��B 1943�N�S��18���A�R�{�̓��o�E���ŏ��������サ�A�����čőO���̃u�[�Q���r�����֕��������������ߎ��@��s���A�Đ퓬�@18�@�̑҂����������Ă����i���N59�j�B�R�{�̓��o�E���Ɍ������O�ɁA�┯���ɓ���Ėx�ɑ����Ă����B�R�{�̍�����Ɂg�R�{�_�Ёh�����̘b���o��ƁA�R�l�̐_�i�����R�{���ь������Ă������Ƃ���A�x��ē������A��㐬����́u�R�{�����f����v�Ƌ��������A�_�Ђ���点�Ȃ������B�ӔN�A�x�͎R�{�̖{�S�𐢂ɓ`���邽�ߎ�L�w�ܕ��^�i���ق��낭�j�x���܂Ƃ߂��B1959�N5��12���A�������c�J�ő��E�B���N75�B ���⍜�͌̋��̑啪���n�z�s����K���Ɨ��R�ɕ�������Ă���Ƃ̂��ƁB |
���ɓ� ����/Seichi Ito 1890.7.26-1945.4.7 �i�������A�喴�c�s�A�ɓ�����C�R�叫�揊 54�j2014
 �@ �@ �@ �@ |
 |
| ��́u��a�v�Ɖ^�������ɂ����͑��i�ߒ����B���v�O�Ɂu�L�ׂȐl�ނ��E�� ���Ƃ͂Ȃ��v�Ǝ����̔��f�ō�풆�~���߂��o���A���m�B��S�ł���~���� |
�u��a�v���U�O�ɍȎq�Ɉ��Ă��D�����⏑���c���B �������ɓ��B�E�[�̒��j�͕��̎���_���œ��U |
 |
 |
 |
| ���̖��Ƃ̊Ԃɓ����Ă��� | ����ƈɓ��Ƃ̍L���揊�i�|�[���t���j�������Ă��� | ��O�ɂ͑傫�ȓ��킪������p�i�H�j�ɂ��� |
 |
 |
 |
 |
| ���ʂɋ����Łu�C�R�叫�ɓ�����V��v | �����Ɉ����� | �Ǝ����f�ŎႢ�����~���� | �g�l�������펀�h |
| ��́u��a�v�Ƌ��ɎU�����C�R�叫�B���{�C�R�ŗB�ꌻ�ꔻ�f�ō�풆�~���߂������������~�����i�ߊ��B�������O�r�S���c���i���E�݂�s�j�o�g�B�C�R���w�Z39���B1912�N�A22�ŊC�R���тɔC���B�ɓ��͓����ǂ��A1923�N�i33�j�A�C�R��w�Z����Ȃő��Ƃ����i21���A�����͎R�{�\�Z�j�B���N�����ɐi���B 1927�N�i37�j�A�č��ɔh�����ꌩ����[�߂�i���̒��ĕ���������㊯�͎R�{�\�Z�j�B���N���ɒ����ɐi���B1931�N�i41�j�A�卲�ɔC���B1933�N�i43�j�A���m�́u�ؑ\�v�͒��ƂȂ�B���̌�A���m�́u�ŏ�v�u�����v�͒��A��́u�Y���v�͒���l���ǂ̋Ζ����o�āA1941�N�i51�j�ɌR�ߕ������ƂȂ�A���N�C�R�����ɐi������B 1944�N�i54�j�A341��i�߁E������t�卲�̓��U���s�i�_���j�̈ӌ��ɑ��A�܂��̓�����U���𖽂��鎞���ł͂Ȃ��Ɣے肵���B���N12����Q�͑��i�ߒ����ɔC���B 1945�N�R��28���A�y��R�ߕ����������a�V�c�ɍq�U���u�e�����v�̎��{��`����ƁA�V�c�́u�C�R�ɂ����͂͂Ȃ��̂��A�C�㕔���͂Ȃ��̂��v�Ǝ���B���]�����y��R�ߕ������́u���㕔�����܂߂��S�C�R���͂ő��U�����s���v�Ɠ����Ă��܂��A�������ܑ�a�����͂Ƃ����A���͑����͑��ɉ���o���̖�������B����͕Г����̔R���i�R�������Ƃ̐�����j�ʼn���̊C�݂ɏ��グ�A����C��ƂȂ��Đ킦�Ƃ����u������U�v�̎w�߂������B ������U�͘A���͑���ȎQ�d�E�_�d���i���� �����̂�j�卲�����ӂ��A�L�c�����i�Ƃ悾 �����ށj�A���͑��w�ߒ��������肵���B �R���l���Ă������X�̍��ł́A��a���g���ĕĊ͑���{�y�̑��܂ŗU���o���A��ƊC����@���Ƃ������̂������B�������V�c�̌��t�ō��͌��ρA�u�����L�䌾�t���q�V����i�L���E�N�j�j���w�Y�c�v�Ƌً}�d��œ��U��������ꂽ�B �S���T���A���˓��C�ɕ����ԁu��a�v�͏�̒��̃R�[�q�[���B���U���߂�`���ɗ����A���͑��Q�d���E�������V����ɑ��A��Q�͑��i�ߒ����̈ɓ��́u�q��@�x�����Ȃ����d�ȍ��Ŗ��ʎ��ɂ��v�ƍR�c�B�����Q�d�����g�����ɋ^��������Ă������ߖق肱�����Ă��܂��ƁA���Q�d�E�O���v�������u�v����ɁA�ꉭ�����U�̂��������ɂȂ��Ē��������A���ꂪ�{���̊�ڂł���܂��v�Ɛ����B�ɓ��́u�킩�����B���̐��ۂ͂ǂ��ł������Ƃ������ƂȂȁv�u��X�͎��ɏꏊ��^����ꂽ�v�Ɗo������߂����A�g�������h�ƈ�������o�����B�u��킪���悢�搋�s�ł��Ȃ��Ȃ������́A���̌�̔��f�͎��ɔC���ė~�����v�B�����Q�d���͂��ȂÂ����B�Q���������o�q�������������A�S���U���[���A��a�͌�q�̌y���P�ǁA�쒀�͂W�ǂƋ���10�ǂŏo������B �ɓ��͍ȂɈ��Ăāu�e���Ȃ邨�O�l�Ɍ㎖������ĉ����̗J���Ȃ��͍��̏���Ȃ��d�����ƒ��S��芴�Ӓv�� ���Ƃ����ň��̂��Ƃ��a�v�A���Ɉ��Ăāu���͂��܉������Ȃ������̂��Ƃ��v���Ă���܂��B�������Ă��Ȃ������̂�������͂����̂��߂ɗ��h�ȓ����������ƌ�����悤�ɂȂ肽���ƍl���Ă���܂��B�����莆�͏����Ȃ���������܂��A�傫���Ȃ����炨�ꂳ��̂悤�ȕw�l�ɂ��Ȃ�Ȃ����B�Ƃ����̂����̍Ō�̋��P�ł��B��g��ɁB�����v�ƈ⏑���c�����B ���́u��a�v�o���ɍۂ��A������n�i�ߊ��E�F�_�Z�����͓r���܂Ō�q�퓬�@�������A���̒��Ɉɓ��̒��j�E�ɓ��b�i������j���т̗��������B ���u���j���p�Ӂv�B��R�疼�̏�g���ɍ����e�����U�ƒm�炳�ꂽ�̂͏o�q�̌�B���h���A���U�̐���������ďՓ˂����g���ɑ��A�g����͖��ʎ��ɂł͂Ȃ��h�ƉP����т̔ߑs�Ȍ��ӂ������B�u�i���̂Ȃ��҂͌����ď����Ȃ��B�����Ėڊo�߂邱�Ƃ��ŏ�̓����B���{�͐i���Ƃ������Ƃ��y�߂����B���I�Ȍ��Ȃ⓿�`�ɂ�������āA�^�̐i����Y��Ă����B�s��Ėڊo�߂�B����ȊO�ɂǂ����ē��{���~���邩�B���ڊo�߂����Ă��~���邩�B�������͂��̐擱�ɂȂ�̂��B���{�̐V���ɐ�삯�ĎU��A�܂��ɖ{�]����Ȃ����v�B �V�ꍆ���͈Í���ǂŕČR�ɓ������ŁA��a�͏o�q���甼���ŕĐ����͂ɕߑ����ꂽ�B�o���̗������߉߂��A�������E�V�m�������q�s���ɕĊ͍ڋ@�����P�B386�@�i�퓬�@180�@�E�����@75�@�E�����@131�@�j���̕Ċ͍ڋ@����Ҕ������B �ČR�ōU�����߂��������̂́A�ɓ���30��̍��A���Ď���ɐe�F�ƂȂ������C�����h�E�X�v���[�A���X�i��̕đ����m�͑��i�ߒ����j�B�čq��@�͍͂������W���I�ɑ_���ċ���10�{�𖽒������A��甚�e�R���𓊉��i�đ��̋L�^�ł͋���30�`35�{�E���e38���j�B14��20���A�D��20�x���X�B���̎��_�Ŋ͑��͂Q�ǂ����v�A�R�ǂ��q�s�s�\�ŁA������̂͑�a�Ƌ쒀�͂S�ǂ݂̂������B�ɓ����u�i�Ⴂ�j�L�ׂȐl�ނ��E�����Ƃ͂Ȃ��v�ƍl���A�S�͑��Ɂu��풆�~�v���߂��o���A��a��g���ɂ͑����ދ��𖽂����B���̌�A�ɓ��͒������ɓ���Ɠ������献�������A��x�Əo�Ă��Ȃ������B ���J�n�����Q���Ԍ�A��a�͂������Ɖ��]���A����ɑ唚�����N�����A14��23���A�͑̂�2�ɕ��f����č��������B�ɓ��i�ߒ����ƗL��K��͒��͂����ĒE�o������a�Ɖ^�������ɂ����B �ɓ��͓����t�ŊC�R�叫�ɓ��i�B�M�ꓙ��������́B �����j�E�b�͕����猩�������Q�T�Ԍ�A�S��28���ɉ���C��Ő_�����U���s���펀�����B ��a�̏�g��3332�l�̂���3056�l���펀�B�����҂͂P���ȉ���276�l�B�����ɑ�a����q���Ă����y���u��v�A�쒀�́u�镗�v�u�l���v�u���v�u�����v�����v���A��q�͂̏�g���v3890�l�̂���981�l���펀�����B���̓V�ꍆ���ł͌v4037�l���펀���Ă���B�����҂��~�������쒀�́u�~���v�̎m���ɂ��A��a��g���͏d���Ő^�����ł������Ƃ����B �ɓ��i�ߒ����̍�풆�~���߂��Ȃ���A��a��g�����~�o�����쒀�͂́A���̂܂܉���Ɋ͑����U�������ċʍӂ��Ă����B���݁A��a�̍Ŋ������p����Ă���̂������҂����Ă����B�ɓ��̉p�f�̂��������B ���C�R���w�Z�����̉������A���ؕ��Y�A�R�������ƈɓ����܂߂��S�叫�͑S�������Ő펀���A����叫�ɓ��i���Ă���B ���V�ꍆ���ւ̌R�ߕ������E���O�Y�����̓����̔��Έӌ����I�m�B�u�ϋɓI�Ȃ̂͂������A����͂��͂���ƌĂׂ�̂��v�B �@  �@�ҍU�ɑς����a �@�ҍU�ɑς����a |
����R ��/Iwao Oyama �V��13�N10��10���i1842�N11��12�j-�吳5�N�i1916�N�j12��10�� �i�Ȗ،��A�ߐ{�����s�A��R�����揊 74�j2012
  |
 |
| ���{�ŏ��̌����ƂȂ��� |
��́w���d�̍��x��� |
 |
 |
| �揊�ɑ������B���E�̐Γ��Ă͓����{��k�Ђœ|�� | ���ʂ̖�̉����揊 |
 |
 |
 |
| ��͕܂��Ă��邯�NJO����悪������ | �w�c�芯����b���R�叫�����]��ʑ�M�ʌ��ꋉ���� ��R�ޔV��x�B�_�����̕� | |
| �F���ˎm�B���{�ŏ��̌����B���������̏]��B�����E�Q�d�������C�B1855�N�A13�ŏ㋞���ē|���^���ɎQ���B1863�N�i21�j�̎F�p�푈�Ō������C�䒷�Ƃ��ď��w�B�]�˂ŖC�p���w�сA��C�푈�ł͖C�����Ƃ��ĉ�Ô˂ȂNj����{�����U�������B�ېV��͂S�N�ԓn�����A1877�N�i35�j�A����푈�ɑ�T���c�i�ߊ��Ƃ��ĎQ���B1885�N��43�ŗ����A�C�B���Y����̐��Y��i�߂�B1894�N�̓����푈�ő��R�i�ߊ��Ƃ��ďo���A���I�푈�ł͖��B�R���i�ߊ��ɂȂ����B���B�̎R���L���Ɨ��R���F�����ɂQ�������B���R�叫�B1916�N�A74�ő��E�B���C�E���B�g���̓��{�l���ڋq�Ƃ̂��ƁB |
����t �\��/Toshichi Chiba 1885-1934.12.17 �i�{�錧�A�I���s�A��ю� 49�j2012
���� �d��/An Jukon 1879.9.2-1910.3.26 �i�{�錧�A�I���s�A��ю� 30�j2012
 |
 |
 |
| �Ŏ�̊֓��R �㓙����t�\�� |
�ɓ��������ÎE�� ���Y���ꂽ���d�� |
��t�\���̕�A�{��̑�ю��B��t�͓��� �ÎE�Ƃ̈���ł������A�h�ӂ�����悤�ɂȂ��� |
 �@ �@ |
 |
 |
| ��ю��̖{���O�Ɍ��L�O��B���Y�O�̈��̐�M�u�����g�R�l�{���v �i���ׂ̈ɐg�������͌R�l�̖{���Ȃ�j���A���M���g�債�Ē����Ă��� |
�g���������h |
�L�O��ɃL���`�ƃ}�b�R�����������Ă��� |
 |
 �@ �@ |
| �{������̕�n�ɖ����t�v�� | �w�����t�\���v�w�V��x |
 �@ �@ |
 |
 |
| ��O�ɂ����̐�M�i��n�j�肪����A���̎�`�������Ă���B�w�������Ă���̂� �������u�Ɩ�w���A���̌��ō����Ɂu��ؓƗ��v�̕������������߂����� |
��n�̐Δ�̔w��ɗR�����B��t�v�Ȃ� �{�q��1994�N�ɋ��{�Ō����B���26�� |
�^���Ԃȗ[�z�����ˁB �������̓n���O������ |
|
1909�N10��26���A����؍����āE�ɓ��������n���r���w�ň��d���i�A���E�W�����O���A30�j�Ɍ�����▽����B���̓��V�A�����Ɏ�艟�������A���{���Ɉ����n���ꂽ�B���͂��Ƃ��Ɛe�����ŁA���I�푈�œ��{�����Ɓg�A�W�A��������|�����h�g���{�̓A�W�A�̊�]�h�Ɗ��т��Ă����B�Ƃ��낪�A���I�푈��̓��{�́A�؍��ɓ��������A�O������D���A�c���ވʂ����R��x�@�܂ʼn��U�������B�[�����]�������́A�Ɨ��^���̂��߃��V�A�֖S�����āu��؋`�R�v��g�D���A���u�Ƌ��ɖ�w���A���̌��ō����ɑ�ؓƗ��̕������������߂�؋�����̍R�������ƂɂȂ����B
�ÎE������A���͎�蒲�ׂɍۂ��A�ɓ��ÎE�Ɏ��������R���q�ׂ��B�u�؍��c���p�ʂ��������Ɓv�u�؍��̌R�������U���������Ɓv�u�`�������ɍۂ������̗ǖ����E�Q���������Ɓv�u�s�����������������Ɓv�u�؍��̊w�Z���ȏ����ċp���������Ɓv�u�؍��l���ɐV���w�ǂ��ւ������Ɓv���X�B���̒��ɂ́u�i�ɓ��炪�j�����V�c�̕��N�i�F���V�c�j���ÎE�������Ƃ͊؍����݂Ȃ��m���Ă���v�Ƃ��������̗��R���܂܂�Ă���B
���N�Q���A��������S������Ɏ��Y����������B���͕ꂩ��u���Ȃ��̎��͂��Ȃ���l�̂��̂ł͂Ȃ��A�؍����̓{���w�����Ă���B�T�i���������͖���ɂȂ��Ă��܂��v�Ǝ莆�����T�i���Ȃ������B
�����̓{��͋t�̗���ɂ���Ɨ������₷�����u���{�̓V�c��p�ʂ��������Ɓv�u���{�̌R�������U���������Ɓv�u�`�E���̒����ɍۂ������̎s�����E�Q�������Ɓv�u�s�����������������Ɓv�u���{�̊w�Z���ȏ����ċp���������Ɓv�u���{�����ɐV���w�ǂ��ւ������Ɓv���X�B �����A�ÎE�Ƃ̈���ł������{�l�Ŏ�̐�t�\���i�֓��R�㓙���j�́A�����咣����g���{�̔�h�͊؍��l���炷����ʂ��Ă��邱�Ɓi�����Ɉٍ����Ђ�i���A���ɔR����Ή��̎u�m�ƒʂ�����̂��������j�A�u���̕��a�Ƃ́A�n�����Ă��l�X���Ɨ����Đ����Ă����邱�Ƃ��v�Ƃ������̐M�O�ɐS������A��b��ʂ��Đl����v�z�ɋ������o�����B�����Ĉ��͗����č��i���E��A�j�Łu���m���a�_�v������������B
���Y���s�͔����̗����A�R��26���B���͍i��Y�̒��O�A��t���u�����g�R�l�{���v�i���ׂ̈ɐg�������͌R�l�̖{���Ȃ�j�Ə�������A�Ō���u���m�ɕ��a���K��A�ؓ��̗F�D����݂��������Ƃ��A���܂�ς���Ă܂�������������̂ł��v�ƌ�����B�Ƃ��ɁA��31�A��t25�B��t�͋A��������̏����ɂ��A���̖������F����X���߂����B �܂��A���͍ٔ��S���̓��{���������u�؍��̂��ߎ��ɒ��N�����̎m�v�Ɗ��Q�������ق��A�����č����Y�������E�I����g�����̐l�ƂȂ�ɋ����A�@�@����ٔ����Ɂg�����Q��h����������A����������������A���Y�O���ɂ͌��̔��������Ă���B���s��A�I�������͈��̎��ɋ���ɂ߂Č̋��L���ɋA�����Ƃ����B���̏��Y��m���������́A�Ǖ玍�u100�N�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A����ł���1000�N�����邾�낤�v�����B
���ӔN�̈ɓ������͓��ؕ����ɌX���Ă������A����ł����{���ł͕����T�d�h�������B���͈ɓ����ÎE�������ƂŁA���ʓI�ɂ͕��������������A���Y�T�J����ɑ�ؒ鍑�͒n�}�ォ����ł��Ă��܂��B���͓�l�̒�Ɂu�c�����Ɨ�����܂ł͈�̂��n���r�������ɉ������ė~�����v�Ɨ����A���̕�n�����N�Ɨ��̐��n�ɂȂ邱�Ƃ����ꂽ���{���{�́A�閧���ɌY�����̋�����n�ɖ��������B���ʁA�����܂ň⍜�͌������Ă��Ȃ��B1970�N�A�\�E���s���Ɉ��̈̋Ƃ�`����u���d���`�m�L�O�فv�����݂��ꂽ�B ��t�\���̕悪����{�錧�I���s�̑�ю��ɂ͈��̌����肪��������A���N���؍����ň��d���E��t�\���v�Ȃ̋��{������s���Ă���B���̐��m�Ȗ����ꏊ���⍜���s���̂��߁A��ю������̌���������{���Ƃ������i�@�v���s���Ă���j�B ��2008�N�Ɉ��������Ŏg�������i������j���������ю��ɕ�[���ꂽ�B���̗��ɂ́u�M���R�� �������� ���d���v�ƍ��܂�Ă���A�R��26���ɗ����č��ŏ��Y����钼�O�܂Ŏg�p�������Ƃ݂���B���Y�O�Ɉ��͐�t�ɏ��u�����g�R�l�{���v�u���ؗF�b�i�䂤���j�P��Љ�v���Ă���A���̈�n�Ɏg��ꂽ�����낤�B��t�͂Q�l�̗F��̏Ƃ��Ĉ�n���̋��ő�ɕۊǂ��A���̐��a100���N�ɂ�����1979�N�Ɏq�����؍��֕ԊҁB���̒n�ō���Ɏw�肳�ꂽ�B���̌����؍��ł͊ԈႢ�Ȃ����B���������͍̂�ʂ̌Â����̎��W�ƁB�����B�S���̃R���N�V�����̒��ɂ������B���W�Ƃ��킭�u���d���̍��̂��������i������A���ɍ��܂ꂽ�v����厖�ɂ��Ă�����Ɋ��悤�Ǝv�����v�B�����Đ�t�\���ƈ��̖@�v�N�c�ޑ�ю��ɁA�����g�p�����Ƃ݂���n�Ђƈꏏ��08�N�S���ɕ�[�����Ƃ̂��ƁB |
���T�� ��T/Maresuke Nogi �Éi2�N11��11���i1849�N12��25���j-�吳���N�i1912�N�j9��13�� �i�����s�A�`�A��R�쉀 62�j2014
1�탍10��26��4�A5��
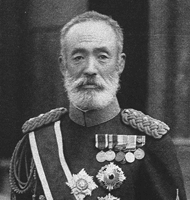  |
 |
| �����_�����邪�����ƕ]������l������ | �}�������̔T�ؕv�� |
 |
 |
| �R�쉀�̈�p�A�w�T�؏��R�揊�x | �w���R�叫�T�؊�T�V��x |
 |
 |
 |
| ���͐Îq�v�l�B���ɏ}������ | �T�؏��R�̐��ʂɗ��e�̕� | ���I�푈�Ŏ��Q�l�̑��q |
| �������̗��R�叫�B�u�C�R�̓����A���R�̔T�v�ƕ��я̂��ꂽ�B���B�̎x�ˁA���{�ˎm�E�T�؊̎O�j�B�c���͖��l�i�Ȃ��Ɓj�B���N���ɍ��ڂ��������Ă���B�w�҂��u���Ă������A1865�N�i16�j�̖��{�ɂ�����B�����ł͒��{�ˎm�̕��ɉ����A����ƍ������Đ퓬�ɎQ���i�C���j�B���q���ԏ��̕�����������B1871�N�A22�ŗ��R�����ɔC���B1877�N�i28�j�A����푈�ɏ��q����14�A�����Ƃ��ĎQ��B���̍ہA�A������E�͌��їY�����т��펀���R���𐼋��R�ɒD���Ă��܂��A���ꂪ���U�̃g���E�}�ƂȂ�B1876�N�A�u���̗��v�Ŕ����R�ɉ����������E��惂��펀�B1878�N�i29�j�A�Îq�ƌ����B30��㔼�Ƀh�C�c�ɗ��w�B1894�N�i45�j�A�����푈�ɕ�����ꗷ�c���i�����j�Ƃ��ď]�R���A�����v�ǂ̍U����ɉ����A�킸���P���Ŋח��������B�����퓬�ł������R�ӂ��A�u���R�̉E�ɏo��҂Ȃ��v�Ǝ]����ꂽ�B1896�N�i47�j��p���Ƃ��Ē��C�A���{���̉��E�ɖڂ����点�j�I�l�����s�����B�����������i�܂��Q�N��Ɏ��E�B 1904�N�i55�j�A���I�푈�ɂ����đ�R�R�i�ߊ��i�叫�j�Ƃ��ė����U�͐���w���B�T�J���������Ċח���������A���e�U���̋��s�ŕ�13���l�̂����A��U���l�����������B�T�؎��g�A���j�̏��T�����B��R�Ő펀�i���N25�j�A���j�̕ۓT��203���n�Ő펀�i���N23�j���Ă���B�����ƎO�j�͑������Ă���A���q�Q�l�̐펀�ŔT�؉Ƃ̌��͓r�₦���B �����ח����N�ɂ͓��I�푈�ő�̗���ƂȂ�����V�̉��𐧂��A���{�͐푈�ɏ�������B�A����ɐ���Ȋ��}��Â��ꂽ���A�T�͗����U���̋]���̑������珵�҂����ׂĒf�����B�����Đ펀�҂̈⑰��K��A�u�T�����Ȃ����̎q����E�����ɂق��Ȃ炸�A���̍߂͊������Ăł��Ӎ߂��ׂ��ł����A���͂܂������ׂ����ł͂Ȃ��̂ŁA�����A�����ꖽ�����ɕ�����Ƃ�������ł��傤����A���̂Ƃ��T���Ӎ߂������̂Ǝv���ĉ������v�ƎӍ߂����B�܂��A����u���ł͓o�d�����߂��Ă��オ�炸�A�u���N�A���͏��N�̌Z��𑽂��E�����҂ł���܂��v�Ƃނ��ы������Ƃ����B�T�͐폝�a�҂̂��߂ɉ��x���������A�����̊�t���s�����B 1907�N�i58�j�A�w�K�@�̉@���ƂȂ�A�c����ؑ��q��̋�����s���B�T�͗T�m�e���i��̏��a�V�c�j���������w���B1912�N�V��30���ɖ����V�c�����䂵�A�u�呒�̓��v�ł���9��13����A�Îq�v�l�Ƌ��Ɏ��@�Ŏ��n�A�}�������B���N62�B�⏑�ɂ́u����푈���ɘA������D��ꂽ���Ƃ��������߁v�Ƃ������B���V�ɂ͏\�����̖��O������I�ɎQ��A�e�n�ɔT���J�����T�ؐ_�Ђ��������ꂽ�B������ʁE�M�ꓙ�E���ꋉ�E���݁B�A�Q�����R����E���Ȃ������Ƃ����B�揊�͐R�쉀�B�����U����A�T���~���������V�A���Ɋ���ȏ��u��^�������Ƃ���A���E�e������^�̏��Ȃ���ꂽ�B |
���쑺 �g�O�Y/Kichisaburo Nomura 1877.12.16-1964.5.8 �i�����s�A������A�썑�� 86�j2014
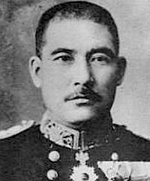  |
 |
|
| �m�Ĕh�̊C�R�叫�B�J�����̂��ߓ��Č��ɓw�� | �쑺�g�O�Y�ƃn�����������i���j | |
 |
 |
| ���ۖ@�ɏڂ������� | �傫�ȕ掏 |
| �C�R�叫�B���ۖ@�̌��Ђł���A���ĊJ�펞�̒��đ�g�Ƃ��Ēm����B�푈����̂��߃M���M���܂œ��Č��ɖz�������B�a�̎R�o�g�B1898�N�i21�j�ɊC�R���w�Z�𑲋Ƃ�����A�I�[�X�g���A�A�h�C�c���ݕ������o�āA1914�N�i37�j����S�N�Ԃ𒓕đ�g�ٕt�����Ƃ��ăA�����J�ʼn߂����i���̂Ƃ��ĊC�R�̃t�����N�����E���[�Y�x���g�Ɛe��������ł���j�B�p���u�a��c��V���g����c�ɐ����Ƃ��ďo�ȁB1926�N�i49�j�A�R�ߕ������ɏA�C�B���{�����{�������o�āA1932�N�i55�j�A��R�͑��i�ߒ����ɒ��C����ꎟ��C���ςɎQ�킵���B�������̓��N4��29���A��C�̓V���߁i�V�c�a�����j�j����ɂĒ��N�l�Ɨ��^���ƁE����g�i����ق�����/�����E�|���M���j�����{�l�v�l�Ȃɓ�������֒e�ʼnE�����������i���Ȃ݂ɓ����S�����g�E�d�����͉E�r�������A��C�h���R�i�ߊ��̔���`�����R�叫�͗��������j�B 1933�N�i56�j�叫�ɏ��i�B59�ŗ\�����ɕғ�����A�w�K�@�@���߂�B1939�N�i62�j�A���B�ő���E��킪�u�����A�L�x�ȊC�O�o�����Ĉ����M�s���t�ɊO���Ƃ��ē��t�B��1940�N11���i63�j�A���[�Y�x���g�ƒm�荇�����������Ƃ���A��߉q���t�ɂ����Ē��đ�g�ƂȂ����B�����m�����f���ĕč��ɏ㗤���钼�O�u�����m�͖{���ɍL���ȁB���Đ푈�Ȃ�đz�����邾�ɑ�ς��ȁv�Ɠf�I�B�č��̋���ȍ��͂�m���Ă����쑺�́A�푈����̂��߂ɐ^��p�U���̒��O�܂Ńn�����������Ɖ�k����Ȃǐs�͂��邪�A���{���{�̓n���C��P�ɓ��ݐ�A�đ�����ڋ��҂Ƌ��e�����Y����B���A���{�r�N�^�[�В���Q�c�@�c�����C�B1964�N�ɑ��E�B���N86�B�����͌��C�@�a�����g���勏�m�B�]��ʌM�ꓙ���B�u�����i�@���j�͈̂������ˁB�����Ƃ͂���ׂ��̂ɂȂ�ʁv�i�쑺�j�B |
�y���E���̕č��̃j���[�X�G���wTIME�x�i1923�N�n���j�̕\�������������{�l�����z
�����ɖ쑺�������Ă���B�^��p�U���̔��ĎҁA�R�{�\�Z�̊炪�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȉ��l��Ɂc�C�G���[�ɂ����ӂ�������c�i���j
 |
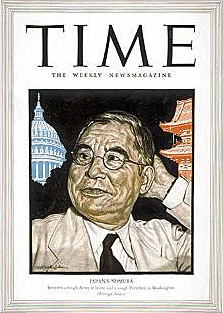 |
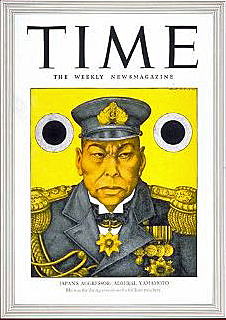 |
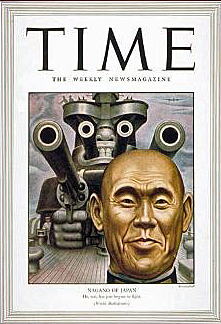 |
| ���������Y | �쑺�g�O�Y | �R�{�\�Z | �i��C�g |
���i�� �C�g/Osami Nagano 1880.6.15-1947.1.5 �i�����s�A���c�J��A��^�� 66�j2012
 |
 |
| �J��ɂ����U�ɂ����� | ��i���i���ق�Ԃj��^���̎Q������ |
 |
 |
 |
| �A���͑��i�ߒ����A�C�R��b�A�R�ߕ������Ƃ��� �C�R�̂R��|�X�g�����ׂČo�������B��̌R�l |
�u�i��ƔV��v�B��ʂ̘a��Ƃ͈قȂ�B ��y�@�̎������_���M�҂Ƃ��Ė��� |
�����ٔ��̌������ɑ��E�B �����ɂ�����s�Ҏ��Ƃ����Ă��� |
| �C�R�̂R���E�ł���A�A���͑��i�ߒ����A�C�R��b�A�R�ߕ����������ׂČo�������B��̌R�l�B�C�R�����B�����m�푈�ł͌R�ߕ������Ƃ��ēr���܂ō��w���ɂ��������B���m�o�g�B1900�N�i20�j�C�R���w�Z�A1910�N�i30�j�A�C�R��w�Z���ƁB33����35�܂Ńn�[�o�[�h��ɗ��w���A�����40�`43�܂Ń��V���g��D.C.�ɂđ�g�ٕt�������߂�B1928�N�i48�j�A�C�R���w�Z�Z���ƂȂ�A�ɓ�����Ƌ��ɑ̔��̋֎~�ȂNj�����v�𐄐i����B���̌�A�R�ߕ��������o�āA1931�N�i51�j�ɃW���l�[�u�R�k��c�S���ψ��ƂȂ����B1934�N�A54�ő叫�ɏ��i�B�����h���R�k��c�S�����C���A1936�N�i56�j�ɍL�c�O�B���t�̊C���ƂȂ�B 1937�N�i57�j�A�A���͑��i�ߒ����ɔC���B�ΕĐ푈�Ɍq����O���R���������������ׂ��A���h�̎R�{�\�Z�𒆉��ɓ���ĊC�R�����Ƃ��A�^�J�h�����p�l���ŒǕ�����Ă������h�E�R�k�h���������B1941�N�i61�j4���ɌR�ߕ������ɏA�C�B�u�R�l�͋ɗ͐����Ɋւ��ׂ��łȂ��v�Ƃ����M���������Ă������A7��30���ɏ��a�V�c�Ɂu�C�R�Ƃ��Ă͑ΕĐ푈��]��ł��Ȃ��v�u�������O�����������������Č��͂܂Ƃ܂炸�Η��W�ɓ���v�u���Č����܂Ƃ܂�Ȃ���ΐΖ��̋�����₽���v�u�����̐Ζ����~�ʂ�2�N�A��ƂȂ��1�N�����������Ȃ��v�u���̏�͑ł��ďo�邵���Ȃ��v�Ə�t�����B���̏�ŏ��Z�ɂ��Ắu���ނɂ͎��v��ł����Z����Ə����Ă��邪�A���{�C�C��̂悤�ȑ叟�͂������A���Ă邩�ǂ�����������܂���v�Ɨ����ɍ������i������g�i���t�h�j�B 9��6���A��O��c�ɂāw�鍑�������s�v�́x���̑�����A�i��͓�������\�Ƃ��Ă���������u��킴��ΖS���Ɛ��{�͔��f���ꂽ���A�키���܂��S���ɂȂ���������ʁB�������A��킸���č��S�т��ꍇ�͍��܂Ŏ������^�̖S���ł���B�������āA�Ō�̈ꕺ�܂Ő키���Ƃɂ���Ă̂݁A�����Ɋ��H�����o����ł��낤�B����Ă悵��Ώ������Ƃ��A�썑�ɓO�������{���_�����c��A�䓙�̎q���͍ĎO�ċN����ł��낤�B�����āA��������푈�ƌ��肹��ꂽ�ꍇ�A�䓙�R�l�͂��������喽�ꉺ�킢�ɕ����݂̂ł���v�B �i��͗����A���̂悤�ɏq�ׂ����A�č��؍݂̌o�����獑�͂̍���Ɋ����Ă���A�{�S�͊J�����ɂ������B11��1���A�Ō�̍������j�����߂�A����c�ŁA�i��͓��������R��b�Ɂu���ĕs��v���āB�g���C�R�͖������߂Đ��{�ɋ��͂��A�������Ŗ�������������j�h������B����ɑ��A�����́u��������ቺ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƌp�����ꂽ�B�����̓��̉�c�ł͓����Γ��O����b�Ɖꉮ����呠��b���푈�������悤�i���Ă���B �J���͏��킱�������������̂́A�č��̊����Ԃ��͐��܂����A1942�N�U���̃~�b�h�E�F�[�C��œ��{�@�������͎l�ǂ̋�����x�Ɏ������B��1943�N�S���A�R�{�\�Z�펀�B12���A�i��͍��ؔ��i���тƐm�Ȋ֕v���т���u�l�ԋ����v���Ă���邪�A�����͂�����ȣ�Ƌp�������B��Lj����ɂ�A���R���͂����Ɉڂ��悤���c�ɑ��Y�C���Ƌ��ɗ��R�ƌ���������q���A�q��@���Y�ɑ���A���~�j�E���̔z���ł��C�R�̗v�����ʂ炸�A1944�N�i64�j2��21���A�i��͌R�ߕ����������E���A���c�C�����R�ߕ����������C�����B�i�삪�v�E����������A�V���ɃT�C�p�����ח����A�W���ɃO�A���������A10���ɂ͐_���̓��U���n�܂�B ������1945�N8��14���A�s��̑O���B�i��͈⏑�������I�����������ӂ������A�e�F�̍�����b�E���ߎi���O�i������ ��������/�C�R�����j����u�ӔC�҂�����Ȃɂǂ�ǂ�ł� �܂��ĒN���É����Ƃ��炨��肷��̂��A�M�l�͐h�����낤�������Ă���v�Ɨ@���ꎩ�����v���Ƃǂ܂����B ���A�i��͐^��p�����������ӔC�����AA����Ɨe�^�҂Ƃ��ċɓ����یR���ٔ��ɏo��B���̍ٔ��ɂ����ĉi��͌̐l�ƂȂ����R�{�\�Z�ɐ^��p�U���̐ӔC�����������A�u�ӔC�̈�͎���ɂ���v�ƌ����������B�i��̘S���͐^�~�ɂ�������炸���K���X������Ă���A�V������\���Ėk����h�����Ƃ����������ꂸ�A�܂������C�����v���ꂽ�Ƃ����B���̌��ʁA1947�N1��2���A�}���x���ɂ����葃���v���Y�����琹�H�����ەa�@�ֈڑ����ꂽ���A�R�����1��5���ɑ��E�����B���N66�B���O���̏d�����͂����Ǔ������u������ ��������� ���߂����� �����m�� ���H���ǂ��v�B�v��31�N�ڂ�1978�N�A�펀�ł͂Ȃ��a���ł͂��������A�@�����Ƃ��Ė����_�Ђɍ��J���ꂽ�B ��͐��c�J�̏�^���ƍ��m�s�̕M�R��n�ɂ���B�č������z�I�Ƃ����O���������������ē��Č����܂Ƃ߂Ȃ�����푈�ɂȂ�A��������Ă��Ȃ���J���j�~�ł��Ȃ��������Ƃ��i��͂����Ɖ����ł����B ���i��C�g���Ƒ��Ɉ��Ă������w�푈�����ƌ�l�̗���x�̗v�� �uA����Ƃ̌��d�����҂Ɠ���Ɏ�舵����̂͐��Ɉ⊶�B�����͂����Ĉ�̖d������I�����Ɋ֗^�������Ƃ͂Ȃ��A�I�n�C�R�R�l�Ƃ��Č�������Ȑ������c��ł����B�i�J��W�J���O�́j1941�N4���A�����{���R�ߕ�������a�C���E�̍ہA��C�ɐ����ꂽ�������ɂ͎��a������A�܂����R�ɑΛ����鎩�M���Ȃ��i�ނɋꗶ�������A���R�ɂ���i�D��I�ȁj�����̒��V�ɒނ荇���l�ԂƂ��āA�ÎQ�ł��鎩���������̐E�ɏA���O�Ȃ��ƐM���A�g���̂č���ɓ����������悾�B���̔��f�ɂ͍�������͂Ȃ��B ���āA�R�ߕ������ɏA�C���������̏́A�����푈���l�N�ڂɓ���A�i�����I��Ƃ����j���R�̗\�z�𗠐�A�܂�����G�������ł��錩���݂��Ȃ������B�O�N�̎O������������A�R�����J��Ɍ����Ďw����`���A�E���w�c�̊����͈�w�������A�e���c�̈Њd���p�ɂɂ���A�ĉp�Ƃ̊W�͂ǂ�ǂ����A������ɘa�������邱�Ƃ͎���ł������B���R�̓h�C�c��M���������O����������߂邱�Ƃ��o�����A�p�Ă͂��̂悤�ȗ��R�̑ԓx�ɔ��������̍D�]�����҂ł��Ȃ��������A�܂����R��������đԓx��ϊ������悤�Ƃ���҂����Ȃ������B �����푈����q�𑱂��Ă���Ȃ��A���C�R���m���𑱂���A��R���钆�����̐�ӂ������A�ĉp�����������������đԓx���������鋰�ꂪ�������B���C�R�̑Λ��͐�ɔ����˂Ȃ�Ȃ�����ɂ����āA���R�J��h�����������̗����N���ς��邱�Ƃ��o�����A���ɍň��̟��֓˓������̂͐��Ɉ⊶�ł���B�����A����͓��{�����̐ӔC�ł͂Ȃ��B�č��̎w���ҊK����R�l�̒��ɂ������A�����̐l����R���Ċ��������B�Ζ��֗A�͕�����g�킸�ɐl���E����i�ł���B�����ɑ���R�퉇�����s���߂��Ă����B�Ȃ�ɂ���A�Εĉp�푈�̑j�~�ɓw�߂����A���R�𒆐S�Ƃ��鎞��̗���ɍR���邱�Ƃ��o�����A���ɍ����̏�����Ɏ��������Ƃ͎��Ɉ⊶�Ɋ������A����i���傤���j�̎��肾�v�B |
���Ό� �Ύ�/Kanji Ishihara 1889.1.18-1949.8.15�i�R�`���A�V�����A�Ό��Ύ��揊 60�j2012
 �@
�@ �@
�@
�_�����̉~�`�揊�����A�Ό��͓��@�@�̏@�k�ł���A��W�ɂ́u�얳���@�@�،o�v�ƍ��܂�Ă����B�t�߂ɂ́u�_�H��́v�̎v�����L�����̐Δ肪����
 �@
�@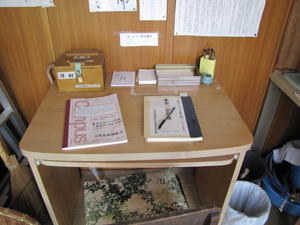 �@
�@
�u�����K�̕��͂��L�����肢���܂��v�Ɣ��ɏ�����Ă��鏬��������A���Ƀm�[�g���B
�̐l��Ǔ����錾�t�ɍ������āA�����E�؍����������t�Ŕl��L�q���U�����A���G�ȋC�����Ɂc
�����炭�A�Ό��Ύ��͂��������̂ق�ƌ����Ǝv��
| ���R�����B�R�`���߉�����B�����푈�u�������̎Q�d�{����핔���B���B���ς̎�d�ҁB �֓��R�Q�d�Ƃ��Ė��B���ς������N�����A�ܑ����a���f���Ė��B���n�݂𐄐i�����B�ŗD�悷�ׂ��͗�����ׂ��u�ă\�Ό���v�̐��E�ɔ����ē��{�̍��͂����߂邱�Ƃƍl���A���Ր�ƂȂ钆���ł̐���g��ɂ͖Ҕ������B �Ό��͖��B���B�l����ɉ^�c�����邱�Ƃ��d�����ăA�W�A�̖��F����Ă悤�ƍl���Ă���A����𗝉����Ȃ��������u�����㓙���v�ƌĂ�Ŕn���Ă��ɂ����B�u���������g���Ȃ����X�����z�v�Ƃ��B�܂��A���������肵���u��w�P�v���������낵�A���{���������ɍ��J����1941�N�\�����ɕғ��B ���E�ŏI��_�������A�����A�����w�������B �揊�͎R�`���O�C�i�����݁j�S�̗V���i�䂴�j�������i�������Ɓj���i�����j����i�����́j�̗т̂Ȃ��B �u���i�Ζ��j���~��������Ƃ����Đ푈����n�������邩�v�i�Ό��Ύ��j �u�F����A�s��͐_�ӂȂ�I�����ėǂ������I���������͍���܂��܂��R�������̖��i������ł��낤�����{�͍��h��s�v�ɂȂ邩��A���������ɐU�������B�s�ꂽ���{�����E�j�̐擪�ɗ���������̂ł���I�v�i�Ό��Ύ��j �u�i����A��������j���{�����W�i���イ���j����Ă��\��Ȃ�����A��X�́A��A�푈�����ɓO���Đ����Ă����ׂ��ł��v�i�s���̐Ό��Ύ��j |
������ ��/Mitsuru Ushijima 1887.7.31-1945.6.23 �i��ʌ��A�������s�A�t�� 57�j2019
10��30��
 |
 |
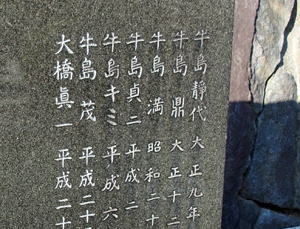 |
| �ɂ߂ĉ��������� |
�����u�H�҂��� �͂�s������ ���� �c���̏t�� �S��Ȃށv������ |
�掏�̉E����R�Ԗڂɋ����叫�̖� |
 |
 |
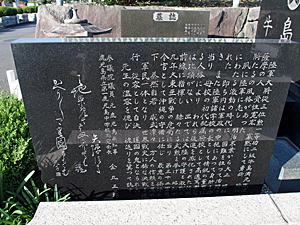 |
| �����Ƃ̕揊��10��30�� | ���ɕ掏�A�E�Ɍ����� | �Δ�w�ʂɁu���E��j�Ɋ�Ȍ���𐋍s�v |
| �������w���������R�R�l�ł���A���{���R�̑叫�ɏ��i�����Ō�̌R�l�B�������o�g�B���͗��R���сB �����͋ɂ߂ĉ����Ȑ��i�ŁA�㊯�Ƃ��Ē��C���������͌ÎQ���ɂ��V�������߂��������B 1936�N�i49�j�A�������A�����ƂȂ������̔N�Ɂu��E��Z�����v���u���A�����͑��A�����͂��ߎ����Ɋւ���������𗧂Ē����B 1937�N�i50�j�A���R����������36���c���Ƃ��ē싞�U����Q���B 1942�N�i55�j�A���R�m���w�Z�̍Z���ɏA�C�B������A���Z�ʼnЂ�����A�R�ΔN��̓������璆�������l���ōőO���֑���Ǝw�����������B�����́u�Z���̎����ӔC���Ƃ�B�܂��Ă⒆�������Y���I�ɍőO���ɑ���Ȃǐ�Δ��v�Ƌ��ۉ𓌞��ɑ�������B 1944�N�i57�j�A����ɌR�i�ߊ��i��32�R�j�Ƃ��ĕ��C�������w���B�����i�ߊ��͘A���R�㗤���O��1945�N3���܂łɁA����{����艄��187�ǂŖ�80,000���A���d�R����30,000���̏Z����a�J�������B 1945�N�R��26���A�ČR���c�NJԗɏ㗤�B�����ĂS���P���A�ČR�͖�1,500�ǂ̊͑D�Ɖ��ז�54���l�̕����������ĉ���{���ɏ㗤���J�n�����B���{�R�ɂƂ��ĉ����̖{���́u�������邽�߁v�ł͂Ȃ��A�u�{�y����̂��߂̎��ԉ҂��v�ɂ������B����䂦�����͎i�ߕ���u������ł̌��������A����{���암�ɓP�ނ��A�Ō�̈ꕺ�܂œ������Ƃ𖽂����B���̓암�P�ނɂ���đ����̏Z�����퓬�Ɋ������܂�A�]���҂��啝�ɖc��B�Ɍ���ԂɊׂ������m��������Z����ǂ��o������A�E�Q�����肷�邱�Ƃ��N�����B ���N�U��23���A�ČR�ɕ�͂��ꂽ�����͌��e�̎����ł͂Ȃ����Ŋ�������B��57�B���̎��������ē��{�R�̑g�D�I�퓬���I���������Ƃ���A���S�����U��23���͉��ꌧ�̈ԗ�̓��ɐ��肳��Ă���B�����ł͌����̂S�l�ɂP�l�����S�����B �����͍Ō�܂Ŗ{�y�����M���ċ^�킸�A�����������r�B�u�H�҂��� �͂�s������ ���� �c���̏t�� �S��Ȃށv�B �������s�̋����a�F�O�����قɁA�����̐����O�ɔ������u�Ō�܂Ŋ������I�v�̑�`�ɐ����ׂ��v�Ƃ̋����i�ߊ��̍Ō�̌R�߂�W���B���̃L���v�V�����ɂ́u�����R�i�ߊ��̎����͐퓬�̏I���ł͂Ȃ������B���̖��߂ōŌ�̈ꕺ�܂ŋʍӂ���I���̂Ȃ��퓬�ɂȂ����v�Ƃ���B ���R�쉀�̕揊�́u�P�C�P-25���W�ԁv�B |
������ �L��/Hironori Mizuno 1875.5.24-1945.10.19 �i���Q���A���R�s�A�@���� 70�j2018
 �@
�@
�C�R�卲���甽�핽�a��`�҂ցI�I
 |
 |
 |
| �@�v�ɂ��킹�ĕ�Q | ����L���̐e���̕�������ꂽ | ���́u���a��O��v |
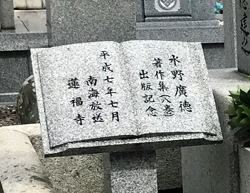 |
 |
 |
 |
| ����L������W�i�����j�o�ŋL�O |
�u���쎁�ݑ�V��v | �w�ʂɘa�� | ���ʂɐ�v�������j |
| ���a��`�҂ƂȂ��Ĕ���i�����C�R�卲�B1875�N�T��24���ɏ��R�Ő��܂��B����Ƃ͋����R�˂̉������m�łƂĂ��n���������B���܂ꂽ���N�ɕ���A�T�ŕ���S�����A�Z��T�l�̓o���o���ɐe�ʂɈ�������A�L���͕����̔����̉ƂŎg�p�l�̂悤�Ɉ�i����̔����̍Ȃ͏H�R�D�ÁE�^�V�Z��̐e�ʋj�B���͈�ԂɋN���đ|���|���A���܂ǂ̉Εt���A���H�̗p�ӂ����Ēʊw�����B���w���̍�����A���͂�U�肩�����҂ւ̔��R�S�ƁA��҂̋��J�ɑ��铯��S������A�剖�����Y��`���E���q�@��ɋ������������B1889�N�i14�j�ɗ\�q�풆�w�Z�ɓ��w�B �u�����̊w�Z�͋K�������Ȃ��A�w���͂͂�Ǝ��R�ɉ߂����Ă��܂����B����ɔ�ׂ�ƁA��������܂锠�l�ߋ�����������Ă��鍡�̊w�������͋C�̓łȂ��Ƃł��B�����E�吳�ɂ�������{�̔���I�Ȕ��W�́A�l��̎���̎��R�ȋ���̌��ʂ������ƐM���Ă��܂��v���ȉ��A����̌��t�͊�{�I�Ɂw����L�����`�x�i��C�����j���� �����ɂ�镺���`���ł́A���ׂȃ~�X�ʼn��ł���邽�߁A����͂���������B��̓��A�R�̎m����ڎw���B���R���C�R���L�]�ƕ����A�C�R���w�Z�����邪�����͓���A20�̂Ƃ��ɂT�x�ڂ̒���ō��i�����B�������Ă��e�ʂ̔����́A���߂Ď����̈⌾��������A�����ɗ{��𗊂ނ��ƁA���Ē��߂�������a����Ƃ���A����͗܂��ށB�a�C�ɂȂ������́u�ǂ���������ʖ��A�����ł������q�ǂ��B�̂��߂Ɂv�ƁA�D���Ȃ��̂��H�ׂ��A���܂Ŏq�ǂ��B�ɉĂ���Ă����B 23�ŊC�R���w�Z�𑲋Ƃ��A���ь��Ƃ��ČR�́w��b�x�i����j�ɔz���B���N�A���n���K�̂��߂̉��m�q�C�ŁA�ăV�A�g���A�T���t�����V�X�R�Ȃǂ�����B28�̊C�R��ю���A�����ۍ`�؍ݒ��ɓ]�@���K���B�V���߁i�V�c�a�����j�ɓD�����ď㗤�A���Ƃ����낤�ɏj�ꉃ��̊C�R�����@�ɖ������݁A�ŏ�Ȃɍ����Ă������������Y�E���͑������̑O�ɗ����u�����A��t�i����͂��j���܂��v�ƌ����Ă��܂����B���������͏��Ďނ����Ă��ꂽ���A�ׂ�̏㑺�F�V��E���͑������́u���O�����̗��鏊����Ȃ��I�v�ƈꊅ�A�J�`���Ƃ�������́u������A�㑺�F�V��̔n����Y�߁I�v�Ɠ{��Ԃ����B�~�߂ɓ������A���Ǝ���g�ݍ����ɂȂ�A�����h���̓�K�ŋC�����B������ɂȂ��Đ^���ɂȂ�A�ǂ�ȏ���������̂��r�N�r�N���Ă�����A�����A���������ɔz�u�]�����ꂽ�B�������͋����œG�͂�����U�����鍂�����^�̊͒��B�u����ȗ��\�҂͐������ɂł��悹�āA�����`�̃T���̃G�T�ɂł����Ă��Ƃ����̂��v�B �������`�c�ɓ������̍`�i���E��A�s�j�B���V�A�̗����͑��i�����m�͑��j���┑���Ă����B 1904�N�i29�j�Q���A���I�푈���u������ƁA���V�A�Ɍ������w�߂�����B����͐��������Ƃ��ė����`�̕������ɎQ�������B�i�ߕ��������L�������悤���߂��������߁A�����̑̌����������܂܂ɒԂ����Ƃ���A�C�R�ɂ͏]�R�L�҂����Ȃ��������Ƃ���V����G���Ɍf�ڂ��ꂽ�B���Ȃ݂ɁA����͕��w�Z���w�����̊��앶�ŎҒ��̍ō��_���Ƃ��Ă���B���̗����Ǒ��L�͑�]���ƂȂ����B 1905�N�i30�j�T���A�����ŋ��Ƃ���ꂽ���V�A�C�R�o���`�b�N�͑��Ǝ��Y�����������{�C�C��ɎQ���B�I���A����L�̐l�C�����������ɁA1906�N�i31�j������I�C��j�Ҏ[�ψ��Ƃ��ē����̊C�R�R�ߕ��ɖ�T�N�ԋΖ����邱�ƂɂȂ����B�����Ŗ�V�т͏o���Ȃ��������A�����ɑ����̏�����ǂ݁A�R�l�Ƃ͈Ⴄ�w�Ƃ̕t�������ɂ���ĎЉ�̎���������B �u��C�Ɛ����ƁA���Ə��ƁA���߂ƕ��]�Ƃ̊O�ɁA�ʂȐ��E�̂��邱�Ƃ�l�͔��������B�l�͓Ǐ��Ɉ˂��Đ��E�̓�����������ꂽ�B�����ɂ͕s�@�̈����ƕs�����Ƃɋ��������̕s�K�Ȃ�퐪�������̐������ꂽ�v�i�w���������܂Łx�j�B 33�ŏ����ɏ��i�A���N�ɑ�������G�ƌ����A���j�̌����i1910-1945�j��������B35�ŕ��ߐ����c�E���\�����i�߂ɏA�C�A�S�ǂ̐������𗦂����B 1907�N�i32�j�A�R���́w���{�鍑�̍��h���j�x�Ƃ��āu�鍑�̍��h�͍U���������Ė{�̂Ƃ��v�ƒ�߁A������R���𒆐S�ɑΊO�c�������i�߂�ׂ��ƍl����B�u�����̕x�́A�L��i�Ђ����傤���܂�Ƃ���j�卑�̉a�B�����h���͌R����`�ɂ���v�i�w�����e�e�x�j �����āI1911�N�i36�j�A�킢�̗l�q���L�^�������{�C�C��L�w�����i���̂�������j�x�����s���x�X�g�Z���[�ƂȂ�B�����ł͌R���������ɍ�������鑶�݂����������B���N�A�R���H��̍����ۊC�R�H���i�������傤�j�ɓ]�C�B���N�A�C�R�ȕ��Ɏ劯�ɔC�������ɖ߂�B�E�����e�͐}���ė��҂ł���A�܂��܂��Ǐ��ɐe���ދ@��������B37�ŊC�R�����ɏ��i�B 1913�N�i38�j�A���Đ푈���z�L�w���̈��x���ŏo�ł���B�����œ��{�̔s���\�z���A�C�R�̋�����i�����B�C�R���̒����Œ��҂Ɣ��o�A�R�ɖ����ŏ������o�ł������ߋސT��������B 1914�N�A�e���̖c�������˂��A��ꎟ���E��킪�u���B���̐푈�͏]���̂��̂Ƃ͈قȂ��Ă����B���ɂ́A�q��@�A��ԁA�ŃK�X�ȂǐV���킪�o�ꂵ�A��ʎE�C���\�ɂ����B 1915�N�A����͊C��Ζ���������]���A���m�́u�o�_�v�����A��́u��O�v�����߂�B���N�A�h�C�c����s�D�c�F�b�y�������g���ĉp�������߂ēs�s�B 1916�N�i41�j�A��푈�̐펞���ɂ��鉢�B���A���Ў����̖ڂŎ��@�������ƍl���A�Q�N�Ԃ̎���w����]���F�߂���B��p�́w�����x�̈�ł����ɗ������B�V���ɓ������o�q���X���Ƀ����h���ɓ����B���̎��_�Ńh�C�c�R�̋�P�͔�s�D��50��A��s�@�Ŗ�25��s���Ă����B����������h���Ńh�C�c�R�R�@�ɂ���P�ɑ������A������ɒn�����i���j����o��ƁA�T���O�ɒʂ�������̉Ɖ����j��Ă����B���̎��̎s���̎��҂͖�150�l�A�����҂�450�l�B����͂T���Ⴂ�Ŗ����E�����B 1917�N�i42�j�A��ꎟ���E���͂S�N�ڂɓ���A����̓t�����X�E�p����K���B�k�t�����X�̐��́A�G����700���̑�R���R�N�Ԃ��ɂ�ݍ����Ă����B���Ƀ��[�}�ɓ����ėl�X�Ȉ�Ղ�p�Ђ����w���A�u�����Ȃ�l�Ԃ̗͂��A���Ԃ̑O�ɂ͉��̌��Ђ������ʁv�Ɗ��S�ɒ^��B�����h���ɖ߂�ƁA�����͐�O�̂R�{�ɒB���Ă���A�H�ׂ��̂̊m�ۂ�����Ȃ��Ă������Ƃ���A�A�����J�o�R�̋A�������ӁB�C�M���X���o�q����D�̓h�C�c�����͂̋����̖ڕW�ɂȂ�\���������A����͍ȂɈ⏑�������A�q�ǂ��̂��߂ɏ�D�O���Ɏʐ^���B�����B�D�͎O����������Ė����ɐ����͂̊������O�֓��ꂽ�B�j���[���[�N�ɒ����ƁA�}���n�b�^���̖��V�O�Ɉ��|����A���̔ɉh�Ԃ�́A�����h���A�p���̔�r�ɂȂ�Ȃ������B�����Ēj�����ڂ̓��{�Ɛ^�t�Łu�A�����J�ł͂܂��ɏ��͒j�̌N��v�Ɩڂ��ۂ�����B����A�푈���s�ɕs���v�ƂȂ錾�_�ɂ͑�e����������l�q�Ɂu���R�̍��A�����J�́A����ɒ[�Ȉ����̍��Ɖ������v�ƐS��܂点��B�嗤�����f���A�T���t�����V�X�R������{�s���̑D�ɏ���ĂP�N�Ԃ�ɋA�����ʂ����B �A����A����̓����h���؍L��V���ɘA�ڂ���B�����ċ̌��Ɋ�Â���@����Ԃ����B�Α����z�����S�̐��m�ƈ���āA���{�͓s�s�ɖؑ��Ɖ������W���Ă���A��P�ɂȂ�Γ����͈��ɂ��ĊD���ɋA���B�ŐV����s�@�̔�s�����͖�500�}�C���i800km�������`�L���̋����j�ł���A�͒��b�ł̔����ɐ������钛�������邱�Ƃ���A�G�ɗD�G�Ȋ͑��ƃp�C���b�g������A�C�ォ����{�̓s�s���P�����Ƃ��\�ɂȂ�B�u����G���������U�߂悤�Ǝv���Η����𑊖͘p�ɏ㗤������K�v�͂Ȃ��A�͑��𓌋��p�ɐi�߂�K�v���Ȃ��Ȃ����v�ƌ��O�������B �u�����A���{�̔@���@��Ȃ�ؑ��Ɖ��Ȃ��ɂ́A�ꔭ�̔��e�ɎO���܌����X�ƂȂ�Ĕ�U����B������ɉ䂪���ɂ͓������ׂ��n�����Ȃ��A�n���S�Ȃ��A�]���āA�l���̑��Q����Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�Еp���A����̏P���Ɉ˂��āA�����S�s�D�o�ɋA�������}��ꂸ�v�u���ΉA�ł̈Í�����ȂĈ��S����܁i�Ȃ��j��A�c�펞�A�����͓G�@�P���̑��ڕW�����v�i1917�w�o�^�̏L���x�j �������P�̎���28�N���O�ɂ��̌x����炵�Ă����B 1918�N�i43�j�A�C�R�卲�ɏ��i�B���N11���A���B�ł悤�₭�x�����������킪�I������B�J�킩��S�N�S�J���A�Q�퍑��30�ȏ�A����1200���A���4000���~�A�����ʂ�̐��E��킾�����B 1919�N�i44�j�A����̐l���̍ŏd�v�N�B�P���R����`��i�삷��_�����w�������_�x�ɏ����B����͂��̎��_�܂ŁA�푈�}�~�͂Ƃ��Ă̌R���͋��͂ł���ׂ��Ƃ���R����`�҂������B�ΕĐ푈�ɔ����Ă��A����́u�킦�Ε�����v�Ƃ����R����̗��R�������B���N�R���A�s�퍑�h�C�c�����邽�߂ɍĂш�N�Ԃ̎���w���肢�o��B�܂��k�t�����X�ɓ���Ós�����X�iReims�j��K�ꂽ�B�폟���Ȃ̂ɁA���ׂẲƉ�����Q���A�z�e�����匀������ꗎ���A���I�����߁A�p�Ђ��̂��̂������B�t�߂̑����͉�ł��A�c���͍r��ʂāA�������̎p���Ȃ��B�͍��i�����j�̒��ł̓h�C�c�������������܂ܔ��������Ă����B���̎���Ƃ���ɏ\���̕�W�ƁA����オ�����y�\�����������B �������Łu�j��ƎE�C�Ƃ�~�����܂܂ɂ�����킢�̐Ղ́A������ߎS�A�������߈��A���Ɍ���̊O�i�ق��j�ł���B�����͉�ł��A�c���͍r�p���A�Z���͗��U���A�ƒ{�͎��ł��A���ځi�܂�����j����r���A�S�i����j�Ƃ��Đ��������Ȃ��v ����͏Ռ�������ɒԂ�B�u�܂�ŕ�̊C�̂悤�ł��B�����ɐ푈�Ƃ͂����A���܂�ɂ��l�Ԃ̖��̈������Ƃł͂���܂��B���ꂪ�����ł���A�N����l�E����Ă��A�Љ�̑厖���Ƃ��āA�������A�ٔ����Ƃ��������ɂȂ�ł��傤�B���ꂪ�푈�̂��߂Ȃ�A���̑�ʎE�l���s���Ă������̂ł��B�l�͍r��ʂĂ����l�̑����ɗ��ꗧ�\���̕�W�߂A�푈�̓������l�Ɛl�Ԃ̐������l���l������܂���ł����v �����Đ���́A��ꎟ���E���ɂ�����ő�̌���n�x���_����K�ꂽ�B���̓y�n�ɂ͕��R�̗v�ǂ����������߁A10�J���ɂ킽�范�����U���������A���R���킹��30���l�ȏオ�펀���Ă����B���I�푈�̓��{�R�̐펀�҂͂W���l�ł���A���̂S�{�߂������̐��Ŏ���ł����B��т̘V�l�A�����A�q�ǂ��������Y���ɂȂ��Ă���B �u�s�X�n�͊��S�ɔj��A�l�̏Z�މƂ͂Ȃ��A�܂�Ń|���y�C�̔��@�Ղ̂悤�ł����B�ƌR��50���̕��𓊓����āA��x�͂��̒n���̂��܂������A���R�ɂ���đS�ł������܂����i�����݂̐��ł͓ƌR�����Җ�35���l�A�������Җ�15���l�j�B�ނ�͌����Ď��ɂ����Ď��̂ł͂Ȃ��B�������Ƃ̂��߂ɌȂ̖����̂Ă��̂ł��B�ނ�͍��Ƃ̗v���ɂ���āA���≞�Ȃ��ɖ������グ��ꂽ�̂ł��v �����Ɏ���A����͐펀�҂ɂ��āA���Ƃ̂��߂ɖ����̂Ă��̂ł͂Ȃ��A�L�������킳���������グ��ꂽ�ƌ��Ȃ��悤�ɂȂ����B �u�R�i�����j��ɂ��ꓙ�̍��Ƃ͑��������̕n�����~���ׂɁA���������̕x���]���ɋ��i���傤�j���邱�Ƃ������Ĉׂ��Ȃ��v�i�吨�̕n���������̂��߂ɏ����̕x�T�w�̕x�������o�����Ƃ������Ă��Ȃ��j �u�ア��������͂��̊|���ւ��̂Ȃ������������D���Ȃ���A������������͂��̗L��]���x������D�����ʍ��ƁA���ꂪ�ō��̓����ƌ�������ł��낤���v�i�u���������܂Łv�j ���̌�A���߂Ĕs�퍑�h�C�c�̒n�ށB���\����̎����Ԃ�A�����ɖv�����ꂽ�h�C�c�ł́A�����Ă��獜���������n���n�Ԃ��Ђ��Ă����B��s�x�������ł����w�O�̍L��ɔn�����ςݏd�Ȃ��ĈُL������Ă���B���[�ł͍��Ƃ̂��߂ɐ�����p���i���a���j����������Ă���A�����R�l�Ƃ��ċ������ߕt����ꂽ�B�h�C�c�̉ݕ����l�́A��O�̂S���̂P�ȉ��ɉ߂����A�D�_�������c���ꂪ�s��B���n�ʼn�������{�l���킭�u���������̑ޔp�����́A�푈�Ńh�C�c�������ނ������`�̑呹�Q�ƌ����邾�낤�v�B ����͐푈�̕s�т��A���s�s�������߂�B�u�펀��1200�����o�������̐푈�A�s�퍑�h�C�c�ƃI�[�X�g���A�A�v���̋N�������V�A�͌����܂ł��Ȃ��A�������C�M���X��t�����X�A�C�^���A�ɂ���A���̍����͐�O�����ʂ����čK���ɂȂ��Ă���ł��傤���B�ǂ̍��������̌��R�Ɛ�����A�J���s���ɏP���Ă��܂��v�B �����̑̌�����A����͎v�z�I��180�x�̑�]�����Ƃ���B�R����`�҂���l���I���a��`�҂ɐ��܂�ς�����B �u�l�͂܂��k�t�����X�̐������āA�푈�̋���ׂ������m��܂����B�폟���ł����A�험�œ������̂́A�푈�Ŏ��������̂������ɂ͑���Ȃ��̂ł��B�푈�͍��Ɣ��W�̍ŗǎ�i�ƍl���Ă����l�̌R����`�v�z�́A���{���畢�i�������j����܂����B�����ăh�C�c�Ŕs�킪�����炷�Љ�̗l�q�����āA�l�ނƐ푈�ɂ��Đ[���ɍl������܂���ł����B�푈�łЂƂ��������悤�Ƃ������ȊϔO�𗣂�āA��������ɁA�l����̗ǐS�ɑi���Đ푈�̔ߎS�ȑ��Q������A�N�����푈�͔�����ׂ��Ǝv���ł��傤�B���Ƃ��푈�ɏ����Ă����ƂƂ��ĂقƂ�Ǘ��v���Ȃ��̂́A��킪�����܂����v �u���ۘA���́A���̈��S��ۂ�����ŏ����ɂ܂ŌR�����k�����邱�Ƃ��K�Ă��܂��B�������A�ŏ����x�̊���ǂ���߂邩�Ƃ����A�ł��d�v�ȓ_���K�肵�Ă��Ȃ��̂ł��B�R���̏k���́A�푈�̔������Ƃǂ߂���ʂ͂��邩������܂��A�푈��h�~����ł��邱�Ƃ͏o���܂���B�R�����������A���z�G���͑z�肳��A�푈�̋��Ђ�����܂��B�m���ɐ푈���ł��A�i�v�̕��a���m�����悤�Ƃ���Ȃ�A�e���̌R����S�p���A���ۘA���̊Ǘ��̉��A���E�x�@�R��ݒu���邱�Ƃ���̎�i�ł��傤�B���ۘA�����^�ɐ��E�̉i�v���a���������悤�Ǝv���A�R���k���ȂǂƂ������ɓI�Ȏ�i�ɗ��炸�A�X�̌R����P�p���A���ۘA���R�̕Ґ��܂Ŏ����čs���Ȃ���Ȃ�܂���B�푈���ł��������̕��@�́A�����ɐ푈�̐^���Ǝ�����A���m�ɒm�点�邱�Ƃł��B�����I�ɁA�o�ϓI�ɁA�R���I�ɁA�������푈�̐��̂��͂�����ƔF������Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�̖�S�Ƃ���Ă�N���푈�����͔�������ł��傤�v �u���Ȃ�����̂͌R���̓P�p�ł��B�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�R�l�̑��݂ł��B���Ƃ͉i�v�ɌR���͂ɂ���Ă̂ݗ��ƐM���Ă���R�l�������̎��������鍑�ɂ́A��ɐ푈�̊댯������܂��B�g�R���͕��a�̕ۏ�Ȃ�h�Ƃ����̂́A�������a�_�҂̗��_�ł��B���O�̒鍑��`�I�����Ƃ�R�l�́A�N���̖�S�����̗��_�ɂ���ăJ���t���[�W�����A�R���̊g���ɓw�߂܂����B�������A���̌��ʂ͂ǂ��������ł��傤�B���E�̖��������a�ł����Ăق����Ȃ�A���a�̐�����W�i���܂��j�����̂��Ƃ���������E�C���Ȃ���Ȃ�܂���B�������a�̖��ɉB��āA�\�����͕��a�������Ȃ���A���ŌR���̕K�v������͔̂ڋ��҂̋U�P�ł��v 1919�N�W��31���̓V���߂̓��A�݃x���������{�l��25�l���u�z�e���E�J�C�U�[�P���[�v�ɏW�܂�����j�i�ق����キ�j�̉�ŁA����͏��߂ČR���P�p�̈ӌ������\�����B �u���̐��S�Ȗk�t�����X�̐�ՁA�����Ă��̃h�C�c�̉A�S�ȍ��������̎�������āA����푈�̎S�ЂɐS���Â����Ȃ��l�͂��Ȃ��ł��傤�B���̖��\�L�̑�킪�c�������̂́A�ʂ����ĉ��ł��傤���B�����n���疜�̕�W�ƁA���S���̖��S�l�ƌǎ��A�����ĐV���ȍ��ۊԂ̉����݂̂ł��B�����ɂ��Ă��̑��ނׂ��푈������邩�́A����l�ɉۂ���ꂽ�Ӗ��Ǝg���ł���ƐM���܂��B�푈��h���A��������@�͈�ł͑���Ȃ��ł��傤���A�����ɏo���邱�Ƃ́A�e�����̗ǐS�ƗE�f�Ƃɂ��R���̓P�p�݂̂ł��B���ۘA���̏�����R���k���Ȃǂ́A�f���Đ푈���ł�����@�ł͂���܂���B���Ƃɍ��A��Q�̃h�C�c�Ƃ��Đ��E����₽�������𗁂тĂ�����{�Ƃ��ẮA�ɗ͐푈��������i���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���̂��߂ɁA�킪���͗ɗ��悵�āA�R���̓P�p�𐢊E�Ɍ������Ē��ׂ��ł���A���ꂪ���{�̐�����ł����S�ȍ�ł���ƐM���܂��v �������u�푈��h���A�푈�������r�́A�e�����̗ǒm�ƗE�f�ƂɈ˂�R���̓P�p����݂̂ł���B���̃h�C�c�Ƃ��Đ��E�ȋ^�̒��S�ɗ��Ă���{�Ƃ��ẮA�ɗ͐푈�������̓r���l���˂Ȃ�ʂƐM����B���ꂪ�ׂɉ䍑�͗ɗ��悵�āA�R���̓P�p�𐢊E�Ɍ������Ē��ׂ��ł���B���ꂪ���{�̐�����ł����S��ł���ƐM����v ���̃X�s�[�`�ɗ��R�̌R�l���������a�_�������Ĕ��������A���̑��͑命���̋��Ǝ^�����B �u�l�ނ̏��������a�ł���˂Ȃ�ʂƐM����l�́A���E�̖��������a�ł���Ƃ�~����l�́A�R�����̌R����`�̊k��E�����ĂĖ|�R�i�ق�j�R���P�p��`�҂ƂȂ����v�i�u���������܂Łv�j 1920�N�i45�j�T���A�A���̈��A�ŊC�R��b�E�����F�O�Y��K�˂��ہA�u����������̂͂��������v�Ɩ���A����͌R���P�p�̎��_���Ɖ����B 1921�N�i46�j�A����̕��a��`�̍L����ɑ���R�l�̕s��������������ɂ�A����͒����g��u�����Ă��ꂽ�C�R�ɐ[�����ӂ����A�l�ލő�̍K���ł��鐢�E���a�̎����͌R���̓P�p�ɂ���Ƃ����M�O���A�R�E�Ɨ������Ȃ��Ȃ������Ƃ�Ɋ�����B�����ĂW���A���w�Z�ȗ�25�N�U�J���̌R�l�����ɕʂ�������A�W���[�i���X�g�ƂȂ����B����ɂƂ��ČR���̓P�p���ڕW�ł��������A�܂��͌����I�ȌR�k����i���n�߂��B �u�����R���P�p������ł���Ƃ���A���߂Ċe������̂��ƂɌR�����k�����A�����Ă��̋����I�g����j�~���邱�Ƃ��K�v�ł���v�i�������_�w���V���g����c�ƌR���k���x�j ����͌R����`�҂�����ƍU�����ꂽ���u�ǂ��炪�����́A���̗͂������Ă����ł��傤�v�ƈ���������Ȃ������B���{�̌R����͍Ώo�̖�T���ɒB���Ă���A�����͑��łɂ������ł����B����䂦�A����̎咣�͍����ɍL��������Ă����B�R����̕��S�ɋꂵ��ł����͉̂��ė̍����������������B ���N11�����琢�E���̌R�k��c�ƂȂ郏�V���g����c���J�Â����B�ړI�͊e���̎�͊͂ۗ̕L�ʐ����B����́u�R���k�����u��v�ɎQ���i�����o�[�ɔ���s�Y����X�R�j�A�y���������ČR���k���̕K�v����i���������B ���N�A���V���g���C�R�R�k��̑�����A�A�����J10�ɑ��ē��{�͂U�ƂȂ����B���{�̑S���ψ��Ƃ��ĉ�c�ɏo�Ȃ��A�ϋɓI�ɌR�k�𐄐i�����̂́A���삪�u�R���P�p�̎��_���v�ƕ��������F�O�Y�������B����̓��V���g�����̒������u�L�j�ȗ��l�Ԃ̂Ȃ�����ł��_���Ȃ鎖�Ɓv�ƔM�]�����B�����ė��R�̏k���Ɏ��|����B �u�C�R�̏k���͐��E�I�ɋ����v������A���R�͗��̏�ɉ����č����I�ɏ������邱�Ƃ��o����B���R�k���͍��⍑���̐��ł���B�����̗v���ł���v�i�������_�w���R�k���_�x�j 1923�N�i48�j�A�R�����č������z�G���Ƃ���u�V���h���j�v�����肷��ƁA����͓��Đ푈��O��I�ɕ��͂��A���{�̔s�k��\�������u�V���h���j�̉�U�v�\�����B�u�����́A���͂����o�ϗ́A���͂̐킢�ł���B�l�X�Ȃ��Ƃ���������ƁA�䂪���͕č��ɑ��Ĉ��|�I�ɗ��A������ɐ₦���Ȃ����낤�v�u���ۂ̐푈�ɂ����Ă͋�R����̂ƂȂ�A�����S�s�͕ČR�ɂ���P�ɂ���āA���ɂ��ĊD���ɋA���ł��낤�B����ɁA������ɂȂ邱�Ƃ�z�肷��ƁA���{�̔s��͖Ƃ�Ȃ��v�u���̂悤�ȍ��h���j�́A���ł����������Ȃ�Ȃ�����́A��邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�ƒf�����B����͂����ł��������P�̎S���I�m�ɗ\�z���Ă���B�ނ́w�������_�x�Ŗ����̂悤�ɔ���E�R�k��i���A���ǂ���댯�l���Ƃ��ă}�[�N���ꂽ�B���N�A�֓���k�Ђ̉e���Ń����G�v�l�����E�B 1925�N�i50�j�A���_�̌R�k�M�ɉ�����A���R����K�͂ȌR�k���s���B21�t�c�̂����S�t�c���팸���A�R���S��l���l���������ꂽ�B���N�w�������_�x�ɔ���_���u�č��C�R�Ɠ��{�v�\�B���̘_����20�N��ɗ\�z�����Ȃ��`�Ő��ɍēo�ꂷ��i��q�j�B�܂��u�R����b�J���_�v�ŃV�r���A���R���g���[���̏d�v��������B 1928�N�i53�j�A�����c���ƍč��B 1930�N�i55�j�A�����h���̊C�R�R�k��c�ŌR�k��������������{���{�ɑ��A�C�R�́u���{���R�̕Ґ��ɂ��ď������Ԃ͓̂����i�Ƃ������j���̊��Ɓi����ς�j�ł���v�ƈًc��������B�������Ƃ͌R�̍��Ȃǂ̍ō��w�����B����{�鍑���@��11���́u�V�c�͗��C�R�����v�ƒ�߂Ă���A�������͓V�c�̑匠�������B�C�R�͌R�̕Ґ����������ɑ�����Ǝ咣���A�R�k���������{���U�������B�u�������v�Ƃ������t�������o���ꂽ���ƂŁA���{�͌��o���ł��Ȃ��Ȃ����B���̎�����A�R���̓Ƒ����n�܂�B����͌Ñ��ɒ�R�����B�u�R����������������ʂČ��@�̐���������Ƃ���́A�����̏������i�₭�j�����Ȃ炵�ނ�̋��ꂠ��v�i�����V����e�U���T���j�B�ނ͌R���������������������̌����̂悤�ɉ��߂��邱�ƂŁA������点�Ă��܂��\�����뜜�����B11���A�����h���C�R�R�k����f�s�����l���Y�K���A�����w�ʼnE���ɑ_�������Ƃ����厖�����N����B�l���͂X�J����Ɏ��S�����B�R�̈ӂɉ���Ȃ����Ƃ������ΐg����Ȃ��A����Ȏ���ɂȂ����B ���̔N�A����͕č��ɂ�铌�����P��\������������L�w�C�Ƌ�x���o�ŁB�쒆�A�����͐��S�@�̕ČR�@�����������ĈΒe�ƃK�X�e�ŏœy�ƂȂ����B ���w�C�Ƌ�x����}���كf�W�^�����C�u�����[ http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1032592 1931�N�i56�j�A�X�����B���ς��u���B�֓��R�i���{���R�j�����쎩���̃e�����s���������k�ւ̐N���푈���n�߂��B��Γ��t�͕s�g����j���Ƃ������֓��R�͓��k�O�Ȃ��́B�����푈�̔��[�ƂȂ�B 1932�N�i57�j�A�R���֓��R�����{�̘��S�i�����炢�j���ƁA���F���������B���{�͌i�C����������Ă���A�����͖��B�����Ɍi�C�̉����҂��A�}�X�R�~���R���̍s�����x���A�S���̐V���Ђ̂���132�Ђ܂ł������B�����������}���鋤���������o�����B�����A����͖��B���̖�肪�A�����J��G�ɉ��ƂɂȂ�ƌx�������B���N�A���Đ푈�̉��z�����w�ŊJ���j�ł��E���S�̍����x�����֏����ƂȂ�B�����Ɂu���{�̖��B�����F�́A���ۘA�������������߁A�č��S�����߁A�������E�i���j�����߂��v�Ƃ���A���ꂪ���{�Ŗ��ɂȂ����B�܂��A�w�C�Ƌ�x�Ɠ��l�ɋ��낵���`�ʂŖ����̓������P���`����Ă���B �u�����ł͐��S�̔�s�@�������̔@���Ë�ɋ������ēG�����̎��ʂ��o���Ȃ��B�����f�ӕS���̎c���s���A���q�v�w���������i���肱���j�A�ߖ̐��B�Ղ͂����D�̒��A�œy�̒��B���[�̒��ł���v�i�u���S�̍����v�j �����Ȃ́u�o�Ōx�@��v�ɂ��ƁA���B���ς���킸���P�N�Ō��{�ɂ�锭�֏����͂T�猏�ɂ��̂ڂ��Ă����B ���N�u�܁E������v���N���A���F�����F�ɐT�d���������{�B���C�R���Z�����ÎE����A���}���t�̎��オ�I���B�e���̋��|���琭�{�ł������R���ɑ��Ă��̂������Ȃ��Ȃ��Ă����B���̋�C�̒��Ő���́A�u���B���͓��Đ푈�ɔ��W���A���{�͔s��A�r��Ȕ�Q����v�Ǝw�E���������B 1933�N�i58�j�A�R�����{�͍��ۘA����E�ށB�W������͎��M�ŏ����Ȃ����A����̐��Ō�낤�ƍu���������n�߂�B�����u�ɓ����a�F�̉�v�n������ʼn������ɖ\���ɏP��ꂽ�����A�x���ɂ�艉�����̂𒆎~�����B 1934�N�i59�j�A12�����{�̓��V���g���C�R�R�k����j���B�{�i�I�ɐ푈�ւ̓���˂��i�ށB 1936�N�i61�j�A�u��E��Z�����v���N���A���R�N���Z�炪��1500���̕����𗦂��Ď��@�Ȃǂ��P���B����b�֓����E�呠��b���������E���瑍�ēn�ӏ����Y�炪�E�Q�����B�R���̐����x�z�͂�����ɋ������ꂽ�B 1937�N�i62�j�A�Q���A�c�i�Ђ낽�j���t�������E���A��p�ɗ��R�̑啨�ł���Ȃ���R���t�@�V�Y���ɔᔻ�I�����������h�E�F�_�ꐬ�i���������j�ɂ��g�t�����҂��ꂽ���A�R���^�J�h�̒�R�i�R����b���������g���ĖW�Q�j�ŗ���Ă��܂��B �V���k���x�O��ḍa���œ������R�������I�Ɍ�킵�A��������S�ʓI�ȓ����푈���n�܂�B�X������͔���v�z�̎�����Ƃ��Č����̐q�����B���R�͏�C�����s�싞�ɐi�����A12���ɓ싞���ח������đ����̎s�����]���ƂȂ�B�ߗ��E�Q�͂S���l�ȏ�B�V���A�G���͌R���̊���������悤�ɕ��A�����������ɐ������ꂽ�B�싞�ח��̗����A�S���Ő폟�j��W��J�Â���A�����ł͎s��40���l���u�o���U�C�I�o���U�C�I�v�Ə������j���j��s����s�����B�����ɐN���ҁE���Q�҂Ƃ����ӎ��͂܂������Ȃ��B���̎s���̒s��͌R���̐���g����㉟�����A����Ӗ��A�����Ɉ����Ȃ�������Ă��܂����B 1939�N�i64�j�A�w����L���S�W�x�������֎~�ƂȂ�B�X���h�C�c�R���|�[�����h�ɐN�U������E��킪�u���B���N���A���L�Ɂu���t�� �m�ȁi�����A�e�F�j��S�N�� ��i�̂��j�ɑ҂v�� ����L���B 1940�N�i65�j�A12�����_�����𑱂��鐭�{�ƌR���́A���̑��d�グ�Ƃ��ē��t�Ɂu���ǁv��ݒu�A�̈�{����_�����B�ŏI�I�ɁA�����͑�{�c���\������������Ȃ��Ȃ�B 1941�N�i66�j�A�Q��26���A����͏��ǂ��o�������M�֎~�҃��X�g�ɍڂ����A����łƂ��Ƃ���̔��\�̏��D��ꂽ�B������12���W���ɓ��{�R���n���C����P�U���A���삪�ł�����Ă������Ă̑����m�푈���n�܂�B�����ɂ́u���{�R�D���v�u�܂����Ă��叟���v�Ƃ����`�����Ȃ��Ȃ�B 1942�N�i67�j�A�U�����������m�̃~�b�h�E�F�[�C��Ŏ�͋��S�ǂ�������s�A�q��@��300�@�A������3000���ȏ���ꋓ�Ɏ����B�W���\�����������c���M���������400�l���ŏ��̋ʍӁB12���K�^���J�i��������P�ތ���i��T�����Ԃœ��{���R���U��l�̂����Q���T��l���펀���邢�͉쎀�j�B 1943�N�i68�j�A�S���A���͑��i�ߒ����E�R�{�\�Z�펀�A�����B�T���V�c��Ȃ̌�O��c�Łw�哌�������w����j�x�����肵�A�u�}���C�i���}���[�V�A�E�V���K�|�[���j�A�X�}�g���i���C���h�l�V�A�j�A�W�����i�����j�A�{���l�I�i�����j�A�Z���x�X�i�����j�͒鍑�̓y�ƌ��肵�A�d�v�����̋����n�Ƃ��ċɗ͂���J�����тɖ��S�c���ɓw�ށv�Ƃ���B���O��́u�A�W�A����ׂ̈̐���v�����A���ۂ͐�̒n���u���{�́v�ɂ��邱�Ƃ��A��O��c�܂ŊJ���Ċm�F���Ă���B�t�B���s���ɂ��Ă͐푈�O����č����Ɨ�����Ă����̂ŁA�g����h�Ƃ�����`�����ׂ̈ɂ������Ɨ������邵���Ȃ������B�r���}�Ɋւ��Ă��A���C���h�̑Ήp�Ɨ��^�����h�����邽�߂ɓƗ��������B��{�c�͌R���ɂ�钥������̒n�Z���ɏd�����y�ڂ����Ƃ�\�z���A���ĊJ��̑O���̒i�K�Łu�i�d���́j�����E���߁v�i���ς�������j�Ƒł��̂ĂĂ���i�w�����̒n�s�����{�v�́x�j�B 1944�N�i69�j�A�S���C�R�������B�t�B���s���ŎQ�d���E�����ɒ������R���Q�����ɕ߂炦���A�uZ���v�揑�v�i�����m�C��ł̍��v�揑�j��u�Í����v���������P�[�X��D��ꂽ�B�푈�S�̂����E����厖�������A�u���Z���͋@�����ނɊS���Ȃ����낤�v�ƁA�C�R��w����Z���v����A�Í��������ύX���Ȃ������B�����̓Q��������ČR�ɓn����A�Í������ׂĉ�ǂ��ꂽ�B�U�������m�푈�̖��^���������}���A�i���C��i�������j�Ŋ��s�A���R�ǂ�����378�@���̍q��@���A��x�Ƌ@���������j�ɂ����C����s���Ȃ��Ȃ����B����ČR�͑D�̒��v�̓[���B�uZ�v�揑�v�̓���ŁA���{���̐헪�A�Q���͑D��͍ڋ@�A�R���ʁA�e�����̎w�������܂ł��ׂĔc�����Ă������炾�B �V���ČR�̖ҍU�ŃT�C�p�������ח����A�����@B-29�ɂ����{�{�y�����̊�n�ƂȂ����B�T�C�p�������������Ƃœ��{�͐�ǂ̋t�]��L���ȏ����ōu�a�����ԉ\�������S�ɂ����A�������t�͑ސw����B 10����p���q���B��{�c�́u���19�ǁA��͂S�ǁA���m�͂V�ǁA�͎�s��15�nj����E���j�v�Ɨ��j�I���ʂ\�������A���ۂ͐�ʃ[���ɓ������u���m�͂Q�Ǒ�j�v�̂݁A�t�ɍq��@��700�@�������Ă����B���̐��I�̑�������Ƃɍ���̍��v�悪�����A�����c��\���������������܂őS�ł��A�����t�B���s���̃��C�e�C��ł͐_�����U���n�܂����B 1945�N�i70�j�A�R��10���������P�A10���l�̎��ҁB���̒n���̂悤�ȋ�P�������Ă��A�����͓��{�̏�����M���ċ^��Ȃ������B�R��26��������������ʍӁB�Q��933�l�̂����Q��129�l���펀����B�S������ɕČR���㗤���n��킪�n�܂�B�����́u���~��������ڂɂ��킳���v�Ƃ����R�̌��t��M���A�W�c�������Ă������B�����̂S�l�ɂP�l���S���Ȃ����B�����A����͐��˓��C�̑哇�ɑa�J�B�T��������ČR�@���S���ɍ~�������Ȃ����r����458��4�疇�T���A���̒��ɂ́u����L�����킭�v�Ƃ��Ĕ���_���u�č��C�R�Ɠ��{�v�̈ꕔ�����̂悤�ɋL�ڂ��ꂽ���̂��������B �u�吳�\�l�N�l���̒������_�ɐ���L�����͎��̂悤�Ɍf�����B�w��ꓙ�͕č��l�̕č�������邱�Ƃ͋����Ȃ�ƂƂ��ɁA����邱�Ƃ͑�Ȃ���ł���B�č��̕��͂���������ɓ���A���̐l�I�v�f�͔މ䓯���̂��̂Ƃ��āA�l������ɂ��炴��A�p���l�ɑ�����h�C�c�l�̌�Z���J�Ԃւ��ł��낤���Ƃ������x--�R���w���҂͐��쎁�̒��ӂ��ꂽ�ԈႢ������Ԃ����̂ł���B�ޓ��͍��ł͌�Z�����o���Ă���B���̋��~�I�R���w���҂�œ|����ɂ͕č������{�{�y���Ղ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��낤���B�c�����~���I�v �V��26���̃|�c�_���錾�i�~�������j���������ʁA�W���U���ɍL���A�X���ɒ���Ɍ�������������A���̊ԂɃ\�A�̎Q�������A15���ɓ��{�͖������~������B���j�̌������t�B���s���Ő�a�������̂͂W��12���A���ƂR�������Ă���ΏI�킾�����B���̐푈�œ��{�l��310���l�i�R��230���l�A����80���l�j�̖����D���A���Q�҂Ƃ��Ă̓A�W�A�E�����m�e��̒n�ł̐H�ƒ����������炵���쎀�҂��܂�2000���l�ȏ�i�e���̐��{���\�̏W�v�j�̖���D�����Ƃ����B �s�헂���X��27���̐���̎莆�u���C�R�̌R���P�p�ƁA�푈�ӔC�҂̏����Ƃ݂̂́A�����Ԃ�䂪�ӂ�����̂Ƃ��đ傢�ɖ����Ƒ����܂��v�B10��12���A�˔��I�ɒ��ǂǁB���̑Ί݂̍����Ŏ�p���邱�ƂɂȂ������A���M�̃G���W�����r���Ŏ~�܂�A�ۈ�ӊC��ɕY�������߂Ɏ�p���x��A10��19���ɑ��E�����B���N70�B���a���ƂƂ��čďo��������{�����͂��Ă̗������������B���q�̎��͍Ō�܂Œm��Ȃ������B�揊�͏��R�s�̘@�����B ��200m���̐��@���̉̔�ɍ��܂�Ă���̂́u���ɂ��т��l�ɂ����˂炸��͂킪�����Ǝv�ӓ���i�܂ށv�B 1976�N�A���E��31�N��A����̈�i�����Ă����e�ނ��c��ȗʂ̌��e������B �u�푈��h���A�푈�������r�́A�e�����̗ǒm�ƗE�f�Ƃɂ��R���̓P�p����݂̂ł���v�B�C�R�卲�ɂ܂łȂ����R�l���A���͕�����i���镽�a��`�҂ɂȂ邱�Ƃ́A�����͍l�����Ȃ����̂������B�L�x�ȌR���m���������A���I�푈�̗����`���������{�C�C��ɏ]�R�A��ꎟ���E���^�������̉��B�ƁA��シ���̍r�p�������B�������̑��Ō��ĉ��A�A�����J�����f���ċ���ȍ��͂�ڌ��A����炷�ׂĂ̑̌�����o���ꂽ���̂�����̕��a��`�ł�����Ɍ����I�B���Ԕ��Ɲ��������悤�ȕ��a��`�ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ƃ́u�R���͐푈�}�~�͂Ƃ��ĕK�v�s���v�ƍl���Ă����R����`�҂ł��������A���B�̐������@���āA����̕���͂��܂�ɋ��́E�c�E�ŁA���͐�ɂȂ�Ə����������]������������Ɛ��B�폟���ɂȂ��Ă��A����ꂽ�����̍����̖������߂��Ȃ��A�������Ă��u���ƂƂ��Ėw��Ǘ�����Ƃ���Ȃ��v�Ǝv���m��B�u���{�̔@���n�R���ɂ��āA���������E�̌Ǘ����́A�@���ɂ��Đ푈�ɏ��ׂ����ƌ������Ƃ����A�@���ɂ��Đ푈������ׂ������l���邱�Ƃ��A��葽���ٗv�ł���v�B���ǂɘ_���̊�e���ւ���ꂽ����A����͔��̎v����Z�̂�o��ɑ����Ă����B �u�푈�ɏ����Ă���������͕̂������]���ɑS��������Ȃ��v�B���A���X�g�ł��������삾���炱���u�^�ɐ��E�̉i�v���a���������悤�Ǝv���A�R���k���ȂǂƂ������ɓI�Ȏ�i�ɗ��炸�A�X�̌R����P�p���A���ۘA���R�̕Ґ��܂Ŏ����čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�u�킪���͗ɗ��悵�āA�R���̓P�p�𐢊E�Ɍ������Ē��ׂ��ł���A���ꂪ���{�̐�����ł����S�ȍ�v�Ɗm�M���Ă����B���E�̗��N�A1946�N11���R���ɐ푈�����̗��z���f�������{�����@�����z�����B ���l����k���Č���ƁA���삪�R����`�҂��畽�a��`�҂ƂȂ����̂͐��E����̉��B�̎S�����������ł���A���̉��B������Ŏ��@�ł����̂́w�����x���x�X�g�Z���[�ɂȂ��Ĉ�ł�����ł���A�w�����x���������͓̂��I�푈�ɏ]�R��������ł���A����̗���͑��ł͂Ȃ��O���ɔh�����ꂽ�͓̂D�����ē��������Y�Ə㑺�F�V��ɗ����ʂƂ����\���������A�l���Ƃ������͉̂������������Ō��ς���̂�������Ȃ����́B �y�Q�l�����z �w����L�����`�x�i��C�����j �w���̎����j�������� �R����E�����W���[�i���X�g�E����L�����c�������b�Z�[�W�x�iNHK�j �w����L���~���[�W�A���x http://www.mizuno-museum.or.jp/shokai.html ���R�s���q�K�L�O�����يw�|���E�����l��̍u�� �w�ӂ邳�Ə��R�̐S�x�i���R�s����ψ���j �u���Đ푈�̔s�k��\���������R�卲�����L���vhttp://www.maesaka-toshiyuki.com/war/3600.html �u�J�C�[�����_���猩���ꎟ���E���vhttp://www.kaizenww1.com/959jpnsmilitary5.html �u�ߑ�j�N�\�`���{�ƃA�����J�ҁv http://kajipon.com/kt/peace-e.html ������L���̂������X�S�C�I�i���w�������j �E�ŏ��́u���a����邽�߂ɂ������킪�K�v�v�Ǝv���Ă������ǁA�O���̑�푈�i��ꎟ���E���j�������̖ڂŌ��ɍs���āA�l������ς����B �E�C�M���X�����w���Ă���Ƃ��Ƀh�C�c�R�̋�P������A�������R����500�l��������������S���Ȃ����l���łāA�u�R���ɂ����̉Ƃ̃C�M���X�ł���Q������̂ɁA�R���₷���̉Ƃ��������{���ǁA���e��������ƒ����ۂ��ƔR���Ă��܂��v�ƋC�Â��A�������P��30�N���炢�O���炸���Ɗ댯��m�点�Ă����B �E�푈�̂��Ƃ����w���āA����̕���͂��܂�ɋ��͂����āA�푈�ɏ������Ƃ��Ă����������ɋ]���҂��o��B����̐푈�ɏ����҂͂��Ȃ��Ƃ킩�����B���������ɂ肠�������Ȃ�ĂȂ��B �E�u�݂�Ȃŕ�������炻���v�ƌ����Ă��邾������푈�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B�{���ɕ��a���������悤�Ǝv���Ȃ�A���ꂼ��̍������R�����Ȃ����A���A�R�������c���ׂ��Ƒi�����B �E�̂̓��{�́A�u�����Ă��镐����ւ炻���v�Ȃ�Ă����A������b�ł��R���Ɍ�����鎞�ゾ�����B����L���͂ǂ�Ȋ댯�Ȗڂɂ����Ă��A�E�C���o���ĕ�����̂Ă悤�ƌ����������B |
�����e�O�E�m/Nikudansanyushi 1932.2.22 �i���s�{�A���R��A��J��n�j2012
 �@
�@
1932�N�Q��22���A��ꎟ��C���ςɂ����ēƗ��H����18����i�v���āj�̈ꓙ���A�]������A�k���i�����ށj�A��]�ɔV��
�̂R���͎u�肵�ēG�w��˔j�E�������A�ˌ��H���J�����B�R���͉p�Y�ƂȂ���e�O�E�m/���e�O�E�m�Ǝ]����ꂽ�B
����͕���/Senkan-Musa��hi 1944.10.24 �i��ʌ��A�������s�A��{�X��_�Ёj2019
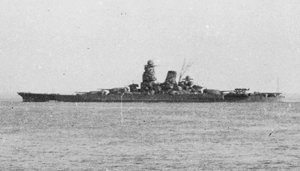 �@
�@ �@
�@
| �u���E���e�Ζ�ʂ̑����R�́v�Ƃ��ăM�l�X�L�^�ɔF�肳�ꂽ��́B�w�����x�͑�a�̓��^�͂ł���A���E�ŋ����ő�̐�͂Ƃ��Č������ꂽ�B1942�N�ɏv�H�B�p�i�}�^�͕��̐�������A40�p�i16�C���`�j�����C������͂������ł��Ȃ��ĊC�R�̎�_�ɒ��ڂ��A��C46�C���`�C���i�O�A���C���O��j�𓋍ڂ��Ă����B �L���̌��ōs��ꂽ�v�H���ɂ́A��ʂ̕X��_�Ђ��U���̐_�傪������A�����͓̊��_�Ђɕ������X��_�Ђ����_�̂����J����u�����_�Ёv�Ɩ������ꂽ�B 1944�N10��17���A�t�B���s�����ӂ̕Ď�͊͑����j��ړI�Ƃ����u���i���傤�j�ꍆ�v��픭�߂ɂ��A�t�B���s���E���C�e����ڎw�����B10��24���A�����͕Ċ͍ڋ@�̍U�������Ɉ����A �퓬�J�n�����X���Ԍ�ɋ���20�{�Ɣ��e17���Ƃ����c��Ȑ��̒������V�u�����C�ɍ��������B�������2600���̂���1319�����펀�B�܂��A������1329�����}�j���h�q�퓙�ɓ�������A�ŏI�I�ɑc���̓y�߂��҂�430�]���ł������B ���v����101�N���2015�N10��24���A��͕��������������s��͕����̔�t����ʂ̕X��_�ЂɌ��������B |
��T�EE�E�������X/Thomas Edward Lawrence 1888.8.16-1935.5.19 �i�C�M���X�A�h�[�Z�b�g 46�j2002��2005
Saint Nicholas Church Graveyard, Moreton, Dorset, England
 |
 |
|
| �����h���A�Z���g�E�|�[�����@�̋L�O�� | ���l�w�̃��[�g������k���Ńh�[�Z�b�g�̒��� | �Г�45���B���̃g���l������������� |
 |
 |
 |
 |
| �Ƃɂ��������I�Ђ���������I | ���ɂ͂������Ƒ����͂ދ����� | �₪�Č����Ă�����n�̖�I | ���z�ɋP���������X�I |
 |
 |
 |
 |
| �w��ɔL�������Ƃ͒m��Ȃ� | ����قǐl�������L�������� | ��̏���U���B��肽������ | �o�C�N���̂Ŏ��� |
�p���l�ł���Ȃ���A���u�Ɋ���ړ����A�g���ڂ̃A���u�l�h�ƌĂ�Ă����ށB�f��w�A���r�A�̃������X�x�ł��̌����������l���`���ꂽ�B
�������������R/Erwin Rommel 1891.11.15-1944.10.14 �i�h�C�c�A�E�����x�O��Herrlingen 52�j2005
Herrlingen Cemetery, Herrlingen (Outside of Ulm), Germany
 |
 |
 |
| ���������ʂ�B�ނ͑��̉p�Y�� | ��n�����̈ē��� | �R�Ԃ̏����ȕ�n�̈�ԉ����ނ̕� |
 |
 |
 |
 |
| �k�A�t���J����̂悤�Ɏ������A�p�R����́g�����̌ρh�ƌĂꂽ�B�g���[�h�}�[�N�̃S�[�O���͉p�R�̂��́I | |||
 |
 |
 |
| �h�C�c�̏��R�ł���Ȃ��瓰�X�� �q�g���[��ᔻ�����E�C���銿 |
�Ԃł��ӂꂩ����������B�����č���O�̐Ԃ��ԗւ̓b�I |
�Ȃ�ƁI���̉Ԃ������Ă����̂� �C�M���X��ԕ����I�G�̌��ԁ� |
���v�v�U�̉p�R��ԕ��p�̖X�́ARoyal Tank Regiment�i������ԘA���j�̃}�[�N�BWW�T��Mark��ԂƊ����`����Ă���B���E�ŏ��̐�ԑ��͉p�R�B
�uFEAR NAUGHT�v��"�������̂Ȃ�"�Ƃ����Ӗ�
| �u�G�̎w�������������́A����߂ėE���ȁA����߂čI�݂ȓG�����B�푈�Ƃ����s�ׂ͕ʂƂ��āA�̑�Ȑl�����B�c���������I�v�u���c�̓i�|���I���ȗ��̐�p�Ƃ��v�i�`���[�`���j �����s���̏����h�C�c�R��ԑ��𗦂��āA���{�̕��͂̃C�M���X�R���A�t���J����Ō��j���������G���G���E�B���E���������ɁA�p�`���[�`�����v�킸���炵�����t���B �g�����̌ρh�����������R�B�l�X�Ȋ��œG�R��|�M�����ނ����i�킸��300�l�̕��͂�8000�l�̓G����ߗ��ɂ����j�A���ł����r�A�����̐킢�͓��ɗL�����B�ނ͎��R���R�Ɏv�킹��ׂɁA�őO���{���̐�Ԃ�z�u���A����͎����Ԃɖؘg���������j�Z��Ԃ��W�J���A�������j�Z��Ԃɂق����⍽���������点�đ�K�͂ȍ����𗧂���������Ԃ�B�p�R��2�����������Ă���Ɛ�̂����w�n���킸���ĕ����A���ɂƓP�ނ����B �p�R����������ɂ͍����p�̃S�[�O���������Ă����B�ނ͂������Ɏ�茾�����B�u�ǂ��f�U�C�����B���炤��B�v����ȗ��A�ނ͓G�R�̃S�[�O�����g���Ă����B���̏��R�́g�G�̕���g�ɂ���Ƃ͉������h�Ɣ������A���������͑f�m��ʊ�B����͔ނ̃g���[�h�}�[�N�ɂȂ����B ���͉p�R���p�j�b�N���N���������R�͂����ЂƂ������B�h�C�c�R�����O�ɍs�Ȃ����R���p���[�h�������p���̃X�p�C���A�u�������������ɑ��ԑ�����v�ƕ��Ă������炾�B�������A������Ȃ�ł��X�p�C���j�Z���m�̐�Ԃ��x�����͂��Ȃ��Ƃ��v�����낤�B���̂��Ƃ͂Ȃ��p���[�h���̂����Ƀ���������㩂������̂��B�p���[�h�̐�Ԃ͉��𒆐S�ɉ~��`���A�Ђ�����O���O���܂���Ă����̂��I �������l�̓����������ˏ��������ׂɍ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��B���������͓����M���o�g�������K���̎m�������Ȃ�Ȃ������t�c���̒n�ʂ��A�����o�g�ŏ��߂Ď�ɓ��ꂽ����ł��Ȃ��B�ނ��Ȃ̐M�O���Ō�܂Ńi�`�X�ɓ��}���Ȃ��������炾�B �ނ̑��q�͂�����z���Ă���c�ނ�15�̍��A�i�`�̐l�퍷�ʗ��_�ӂ��ɕ��Ɍ�������A�u���̑O�ł��������n���������Ƃ�2�x�ƒ���ȁI�v�ƌ��������Ƃ����B ���������͑��̎m�������悤�ɁA�����̉Ƒ����q�g���[��i�`�X�����Ɉ������킹���肵�Ȃ������B�Ќ��E�ւ͍Ȃɂ����܂�āA�a�X�ƈ�x����������Ɋ���o�����B�w�p�Y���������x�͉��ɓ���Ȃ蒅���������������Ɏ��͂܂�g�����o���Ȃ��Ȃ����B���̎��̔ނ̔������P�b�T�N���B�ނ͂������`���Łu����ʂ��ĉ��������I�v�����{��A���͂��Â܂�Ԃ����Ƃ����B ��͂ŏ���̂ɘA��A�s���������p�R���ɂ́g�_����������������Ă���h�Ɖ\�����ꂽ�B�܂��A�������������_���l������ߗ��ɂ����ۂɁA�x�������̑��i�ߕ����g�ߗ��Ƃ��Ĉ��킸�A���ˎE����h�Ǝw�����o�������A���������͂��̖��ߏ����Ă��̂Ă��Ƃ����j���[�X������A���悢���p�R���m�ɂ͔ނɁg�h�Ӂh��\�킷�҂����o���A���ۂɉp�R�i�ߕ����w���������͐l�Ԃł���x�Ƃ������e�́A�O�㖢���̕z�����o�����̂������B ���������͎��E�����A�Ƃ�����莩�E�g������ꂽ�h�B���悢��A���R�̑��������J�n�������ɁA�����ڂ��Ȃ��Ɣ��f�����ނ͓P�ނ̋����x�������ɋ��߂��B �q�g���[�u�����������B����ȊO�ɓ��͂Ȃ��v ���������u�����͔ƍߎ҂��B�c������ł���܂Ő키���肩�v �ނ́A�ƒf�őދp�𖽗߂����B�x�������ɖ߂����ނ̓m���}���f�B�[�̔s�ނ����āA�q�g���[�ɐ푈�̏I����i�����悤�Ƃ����B�q�g���[�͓{���������--�u�����A�o�čs�����܂��I�v�B 3������A�q�g���[�̎g�҂����������@�Ɍ����c�Ŗ�����Q���āB�u�M���ɑ����ÎE�����̋^����������܂����B���̓ł����ނȂ�Ƒ��̖��͕ۏ��܂��傤�v���������͉Ƒ��̈�l��l�ɕʂ����������A���̂܂���̗��̗тɓ���A�X�̊Ԃœł����������B �g�Ȃ������Ă��R�l�͌R�l���h�A����Ȃ��Ƃ͕S�����m���Ă���B�����A�l�̓h�C�c�𐁂��r�ꂽ���̋��C�̒��ŁA�ǐS�̂���������o�������Ƃ��������̂��B ������������^X2 �w�R�̏�w���́A�\�ʂ����X�x�X�x�Œ��͕������嗝�Ζ�Y���肾�x �w���q�g���[�͐����Ă���q�g���[�ȏ�Ɋ댯���x �ŋ߂̃l�I�i�`�̊����ȓ������l����ƁA2�Ԗڂ̌��t�͏d���B ���������̎��́A�����ɂ́u�폝�Ŏ��S�v�ƕ���A�`����̍������s��ꂽ�B �@  �@��ȎQ�l�����u100�l��20���I�v�i�����V���Ёj �@��ȎQ�l�����u100�l��20���I�v�i�����V���Ёj |
�����q�g�z�[�t�F��/Manfred von Richthofen 1892.5.2-1918.4.21�i�h�C�c�A���B�[�X�o�[�f�� 25�j2015
Sudfriedhof, Wiesbaden, Wiesbadener Stadtkreis, Hessen, Germany
 |
  |
| �ꎟ���̃G�[�XP | �x��������Invalidenfriedhof�Ɏc��ŏ��̕�i2015�j |
 |
 |
 |
| �[���Ŋ��ɊǗ��l���͕܂��Ă������� | ���̂��ꂿ��u�n�}�������v�Ƌ����Ă��ꂽ | �Ȃ�قǂ����Ɂg���b�h�o�����h�������Ă���̂� |
 |
 |
 |
| �x����������������ꂽ�Ƃ̂��� | �ꑰ���W�܂��Ă���B�Ԃ��Y�킾 | ���O�Ɩv�N�Ŕނ̕�Ɗm�F |
��ꎟ���E���̓ƌR�G�[�X�p�C���b�g�B�ʏ́g���b�h�o����"�B�Q�퍑�g�b�v�̌��ċ@�L�^�i80�@���āj�B
��@��Ԃ��h�����u�Ԃ������v�ٖ̈��B���B�R�Ɍ��Ă���펀�����B
���W���[�W�E�p�b�g��/George Smith Patton Jr 1885.11.11-1945.12.21 �i���N�Z���u���N�A���N�Z���u���N 60�j2015
Luxembourg American Cemetery and Memorial, Hamm, Luxembourg, Luxembourg
 |
 |
 |
| ���B���N�Z���u���N�ɕĕ��̏W�c��n |
���n������̕ĕ��̏\���ˁB�t�@�V�X�g ���瑼����������ׂɋ]���ƂȂ��� |
��ԉ��ɖ���̂��p�b�g�� |
 |
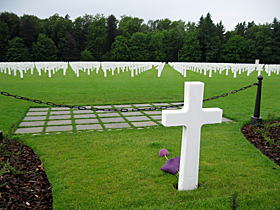 |
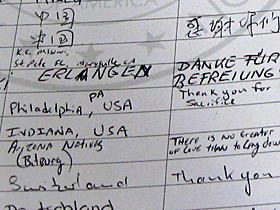 |
| ���R������̑傫���͐V���Ɠ��� | �p�b�g���̌������̌��i | ��q���̋L���B�uThank you�v�⒆���l�́u���Ӂv |
| �A�����J�̗��R�R�l�B���b�g�[�́u��_�s�G�ł���I�v�B�h�C�c�R�畉���́u�d����v�����{�A�Q�T�ԂŖ�1000�L����i���B�G�̕⋋�H���Ւf���邽�߁A�@���͂����Č���ɉ�荞�ސ�@����g�B�h�C�c�~���̔��N��A����Ԃ��ČR�g���b�N�ƏՓ˂�12����ɔx�ǐ��ǂŎ����B�Ŋ��̌��t�́u�i�����Ԏ��̂́j�R�l�̎��ɗl�ł͂Ȃ��ȁv�B |
���i�C�����h�Z��/Niland brothers �i�t�����X�A�m���}���f�B�[�ČR�p���n�j�@2023
�v���X�g���E�g�[�}�X�E�i�C�����h��сi1915�N3��6��-1944�N6��7���j��29��
���o�[�g�E�W���Z�t�E "�{�u"�E�i�C�����h�R���i1919�N2��2��-1944�N6��6���j��25��
Normandy American Cemetery and Memorial�CColleville-sur-Mer, Departement du Calvados, Basse-Normandie, France
 �@
�@
�i����j�O�j���o�[�g�i�E��j���j�v���X�g���i�����j���j�G�h���[�h�i�E���j�l�j�t���f���b�N//�E�ʐ^�͉f��w�v���C�x�[�g�E���C�A���x�̃W�F�[���Y�E���C�A���Q�����i�t���f���b�N�����f���j
 |
 |
 |
| �I�}�n�r�[�`�̉�� | �ĕ��Q��l�����������g���̃I�}�n�h | �m���}���f�B�[�㗤���̑S�e����� |
 |
 |
 |
| �h�C�c�R���r�[�`�ɐݒu�����u���b�N | �I�}�n�r�[�`�Ɏc��ƌR�C�� | ���̋��C���A���R��_���� |
 |
 |
 |
| ���ۂɎg�p���ꂽ�ČR��� | �㗤���ɎQ������12�����̊� | �J�[���̐푈�����ّO�̕��a�F�O�� |
 |
 |
 |
| 9,388�l�̕ĕ��������� �m���}���f�B�[�ČR�p���n |
����F��Ƀi�C�����h�Z�킪���� �i���̐�͐e����������Ȃ��j |
���̐������́w�v���C�x�[�g�E���C�A���x�� �`���ƍŌ�ɓo�ꂵ�A�ϋq�̐S�Ɏc���� |
| �i�C�����h�l�Z��͑���E���ɏ]�R�����j���[���[�N�B�o�g�̃A�C�������h�n�A�����J�l�B���킪�X�s���o�[�O�ē̉f��w�v���C�x�[�g�E���C�A���x�i1998�j�̃W�F�[���Y�E���C�A��2�����̃��f���ƂȂ����B ���j�̃G�h���[�h�E�i�C�����h2���R���i����32�j�́A1944�N5��16���A�r���}�œ��{�R�Ɛ키���߂Ƀp���V���[�g�ŃW�����O���ɍ~�����A�s���s���ƂȂ������ߌR�͎��S�����Ɛ��肵���B ���̗����A1944�N6��6���iD-DAY�j�ߑO6��30���B�A���R�̓i�`�X�h�C�c�ɐ�̂��ꂽ�t�����X��������邽�߁A����E���ōő�̐킢�ƂȂ�u�m���}���f�B�[�㗤���v�����s����B�A�����J�̃A�C�[���n���[�叫�w���̉��ɁA�������ꂽ���͂͑��g�U�������ł�15���l�ȏ�̏����A�͒�5300�ǁA�A���D4000�ǂȂǖ�P���ǂ̊͑D�A�q��@�͐퓬�@5,000�@�E�����@5,000�@�E�A���@�������Čv1��4��@�Ƃ������܂����K�͂ŁA�����g���p�̐l�H�`�܂ŏ����������ƂŁu�j��ő�̍��v�ƌĂꂽ�B �A���R�̓A�����J�R�A�C�M���X�R�A�J�i�_�R����̂ɁA���R�t�����X�A�I�����_�A�m���E�F�[�A�M���V���A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�A�x���M�[�A�|�[�����h�A�`�F�R�X���o�L�A��12�J���̌R���ŕҐ����ꂽ�B�p���̉���܂ł̍��S�̂̐������̂́u�I�[�o�[���[�h�i��N��j���v�Ɩ��t�����A�����ɖ�15���l���R�́E�����@�Ɍ�q����ď㗤�����s�����B���̌�A1�T�ԂŖ�36���l���㗤���A�u�I�[�o�[���[�h���v�S�̂�200���l���t�����X�̒n�݁A������h�C�c�R�̃t�����X��������38���l���}���������B ���́u�m���}���f�B�[�㗤���v�ɃG�h���[�h��3�l�̒킽���S�����]�R����B �iA�j�㗤�̏����A�O�j�̃��o�[�g�E�g�{�u�h�E�i�C�����h2���R�������������82����t�c15,000�l�́A�ꕔ�̕������T���g�����[�����G�O���[�Y�̊X���ɍ~�����Ă��܂��A�����Ƀp���V���[�g������������Ԃ牺������������o���A�h�C�c���Ɏ��X�ƎˎE���ꂽ�B�{�u�͓P�ނ���F�R����邽�߂Ɏu�肵�ăh�C�c�R�̑O�i��j�~������A�@�֏e�����25�Ő펀����B���̌�A��͏W�����Ĕ������J�n�A���n�͘A���R�ɂ���ĉ�����ꂽ�t�����X�ŏ��̊X�ƂȂ����B �iB�j��헂���A��22�����A���ɏ������鎟�j�̃v���X�g���E�i�C�����h���т́A�m���}���f�B�[�̓ƌR�N���X�x�b�N�C��i���^�E�r�[�`�j�̍U�h��ɂ�����29�Ő펀����B���̂S����A�A���R�͂R�O�O���ȏ�̐펀�҂��o���Ȃ���N���X�x�b�N�C����ח��������B �iC�j�l�j�̃t���f���b�N�E"�t���b�c"�E�i�C�����h�R���i����24�j�����������101����t�c6,600�l�̓��^�E�r�[�`�̂���R�^���^�������ɍ~���B���̍ہA���ɍ~�����ēM����������A�A���@�����яo���̂��x�����ĊC�ɍ~�����ēM���������������B����ɓG�R�Ƃ̌�������A��101����~���t�c�͏����ɐ�͂�40%�������B�t���b�c�͍ŏ��̐����Ԃ�킢���������ƁA9���ڂɃ{�u�i�O�j�j�̕����܂ʼn�ɍs�������A�����Ő펀��m�炳���B�Z��S�ł̔ߌ���������邽�߁A�ČR�̓t���b�c��{���ɑ���Ԃ��A�ނ͏I��܂�NY�ŌR�x�@(MP)�߂��B ���A���S�����Ǝv���Ă������Z�G�h���[�h���r���}�̓��{�̕ߗ����e���Ő������Ă��邱�Ƃ������B�t���b�c��2�l�̖����������A�T���t�����V�X�R��1983�N��63�ő��E�B���Z�G�h���[�h�͗��N��71�ŗ��������B �m���}���f�B�[�㗤���̓t�����X�k���̖�100km�ɋy�ԊC�݂ɂT�J���̏㗤�n�_���I�}�n�r�[�`�A���^�r�[�`�A�S�[���h�r�[�`�A�W���m�[�r�[�`�A�\�[�h�r�[�`���߁A�T�̑啔�������ꂼ��p���C����n���đ����̃r�[�`�ɓˌ������B�A���R�͎��O�̏���ɐ������A�z�����ɂ̂���ꂽ�h�C�c�R�͏㗤�n�_�̗\�������A�������ꂽ�`���J���[�ɏW�����Ă����B �i�P�j�I�}�n�E�r�[�`�ł̓R���N���[�g�ŗv�lj������h�C�c�R�̐w�n�Əd�Ί킪�㗤������҂��\���Ă����B��1�g�ŏ㗤������29�����t�c�E��116�����A����A������230�l��212�l���������A�u������90���v�ɒB�����œI�ȑŌ����A�̂��Ɂu�u���b�f�B�i���܂݂�́j�E�I�}�n�v�ƌĂꂽ�B�r�[�`��ڎw���㗤�p�M���Ƀh�C�c�R�̖C�e�����X�ɖ������A�Ȃ�Ƃ��C�݂ɓ������āg�͂����h�����낳���ƁA�҂��\���Ă����@�֏e�������Ďˌ������т����A�����҂�������1�l�Ƃ����M�����������BE�������܂���200�l���A���������܂�104�l���������AF������200�l�̂������������A���g�͎w�����Ƃ�S�Ă̎m������щ��m���͐펀�܂��͕������A�㗤10���ȓ��Ɋ����\�͂��������B�㑱�ŏ㗤�����A�����W���[�W�E�e�C���[�卲�͎��̌��t�������A���m�ɊC�݂���̑O�i�𑣂����B�u���̊C�݂ɂ́A2��ނ̐l�Ԃ�����̂��B���łɎ����̂ƁA���ꂩ�玀�ʂ��̂��B�i�O�i���āj�킨���A�����邽�߂Ɂv�B �C�݂�C���ɂ̓h�C�c�R���ݒu���������̏�Q��������A���m�̏㗤������ɂ��Ă����B�����Ő����j���192�l���A�C����Q����j�Đi�H���J�����Ƃ������A�h�C�c�R�̌������U�����āA�j��ǂ̂���1/3�̕��m�����ɁA�ߔ����͕��������B ���m�����͊������ɐg���B���Ƃ�����Ȃ����l��800�������蔲�����B�ŏI�I�ɃA�����J�R�̓I�}�n�E�r�[�`��2,000�l�̎����҂��o���A���J�n����V���Ԍ�̌ߌ�1���ɖh�q����˔j�����B �i�Q�j���^�E�r�[�`�͉��₩�Ȕg�̂������ő����̐�Ԃ��㗤�ł��A�܂��������ɍ~�����ēƌR�̔w����Ƃ��Ă���A�����̋]���̓I�}�n�ɔ�ׂ��Ȃ菭�Ȃ������B�������A���������삷�邽�ߊC�݂ɐڋ߂��Ċ͖C�ˌ����s���Ă����A�����J�R�쒀�́u�R���[�v���������ꂽ�B �i�R�j�W���m�[�E�r�[�`�ł̓J�i�_��3�t�c����͂Ƃ��镔�����㗤�����݁A�㗤�p�M���������ł��@���ƃh�C�c�R�̖C���Ŏ��X�ƕ��ӂ���A���g��306�ǂ̂���90�ǂ����j�E�����ƂȂ�A�ČR�ȊO�ł͍ő�̑��Q�������B �i�S�j�S�[���h�E�r�[�`�ɂ̓C�M���X�R���㗤�B���ӑ�����ƌR���v�lj����Ă���A�n���v�V���[��1�A���̓��E�A�������̍U�h���200�l�����������B �i�T�j���̍��ň�ԓ����̃\�[�h�E�r�[�`�͉p�R��t�����X���������S���B��s�s�J�[���ɋ߂����ߓƌR����R���A�㗤�n�_�ŃC�M���X�R���Z5�l�A���m60�l���펀���A140�l�ȏオ�����������A�A���R���Η͂��W����2���ԂŃr�[�`�𗎂Ƃ����B�J�[�������Ńp���܂ň�C�ɐ�ԑ��𑖂点�铹�H���J�ʂ���B ����A�h�C�c�R�̏����̎����҂͖�9,000�l�A�ߗ��͖�20���l�ɒB�����B ���̐킢�ɏ��������A���R�̓h�C�c�{�y�ɐi�U���邽�߂̑�������B�ɒz�����Ƃɐ������A�㗤�����͂��̌��3�����Ԃ̐퓬�Ŗ�7��3000�l�̐펀�҂ƁA15��3000�l�̕����҂��o���Ȃ�����A8��25���Ƀp��������B��90���Ńt�����X�̂قڑS�y��A���R���D�҂����B�i�`�X�E�h�C�c�́A�\�A�Ƃ̓�������A�C�^���A����ɉ����āA��������ł��퓬��]�V�Ȃ�����邱�ƂɂȂ�A1�N���炸��1945�N5����{�ɂ͍~���ɒǂ����܂ꂽ�B ���X�s���o�[�O�ē̉f��w�v���C�x�[�g�E���C�A���x�ŕ`���ꂽ�I�}�n�r�[�`�̑s��Ȑ킢�B https://www.youtube.com/watch?v=Kz5c57K9o2o�@�i�U���j �k�m���}���f�B�[�ČR�p���n/ Normandy American Cemetery and Memorial�l �m���}���f�B�[�㗤����2����A1944�N6��8���ɐ펀�����č����m�̂��߂̉���n���I�}�n�r�[�`�ƃC�M���X�C�������n����f�R�̏�ɐݒu���ꂽ�B��n�̖ʐς�70�w�N�^�[���ōb�q������̖�18�{�B9,388�l�̕ĕ�������A���̑唼���㗤���Ƃ��̌�̃��[���b�p����̌R�����̐펀�҂��B �t�����X���{�͎����̂��߂ɐ���Ă��ꂽ�ĕ������Ɋ��ӂ̋C���������߁A1956�N�ɂ��̍L��ȓy�n��Đ��{�ɑ��u���Ԗ������v�u�����v�̍P�v�I�ȑd�ؒn�i�����Ⴍ���j�Ƃ��Ē����B���݁A�č����{�����̕�n���ێ��E�Ǘ����Ă���A�N��100���l���K��Ă���B ��n���̋L�O��ɂ́A�m���}���f�B�[�㗤���Ƃ��̌�̌R�����Ɋւ���n�}��ڍׂ��L�ڂ���Ă���B �����҂̕�͔������T�嗝�ŁA9,238����e���\���i�v���e�X�^���g�ƃJ�g���b�N�j�A151��_�r�f�̐��i���_�����j�B�����A�A�����J�R���F�߂Ă����@���͂���3�����ł��������߁A���̃^�C�v�̕�W�͑��݂��Ȃ��B304�l�̖������m����������A�ނ�̕�ɂ́uHERE RESTS IN HONORED GLORY A COMRADE IN ARMS KNOWN BUT TO GOD�i�_�݂̂��m���F�������A�h������h���̂����ɂ����ɖ���j�v�ƍ��܂�Ă���B �~�n�ɂ́u�s���s���҂̕ǁv������A�I�[�o�[���[�h��풆�ɍs���s���Ƃ��ꂽ1,557�l�̌R�l�̖��O�����܂�Ă���B�����҂̒��ɂ́A�Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�哝�̂̑��q�Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�E�W���j�A������A��ꎟ���E���Ő펀�������[�Y�x���g�哝�̂̂�����l�̑��q�A��s�m�̃N�G���e�B�����ׂɉ������ꂽ�B ��n��10�̋��ɕ�����A�i�C�����h�Z��̃v���X�g���ƃ��o�[�g��F�n��ɖ����Ă���i�W�҂����߂Â��Ȃ��j�B ��1941�N�̃o���o���b�T���ɂ��h�C�c�R�̃\�A�N�U�ȗ��A�h�C�c�̗����͂͂قƂ�ǂ���������Ɍ������Ă���A�X�^�[�����͉p�Ăɑ��ăt�����X�ɑ������z�����Ƃ��ĎO�v�����Ă����B�����āA1943�N5�����V���g���ł�F.���[�Y�x���g�ƃ`���[�`���̉�k�ŏ㗤���̎��{�����肳��A47�t�c�̓��������F���ꂽ�B����̓C�M���X�R�A�J�i�_�R�A���R���[���b�p�R26�t�c�ɃA�����J�R21�t�c�ł���A��1�N�̏�����300���߂��������C�M���X�{�y�ɏW���������B6��6���iD�f�[�j�����́A��������3����t�c�i�C�M���X��6����t�c�A�A�����J��82�A��101����t�c�j�̗����P����������ɍ~�����ēƌR�����������A��ԑ��������t����i�C�݂Ɍ����킹�Ȃ��j���Ƃɐ��������B�����ď㗤�\��n�ւ̋�P�Ɗ͖C�ˌ����s��ꂽ�B�ߑO6�����A�͒���600�ǂ̉���̉��A�A���D����4000�ǂ�5�����t�c�A3�@�b���c��̕��͂�70km����C�݂�5�����ɏ㗤������B�A���R�͏����ɕ�����15���l�A�e��ԗ�7000���A�⋋����3500t���A�܂�7�����܂ł�156��7000�l�A33��3000���A160��t��g�������B �����R�̑��Q�\�z�̐��m���ɒ�]�̂������A�����J��1�R�i�ߊ��I�}�[���E�u���b�h���[�����́A�퓬�J�n�㐔���Ԃ�50,000�l�̎����҂���ƌx�������߂Ă����B�����AD-�f�C�̑O����V�C�����ꂽ���߁A�h�C�c�R�i�ߕ��͓��ʘA���R�̐N�U�͂Ȃ��Ɣ��f���A���������̓h�C�c�{���ɋA�����Ă���ȂǁA�h�C�c�R���ɋْ������������Ă���A���S�Ȋ�P�ɂȂ������ƂŁA�����҂͑啝�ɗ}����ꂽ�B ����U��������̔ߌ��͉f��w�j��ő�̍��x�i1962�j�ŕ`����Ă���B ���������A���̏㗤���ł����Ƃ����Q�������̂͐��ƂȂ����m���}���f�B�̏Z�������������B�㗤�O�̘A���R�ɂ�鏀��������D-�f�C�܂łɃm���}���f�B�𒆐S�Ƃ���15,000�l�̏Z�������S���A�����҂�19,000�l�ɂ��B�����B�㗤�O��P�ɂ���Ď��m���}���f�B�̏Z���́AD-�f�C�ɂ�����A�����J�R�̎��҂�������3,000�l�ɒB�����B�����āu�m���}���f�B����v�܂łɃh�C�c�R�ɎE�Q���ꂽ��A�퓬�Ɋ������܂�Ď��S�����s����19,890�l�ɂ��y�B�A���R�̋Ŏ��S�����t�����X�����̑�����70,000�l�ɂ��B���A�h�C�c�R�̋�P�ɂ���Ď��S�����C�M���X�����̐l����傫�������Ă���B ���J�[���L�O�����فi�������A���E�h�E�J�[���j�̓m���}���f�B�[�㗤���̊֘A���𒆐S�ɓW���A���Ɏ�����j�����ǂ镽�a���F�O�����L�O�فB �����^�r�[�`�ɏ㗤�����ĕ����̒��ɂ͏����Ƃ̃T�����W���[�i1919-2010/����25�j�������B�㗤�̈ꂩ����A�T�����W���[�͐V���f�ڂ��ꂽ�Z�ҏ����u�Ō�̋x�ɂ̍Ō�̓��v�̒��ő�ꎟ���E���̎v���o���ւ炵���Ɍ�镃�e�ɑ��āA�o�����O�̕��m���������_���Ă���B�u������A���ӋC�Ȃ悤�����ǁA�l�͐푈���I�������A��������Đ�Ή������Ȃ��B���ꂪ���̐푈�ɎQ�������S���̋`�����Ǝv���B���҂��p�Y�ɂ܂�グ�Ă͑ʖڂȂB�l�炪�A�҂��āA�q���C�Y�����̃S�L�u�����͍̚����̌����̂ƁA�b���ď����ĊG�ɂ��ĉf��ɂ�����A���̐���͖����̃q�g���[�ɏ]�����ƂɂȂ邾�낤�B �h�C�c�̎�҂��݂�Ȗ\�͂��y�̂��Ă�����A�q�g���[�����Ď����̖�S���ЂƂ�ʼn��߂邵���Ȃ���������v�B |
���G�g���[���M����`������m�̕�i�t�����X�A�p���j2009
Arc de triomphe de l'Etoile , Paris , France
 |
 |
 |
| �V�����[���[�ʂ�̐��[�Ɍ��� | ������m�̕� | ���j�������Ԃ�i�|���I���� |
1836�N�Ƀi�|���I������点���B�M����̐^���ɂ͑�1�����E���Ő펀�����g���s���̖������m�̕悪����B
���h�D�I����������n�i�t�����X�A���F���_���j �i1914�j2023
Douaumont Ossuary & Fleury-devant-Douaumont National Necropolis , Verdun , France
 |
 |
| ��̊C�A1��6��̊�B����̔[������13���l������ | ���哝�̂ƃh�C�c�̕��a�錾�i���ꁕ�ƌ�j |
| 1914�N7��28���ɖu��������ꎟ���E���ł́A32�J����2�̐w�c�ɕ�����ĂS�N�Ԑ�����A�l�ގj�㏉�̐��E��킾�B�Q�퍑��푈�Ɋ������܂ꂽ�n��́A2018�N���_�̍��Ƃɓ��Ă͂߂�Ɩ�50�J���ɒB����B
�푈�Ɏ��闬��́A����36�N�O�A1878�N�ɃI�[�X�g���A�E�n���K���[��d�鍑���A����܂ŃI�X�}���鍑�i�g���R�j�̎x�z���ɂ����������{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i���̂��A30�N���1908�N�ɓ������������ƂɎn�܂�B �����A�o���J�������ł̓��V�A�鍑����돂�Ƃ���ăX������`�ƁA�I�[�X�g���A�鍑�E�h�C�c�鍑�̎x������ăQ���}����`���Η����Ă����B�{�X�j�A�͐l���̑唼���X�����n�ɂ�������炸�A�Q���}�������ł���I�[�X�g���A�̐�̉��ɂ��������߁A�����ɂ͓����X�����n�̗��Z���r�A�����ւ̕��������߂��Z���r�A��`�i�ăX���u��`�j���䓪���Ă����B �I�[�X�g���A�ɂ��{�X�j�A��������6�N��i1914�N�j�A�����ɔ�����{�X�j�A�n�Z���r�A�l�̖�����`�҃K�������E�v�����c�B�v�i1894-1918/�_�Ƃ̎q�B����19���a�����O�j�́A6��28���A�R�����K�̊ω{�̂��߃T���G�{�i�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i��{�j��K�₵���I�[�X�g���A�c���q�t�����c�E�t�F���f�B�i���g�v�Ȃu�ƏP�����A�ˎE�����B�t�����c��50�A�܃]�t�B�[��46�ŔD�P���������B���̃T���G�{��������ꎟ���E���̈������ƂȂ�B ���ÎE�ɐ��������v�����c�B�v�͐_������Ŏ��E��}�邪�s�Ǖi�Ō��ʂ��Ȃ��A���e���E�����悤�Ƃ��ČQ�O�Ɏ�艟������ꂽ�B�ނ͔ƍs��20�ɒB���Ă��Ȃ��������ߎ��Y��Ƃ꒦��20�N�̌Y��鍐���ꂽ�B�̂������B �c���q�ÎE�O���[�v����Z���r�A��`�i��X���u�������̓����j����������閧���Ёu����g�v�Ɏ����������Ă������Ƃ���A�I�[�X�g���A�E�n���K���[���{�̓T���G�{�����̍������Z���r�A���{�ƒf�肵�A�I�[�X�g���A�����ɂ��Z���r�A�����ł̑{�������̎��R��v�����čŌ�ʒ����������B���V�A�́u�Z���r�A���U�������I�[�X�g���A�E�n���K���[�ɑ��ČR������v�ƌx���������A�ÎE�������炿�傤�ǂP�������7��28���A�I�[�X�g���A�E�n���K���[���{�̓Z���r�A�ɐ���z���A�����͊J�킵���B ����3����A7��31���Ƀ��V�A�͌R�����B�t�����X���h�C�c�ɑ���J�폀�����ƂƂ̂����B 8��1���A�h�C�c�����V�A�ɐ��z���B 8��3���A�h�C�c���t�����X�ɐ��z���B 8��4���A�ԓx��ۗ����Ă����C�M���X���h�C�c���t�����X�U���̂��߂ɒ������x���M�[��N�Ƃ������Ƃ������Ƃ��ăh�C�c�ɐ��z���B�C�M���X�͎Q�킵���̂��A�C���h�Ȃǂ̐A���n���畔�������W�����B 8��23���ɂ͓��p�����������Ƃ��ē��{���Q��A�����R���Ȃ̃h�C�c�A���n���U�������B �������āA�唼�̃��[���b�p�卑���Q�킵�A���E���ւƍL�������B �y�Z���r�A��/�A�����z ���V�A�鍑�A�t�����X���a���i�����b�R�ł̌��v���߂����ăh�C�c�ƑΗ����j�A�C�M���X�鍑�́u�O�������v�𒆐S�ɁA�C�^���A�����A����{�鍑�A�A�����J���O���A�Z���r�A�A���[�}�j�A�A�M���V���A�x���M�[�A�����e�l�O���Ȃ�28�J���A���͖�4300���B �y�I�[�X�g���A��/�������z �I�[�X�g���A�A�h�C�c�鍑�A�I�X�}���鍑�A�u���K���A������4�����A���͖�2500���B ���[���b�p�ł̐퓬�́A����(�t�����X�A�x���M�[)�A����(���V�A)�A�암(�Z���r�A)��3�̎�v����œW�J���ꂽ�B ��1914-1915 �J�퓖���̃h�C�c���R�̍��́A�܂���������Ɏ�͂����W���Ė�6�T�ԂŃt�����X�R��œ|���A���̌�ɓ�������Ɍ��������V�A�R�����j����Ƃ������̂������B�h�C�c�R�̓x���M�[�̒������������A�t�����X�k���ւ̐N�U�ɐ�������B�Ƃ��낪���V�A�̓����͑����A�c��j�R���C2���͓������t�����X�ɑ���h�C�c�R�̍U��������(����)���邽�߁A���V�A��1�R�Ƒ�2�R�ɑ��āA���₩�ɓ��v���C�Z���ɐN�U���ăh�C�c��8�R�����j����悤�������B���V�A�R�̕��͂�2�{�ł��苦�͂��Đ킦�h�C�c��8�R�̌��j�͏\���\�ł��������A8��26���A�h�C�c��8�R�i�ߊ��q���f���u���N�叫�i�̂��̃��C�}�[�����a����2��哝�́B�Ō�̓q�g���[���ɔC���j�͓��v���C�Z���̃^���l���x���N(���|�[�����h�k��)�Ő���ł��ă��V�A��Q�R���͂��A�T���Ԃł��������ŁB����Ƀh�C�c�R�̓t�����X�������h�����ꂽ2�R�c�̑��������Č㑱�̃��V�A��1�R�i�����l���J���v�w���j�����j���ē��v���C�Z������쒀�����B���̐킢�Ń��V�A�R��25���̕����Ƒ��ʂ̌R���i�����������A�h�C�c���������������2�R�c�����������Ƃ��t�����X��ɑ傫�ȉe����^����B 9��5������12���ɂ����āA�p���̖k��50km�̃}���k����͂��݁A�h�C�c�R�ƃt�����X�E�C�M���X�A���R���p���̖��^�������Č��ˁB���́u��1���}���k���v�ŁA�t�����X�R�̓h�C�c�R�̐i����j�~���A�h�C�c�R�͖k���G�[�k��܂Ō�ނ����B����ɂ��A��������ɂ������h�C�c�̏����̋@��͎�����B��s�̖h�q�w�����K���G�j���R���A�}������̂����߃p������O���܂�600��̃^�N�V�[�p���A��������ӂŖ�6000�l�̃t�����X�R���m���ڑ�������b���悭�m���Ă���B ���̌�̐�����P��(�������Ⴍ)���A1914�N���܂łɗ��R�̓X�C�X�������烔�F���_�����ւĖk�C�ɂ������800km���̒�������őΛ����A�t�����X���c�f����͍��Q���z���ꂽ�B ��������ł́A���I���܂ŗ��R���S��ԂƋ@�֏e���Ō��łɖh�䂳�ꂽ�͍��i�����j�w�n�����܂��A�D���̒������v��ƂȂ����B�G�̑�C��@�e�̍U�����畺�m�����͍��̐[���́A1.8�`2.5m�B�O�d�ɂȂ��Ă���A�őO���̎U�����̌��ɂ͉���(�����)��������A�G���U�����������Ă����ꍇ�ɂ�2�Ԗڂ̖h����ɂȂ����B���̌���ɂ͔�Ԃ̕��m�����̐����ꏊ�ł���x����������A�⋋������H�ƁA�V���̕��m�͖Ԃ̖ڂ̂悤�ɂ͂�߂��炳�ꂽ�A�������Ƃ����đO���Ɉړ������B�Λ�����G�R�Ƃ̊Ԃɂ͒��Ԓn�т�����A��ɓG�̏e�C���ނ����Ă����B 1915�N4��22���A�h�C�c�R�͑�2���C�[�y���̐�ɂ����āA�x���M�[�̃C�[�y�����U�����Ď��s�������A�h�C�c�R�͂��̐퓬�Ŏj�㏉�̓ŃK�X������������A�������w����̓o��Ő푈�͖����ʎE�C��̗l�����ꋓ�ɋ��߂��B�₪�ė��w�c�Ƃ��ŃK�X���g���悤�ɂȂ�A�ŃK�X�̎�ނɂ́A�ڂ��݂��Ȃ�������́A�畆�������ꂳ������́A�x�������߂���̂Ȃǂ�����A���m�����ɂ́A�ŃK�X�̊댯����g���܂���K�X�}�X�N���z�z���ꂽ�B �C���ł̓C�M���X�C�R�i�͑��j���h�C�c�C�R�̐�͂������Ă������A�h�C�c������U�{�[�g���C�M���X�������͂��A�A�����̑D���ɑ傫�ȑŌ���^���Ă����B1915�N5��7���A1959�l�̏�q�Ə�����̂��ăj���[���[�N����吼�m�����f�����C�M���X�̑�^�q�D���V�^�j�A�����A�A�C�������h����U�{�[�g�̋�������20���������Ȃ������ɒ��v�A1198�l�̏�q(�����A�����J�l128�l)�����S�����B �A�����J�͒�����錾���Ă������A���̎������_�@�ɔ��h�C�c�I�Ȏp���������������߂��B���̂��߃h�C�c�͐����͐���ꎞ�ɘa����B ��̐킢�ł�1914�N8��30���A�h�C�c�ɂ�鏉�̃p������������A12��21���ɂ͏��̃C�M���X�����������Ȃ�ꂽ�B1915�N���痂�N�ɂ����A�h�C�c�̃c�F�b�y������s�D���C�M���X�����ƃ����h����60��������B15�N������́A�q��@���m�̋킪�p�ɂɂȂ�B ��������ł�1915�N5���A�h�C�c�E�I�[�X�g���A�R�͒����|�[�����h�ő�U�����J�n���A9���܂łɃ|�[�����h�A���g�A�j�A�Ȃǂ��烍�V�A�R���쒀���ă��V�A�����ɐi�o�������߁A�K���c�B�A�i�E�N���C�i�쐼���j�ɐN�U���n���K���[�U���̏��������Ă������V�A�R�͖{���h�q�̂��߃K���c�B�A����P�ނ����B �암����ł́A�I�[�X�g���A�E�n���K���[�R���Z���r�A�ɐN������ƃZ���r�A�l�͌�������R�����B�����A1915�N10��11���A�u���K���A���������ɖ������ĎQ�킷��ƁA�Z���r�A�R�Ɖ��R�̉p���R�͌��j����A12���ɃZ���r�A�S�y����̂��ꂽ�B�p���R�̓M���V���̃e�b�T���j�L�ɓP�ނ��čR��𑱂��A�c���Z���r�A�R�����Ӎ��Œ�R�����B �g���R����ł́A�I�X�}���鍑�R�����V�A�ɐN�U�������������������ނ��ꂽ�B�p���R�̓��V�A�~���̂���1915�N4���Ȍ�A�g���R�����̃K���|�������ɏ㗤����2�x���s�������A�w���̗���ƃI�X�}���鍑�R�̌������R��ɂ����č��͎��s�A5��26���ɐӔC�������ĊC���`���[�`������C���ꂽ�B �����m�n��ł́A1914�N8�`9���A�j���[�W�[�����h�R���h�C�c�̃T���A���A�I�[�X�g�����A�R���h�C�c�̃j���[�M�j�A���̂����B11��7���ɂ͓��{�������R���Ȃ̃h�C�c�̋��_�ł���`���^�I(��)��D��A�����11�����܂łɓ��{�̓}�[�V���������A�}���A�i�����A�p���I�����A�J�����������ɂЂ낪��h�C�c�̓�m�������̂����B���I����A���{�͂���珔���̑唼�̈ϔC���������ۘA�����珳�F�����B ��1916 1916�N2��21���ߑO7��15���A�^�~�̒��B�O�N�ɓ�������Ń��V�A�R�ɏ��������h�C�c�R�́A�P�������틵��ŊJ���邽�ߖ�50���l�̕����𐼕�����Ɉړ����A�t�����X�͍����̓��[�Ɉʒu���p���ւƑ����X���ɂ���t�����X�R�̋��_�A���F���_���֑啺�͂������Č����������݂��B ���́u���F���_���̐킢�v�͑�1�����E��풆�̂����Ƃ��傫�Ȑ퓬�̂ЂƂƂȂ�B���F���_���͐�ɖʂ��鍂�n�̏d�v�n�_�ɂ���A�����̗v�ǂȂ�19�̑�K�͂Ȗh��{�݂ō\�����ꂽ�v�Ǔs�s�B�h�C�c�R�͏d�C808��A��C300��������ĖC��ɏW���C�����т��A�c��Ȑ펀�҂������Ȃ�����O�i�����B 2��25���A�h�C�c�R�͈�тōł��傫�������Ԃ̃h�D�I�[�����v�ǁi���FFort de Douaumont�j����������Ɗח������A���F���_���h�q�̗v���������t�����X�R�ɏՌ���^�����B�v�ǂ͓S�R���N���[�g�ŏ㕔��ی삷��ߑ㉻���{����Ă������A������͓G�̑���a�C�̌������C������g����邽�ߍԂ̉��w���ɔ��Ă���A�J����������h�C�c�R�̏����ȏP�������ɊȒP�ɐN���������Ă��܂����B �����t�����X�R�i�ߊ��Ƀt�B���b�v�E�y�^�����R�i����60�j���C�������B�y�^���w�����̕��m�́A���W���`�ʼn�����h�C�c�R�̔g��U�����}�����A�����̋��_��D���Ȃ�����A���F���_���ւ̑S�ʓI�Ȑi�����~�߂��B���̐킢�����Ր�Ɨ������Ȃ��h�C�c�c���q���B���w���������̓��F���_���U���ɌŎ����A���R�Ƃ��D�����Ɏt�c�𓊓����đ���ȑ��Q���o���Ă����B�t�����X��R��4���܂łɐ��̐����m�ۂ��A���F���_���h�q�����蔲������͂ƂȂ����B 3��18���A���V�A�R�͗F�R�̃t�����X�R����u���F���_���ւ̍U�������炷���߁A��������ōU���ɏo�ăh�C�c�R�̐�͂U�����ė~�����v�Ə��������߂��A���x�����[�V�Ńh�C�c�R�ɍU�����d�|�����i�i�[���`�̐킢�j�B����35���l�̃��V�A�R��7���l�̃h�C�c�R�ɑ��Đl�C��p���Ƃ�A�h�C�c�R�̋��łȚ͍��w�n��@�����ߖc��Ȑ��̃��V�A���������ꏊ�ʼn��x�����x���퓬�ɓ������ꑱ�����B���V�A�R�͏�������15,000�l�̎����҂��o���A������5600�l�̎����҂��o���B3��30���A��J�ň�т̑啔�������n�Ɖ��������߃��V�A�R�͍U�����I�������B�s�k���i���������A5�{�߂��������o�������V�A�R�͎m�C��ቺ�����A���̐킢�Łu���Ƃ���R���ł����Ă��A���͂ȉΗ͂�L����͍��ɑ��ẮA��͂̒��������Ɛ��ʂւ̔g��U���͖��Ӗ��v�Ɨ��������B? 5��8���A�h�C�c�R���苒�������F���_���̃h�D�I�[�����v�ǂŒe��ɂ��唚�������B���S�l�̕��m���������A1,800�l�̐����҂̂��������炯�ɂȂ������l���́A�E�o���ɓG���ƊԈႦ��ꔭ�C���ꂽ�B 5�����{�A�t�����X�R�̓h�D�I�[�����v�ǂ̒D�҂����݁A�t�����X�R�̑�C�͍Ԃ�C���������A���̈�т����ʂ̂悤�Ȃ������炯�̕��i�ɕς����B 6��2���A�h�C�c�R�̓��F���_���ŐV���ȍU�����J�n���A6���V���Ƀ��H�[�v�ǁi���FFort de Vaux�j���ח������A���ƒe�s���č~������������̃��C�i���i�ߊ��ɁA��5�R�i�ߊ����B���w�����c���q�͌h�ӂ�\���ăt�����X�R���Z�̌������B�����A���F���_���ł̃h�C�c�R�̍U���͂����܂ł������B���F���_���~���̂��߁A���V�A�R�ɂ��u���V�[���t�U���ƃC�M���X�R�ɂ��\�����U�����N����A�h�C�c�R�͂�����ɐ�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂��B 6��4���A�u���F���_���̐킢�v�̒������ɂƂ��Ȃ��A�Ăюx�������߂�ꂽ���V�A�R�쐼���ʌR�i�ߊ��̃A���N�Z�C�E�u���V�[���t���R�́A�K���c�B�A�i���E�N���C�i�����j�̃I�[�X�g���A�E�n���K���[�R�Ń��V�A�R�ƒ������������R���R�J�����ɂ킽���Č��˂���u�u���V�[���t�U���v���n�܂�B���V�A�R�́u�i�[���`�̐킢�v�̐l�C��p�̔��Ȃ��������Ė��d�Ȑ��ʓˌ��������A�I�[�X�g���A�R�̖h�q���ɔE�ъ���Ċ�P�U������Ă��B�u���V�[���t�͒Z���Ԃ������m�ȖC�����s���A�����̓��ʂɌP�����ꂽ�u�ˌ������v��p���ăI�[�X�g���A�R�͍̚����̎�_���P���A���V�A�R��͂̑O�i�ɕK�v�ȓ˔j�����J�����B���̃u���V�[���t�̊v�V�I��p�́A�̂��ɐ�������ŗp�����邱�ƂɂȂ�h�C�c�R�̐Z����p�̐�삯�ƂȂ����B�O���������I�[�X�g���A�R�͑S�ʓI�ɔs�����n�߁A���V�A�R��20���l�ȏ�̕ߗ��������A�u���V�[���t�̕����̐i�R�̑����ɑ����������Ă���ꂸ�A�t�Ƀh�C�c�̃q���f���u���N���R�͓S���Ԃ𗘗p���ē�������ւ̑f���������ɐ��������B�₪�ēG�������ɔ敾���A�h�C�c�E�I�[�X�g���A�R�����W���ꂽ���[�}�j�A�x���̂��߃��V�A�R�͕����𑗂�K�v�����������߁A9��20���ɂ悤�₭�U���͏I���B�u�u���V�[���t�U���v�̓I�[�X�g���A�E�n���K���[�R�ɂƂ��čň��̎S�s�ł���A�������ɂƂ��čŗǂ̏����ł������B�R�J�����̊Ԃɗ��R���킹��200���l�O��̎����҂��o���A����͂̂��̑���E���̃X�^�[�����O���[�h�̐킢�ɕ��Ԑ��ł���B�u���V�[���t�̐�p�͑���E���ł̃h�C�c�R�̓d�����A���R�̍U���Ŋ��p���ꂽ�B �h�C�c�R�����F���_���U���𒆎~���ē�������ɑ傫�ȑ��������𑗂炴��Ȃ��������ƂŁA�u�u���V�[���t�U���v�͍��̑��ړI��B�������B�I�[�X�g���A���n���K���[�R��150���l�̑����i�ߗ�40���l�j���o���A����ȍ~��x�ƍU�����ɐ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B���V�A����50���l�̑傫�ȑ������o�������A���V�A�R�̕��͖͂c��ł���A���̑����͌R���I�ɂ͋��e�ł�����̂ł������B����A�h�C�c�R�͑���ȋ]�����Ă������F���_���U���𒆎~�������Ƃɂ��Q�d�����t�@���P���n�C�����X�R����A��C�̃q���f���u���N�A���[�f���h���t���A�C�B���[�f���h���t�ƍق��n�܂�A��ɐ����͂ɂ�閳���ʍU���ŃA�����J�Q��Ƃ�������ށB��������ł̓��V�A�R���S����ōU�����J�n���Ĉꎞ�I�ɐ����������߂����̂́A��10���l�̑��Q�������Ďm�C�̒ቺ�Ɖ}��(����)�C���̑�����܂˂��A���V�A�v���Ɍq�����Ă����B 7��1���A��ꎟ���E���ɂ�����ő�̉��u��1���\�����̐킢�v�̉ΊW������B���V�A�R�́u�u���V�[���t�U���v�Ǝ��������킹�A�p���A���R�̓h�C�c�R�ɂ�郔�F���_���U�����y�����邽�߁A�k���̃\�����쉈���̃h�C�c�R�w�n�ɑ�K�͍U�������킦���B�t�����X�R�̓��F���_���ő傫�����Ղ��Ă���A�\������̎�U���̓C�M���X�R�ɂ䂾�˂�ꂽ�B�C�M���X�R�i�ߊ��̓w�[�O���R�A�t�����X�R�̓W���b�t�����R�A����h�C�c�R�̓q���f���u���N���R�ƃ��[�f���h���t���w�������B �J�평���A�C�M���X�R�̓h�C�c�R�͍̚���˔j���đ��h�q���܂Ői�ތv�悾�������A�ʐM�A�����r�₵�ĘA�g�ł����A���łȖh�q�w�n��O�ɃC�M���X�R�͂������P���Ŏ�����7���l�ȏ�i�U���ɎQ������������91���j���o���Ă��܂��B����͐펀19,240�l�A�폝57,470�l�ł���A����͐퓬1���̔�Q�Ƃ��Ă͑�풆�ōő��ƂȂ����B���ǁA�h�C�c�R�͍̚���˔j�ł��Ȃ��܂ܑO�����P�����A�����ł��͍���ƂȂ�B 9��15���A��1���\������ŃC�M���X�R�͎j�㏉�߂Ĕ閧����u��ԁv(�}�[�N�T�^)����ɓ��������B��Ԃ͚͍������z�����邽�ߍU���̐�D�ƂȂ蓾�����A49���z�����ꂽ��Ԃ̂����ғ��ł����̂�18���ŁA����ɎQ���ł����̂�5�������ł���A�\�����ł͋@�������ł��Ȃ������i�}�[�NIV�^��ԂȂǐ�Ԃ�����悤�ɂȂ����̂͗��N�ȍ~�j�B 9�����Ƀ\�����n���͓V��s�ǂŒn�ʂ��D���炯�ƂȂ��č�퍢��ƂȂ�B�Ȃ����p���R�͍U���𑱂�����3�J���ɂ킽��U���ŏ��Ռ������A�h�C�c�R�����˔j�ł��Ȃ��܂�11����{�ɂ͗��R�Λ��̌`�ƂȂ����B11��19���A�S�J�����������\������͏I�������B �\������͑�평���i�Q�N�O�j�̃}���k���ɔ�ׂĕ���̐��\������I�Ɍ��サ�A�y�@�֏e�����߂ēo�ꂵ�����Ƃ���A���R�̑��Q�͐r��Ȃ��̂ƂȂ����B�����҂̓C�M���X�R��45���U��l�A�t�����X�R��20���l�A�h�C�c�R�͖�50���l�Ƃ����S�R���킹��100���l�ȏ�̑��Q���o�������A�킢�̑O��ŋN�����ω��́A�A���R���킸����11km�قǑO�i���������������i�h�C�c�R���\�����삩��͍��w�n�ւƌ�ނ����j�B ���̍����F���_���ł́c 7��16���A��������ł̃��V�A�R�̃u���V�[���t�U���A�C�M���X�R�ɂ��\�����U�����āA�h�C�c�R�͂Q�̐킢�ɂ��Ȃ�̐�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���F���_���U�������~�����B�h�C�c�R�͖h�q��ɓ���A8������t�����X�R�������ɓ]�����B ���F���_����т́A����1916�N�̐킢�ŁA�h�C�c�R�ƃt�����X�R��16�����́E�D������Ă���B 8��28���A�Q�d�����t�@���P���n�C���������������F���_���U���͎��s�ƂȂ�A�t�@���P���n�C���͍X�R���ꃋ�[�}�j�A�U����̎i�ߊ��ɓ]�o�����B��C�̎Q�d�����Ƀq���f���u���N���A�Q�d�{�������Ƀ��[�f���h���t���C����ꂽ�B���[�f���h���t�͘A���R�̍U���ɐ�Đ������ނ����A���łȚ͍��w�n�сu�q���f���u���N���v�i�W�[�N�t���[�g���j���\�z���Ėh����ł߂��B���[�f���h���t�͎����̎w���������g�債�A�ȍ~�̃h�C�c�̐푈�͎����I�Ƀ��[�f���h���t���w���������ɂ�����A�u���[�f���h���t�ƍفv�ƌĂ�鎞���z���B 9��24���A���F���_���Ńt�����X�R�̖{�i�I�Ȕ������n�܂�A�U����10�������ς������B 10��24���A���R�͐r��ȑ��Q���o���Ȃ�������F���_���ő�̃h�D�I�[�����v�ǂ�D���Ԃ����B 11���P���A�h�C�c�R�̓t�����X�̒������S���C�𐔓��Ԃɂ킽���ĎĂ������H�[�v�ǂ���P�ށB�����A���R�͖��l�ƂȂ����v�ǂ̒D�҂ɐ��������B ��P�O�J�����������F���_���U�h���12���P�X���ɏI�����A�t�����X�̓��F���_����̊J�펞�i2���j�Ɏ������w�n�̑唼�����߂����B ���R�Ƃ��ɐ퓬�ł̑��Q�͖c��ŁA�t�����X�R379,000�l�i��������163,000�l�A������216,000�l�j�A�h�C�c�R336,000�l�i�������� 143,000�l�j�Ƃ����قړ����̎����҂��o�����B 1916�N5��31���A���̊͑����킪�f���}�[�N�̃��g�����h�������ł͂��܂�(���g�����h���C��)�A149�ǂ���Ȃ�C�M���X�͑���110�ǂ���Ȃ�h�C�c�͑������˂����B�C�M���X�C�R�͐��2�ǁA���m��4�ǁA�쒀��8�ǂ��A�h�C�c�C�R�͐��1�ǁA���m��5�ǁA�쒀��5�ǂ������A���I�̃h�C�c�C�R�̋ǒn�I�����ɏI�����A�C�M���X�C�R�̗D�ʂ͓����Ȃ������B 1916�N6���A�A���r�A�����ł́A���b�J�̗L�̓J���t�Ńn�[�V���Ƃ̃t�T�C�������q�̃A���[�A�t�@�C�T���ƂƂ��ɃI�X�}���鍑�Ƃ̓������ĊJ���A�C�M���X�Ɏx������q�W���[�Y(���T�E�W�A���r�A��)�̐퓬���w�������B����́A�O�N��10��24���ɃJ�C���Ő��������C�M���X�����ٖ����}�N�}�z���Ƃ̃A���u�Ɨ����Ƒn���Ɋւ����{�I����(�t�T�C���E�}�N�}�z������)�ɂ��ƂÂ������̂������B�����10��29���A�t�T�C���̓��b�J�Ńq�W���[�Y�����̓Ɨ���錾�A�C�M���X����������F�����B����ɁA�C�M���X��11���ɃA���r�A�����ł̔��R�x���̗z�����Ƃ��āA�G�W�v�g���ԌR���V�i�C�����ƃp���X�e�B�i�ɐi���������B�C�M���X�͂������ăI�X�}���鍑�x�z���̃A���u�l�̎x�����Ƃ�������ŁA�O���o���t�H�A��1917�N11��2���A���E�̃��_���l�Љ�̐푈���͂����邽�߂ɁA�p���X�`�i�̒n�Ƀ��_���l�̍���(���C�X���G��)���݂��݂Ƃ߂�������Ȃ���(�o���t�H�A�錾)�B�A���u���ƌ��݂�F�߂�}�N�}�z�����ȂƁA�C�X���G�����݂�F�߂�o���t�H�A�錾�Ƃ�����������́A�����ɂ܂łÂ��p���X�`�i���ނ��ƂɂȂ�B 1916�N8��27���A���[�}�j�A���A�����w�c�ɎQ�����ăI�[�X�g���A�E�n���K���[�̃g�����V���o�j�A�ɐN�U�������A�����ɓ������R�Ɍ��ނ��ꂽ���肩�A���N1���Ƀ��[�}�j�A�S�y���̂��ꂽ�B����ɂ�蓯�����͋M�d�ȏ����ƐΖ����l�������B1918�N5��7���Ƀ��[�}�j�A�͓������ƃu�J���X�g��������A���C���݃h�u���W���n�����u���K���A�Ɋ��������B ��1917 ���͂R�N�ڂɓ˓����A���܂ł��I���ʐ푈�Ɍ��e���̕��m�����̎m�C�͒ቺ�����B 1917�N2��1���A������ɂƂ��Ȃ������s���ɂ��邵�ރh�C�c�́A���C�����m�ۂ��C�M���X�̊C�㕕����Ŕj���邽�߂ɁA�ꎞ�Ђ����Ă��������͐�������A���ɖ����������͐�ɓ˓�����B��l���I�ȃh�C�c�Ɍ��{�����A�����J��4��6���ɎQ�킵�A�h�C�c�̔s�k���Z���ƂȂ�B���̎Q��ɂ͑��傷��C�M���X�E�t�����X�ւ̎؊���������Ď������{��i�삷��Ӑ}���������B�������A�����̃A�����J�ɂ͖{�i�I�ȗ��R�͂Ȃ��A�R�̑g�D����J�n����������̂ŃA�����J�̎��ۓI�ȎQ���1�N�悾�����B �A�����J���h�C�c�ɐ��z������ƁA�y���[�A�{���r�A�A�u���W�����ӂ��ޑ唼�̒���ď���������ɂ����������B�A�����J�͉����R�����[���b�p����ɔh���A6���ɂ�17��5000�l���̃A�����J�R���t�����X�ɓ����A��������ɓ������ꂽ�B�ŏI�I�ɃA�����J�R�̐�͖͂�200���l�ƂȂ�A�A�����̗D�ʂ͕s���̂��̂ƂȂ����B�E�B���\���đ哝�̂͑����ɑ����I�������A�N���̗��z�ł��鍑�ۋ@�\��ݗ����A�P�v�I�ȍ��ە��a���������邱�Ƃ��}���Ƃ݂Ȃ����B 4���A�t�����X�R�̓G�[�k���Ńh�C�c�R�ɍU�������������s�k�A�t�����X�ʼn}��C�������܂�B����ɐV�C�̃t�����X���R���i�ߊ����x�[���E�j���F�������Ă����p�R�Ƃ̋������u�j���F���U���v�́A�U�������ɕ��R38���l�̕������ˌ��������ʖ�5���l���̑��Q���o���B�t�����X�R�͂T���X���܂ł̖�R�T�Ԃ�18��7��l�ȏ�̑��Q���o���A�����̖C���Ŏ��҂��o��悤�ȁA�������m���ȓˌ���ɕ��m���������S���A113�t�c�̓�49�`68���̎t�c�Ŕ����������B�j���F���̓A�t���J�ɍX�R����A��C�Ɂu���F���_���̉p�Y�v�y�^�����C�������B�y�^���ƎN���}���\�[�͑ҋ����P�ȂǂŔ��������Ƃ��}�����݁A�ȍ~�A���̋]�����Ƃ��Ȃ��ˌ��͔�������悤�ɂȂ����B 5���ɘA���R�͗A���D�c���R�͂���q���A�h�C�c�����͂ɍU�������킦��Ƃ����R���{�C�������̗p�����B���̕��@�̓����ŘA���R�̑D���̑����͌��I�Ɍ��������B �܂��A�A�����J�̕��ʎQ��Ő����͂ɂ���Q��₤���Ƃ��ł����B 6��7���A�x���M�[�k�����C�[�y���ߍx�̃��V�k�i���V�[�k�j���n�ɓW�J����h�C�c�R�C���ɋꂵ�߂�ꂽ�C�M���X�R�́A�h�C�c�R�̒n���Ƀg���l�����@����455�g���̔�����d�|���Ĕ�������1���l�̓ƌR��������u���ɉ�ł������B����͂P�X�S�V�N�ɋL�^���h��ւ�����܂ŁA�j����ȊO�Ől�Ԃ��Ӑ}���čs�������E�ő�̔����ƂȂ����B 7���A�h�C�c�R�͍��n���j�̕�����A�C�[�y���Ń}�X�^�[�h�K�X�����߂Ď��퓊�������B���̃K�X�͔畆��ċz��ɉ��ǂ��N�����A����Ă��Ď����Ɏ���ꍇ������A���ȋ�ɂ����B ���}�X�^�[�h�K�X���ʏ́u�C�y���b�g�v�ƌĂ��̂́A�C�[�y���ŏ��߂Ďg�p���ꂽ���Ƃɂ��B 7���R�P���AU�{�[�g�̍U���ɔY�܂���Ă����A���R�́A�x���M�[�C�ݐ��̃h�C�c�R�����͊�n��苒���邽�߁A�x���M�[�k���p�b�V�F���f�[���̍U����u�p�b�V�F���f�[���̐킢�i�C�[�y���̐킢�j�v���J�n����B�퓬�̓C�M���X�A���B���j���[�W�[�����h�A�J�i�_�A��A�t���J����Ȃ�A�����R�h�C�c�R�̊ԂŐ��ꂽ�B ���̒n��̑啔���͌��X������n�ŁA�C�e�̃N���[�^�[�����������ɂ���A��J���~��Ɛ�Ԃł���ʍs�s�\�Ȓꖳ���������鏊�ɐ��܂ꂽ�B�����̕��m�̑����͖�45kg����A�����̕��m���M�������B ����Richard W. Mercer�u�p�b�V�F���f�[���͍����A�����ꏊ�������B��X�͖ؐ��̓n��̏��������B�n�ʂɉ���������q�̂悤�ȕ����B�h�C�c�R�͂����_�����������B���m��������ĕ������]�����悤���̂Ȃ�A�D�̒��ŗe�ՂɓM��ē�x�ƌ��t����Ȃ������B�Ƃɂ����n����痎�������Ȃ������B�v �h�C�c�R�͚͍��ƃR���N���[�g�̃g�[�`�J�i�C��j�Œ�R���A�R�J���ɂ킽�錃��̖��A�P�P���U���ɐ��s�����̃J�i�_�R���p�b�V�F���f�[����D�҂��Đ퓬�͏I������B�A�����R�̑��Q�͖�45���l�ɋy�B�h�C�c���̑��Q��26���l�ł������B���ł�1�����}�C���i2.56 km2�j����̖C�e�E�͖�P�O�O���𐔂��A�A���R�̂���9���l�̈�̂͐g�������ł����A�܂�42,000�l�̈�͍̂Ō�܂Ŕ����ł��Ȃ������B���e�Ƌ@�֏e�͓D�ō쓮�s�ǂ��N��������������т��ыN�����B �A���R�͓D�y�̒��̐��S���[�g���̑O�i�ƈ��������ɖ��P�ʂ̎����҂��o�����������Ƃ���A���݁u�p�b�V�F���f�[���v�Ƃ������t�́u�����̋ߑ�I�푈���������ɒ[�Ȏc�s���v���ے�������̂ƂȂ��Ă���B �G�h�E�B���E�J���s�I���E���H�[�K�����сu���͗����オ���Ď����������Ă��錊�̑O���߂��B�����ɂ͓D�Ɛ��̉A�T�ȍr�n�̂݁B���̕����̍��Ղ��Ȃ��A�����C�e�E���炯�c�����Ď���Ƃ���Ɏ��̂��������B�C�M���X���ƃh�C�c���̎��̂��A���s�̂���Ƃ�����ߒ����N���Ă����B�v ���C�[�y�������́u�^�[�k�E�R�b�g��n�v�̓C�M���X�A�M�푈��n�ψ���̕�n�Ƃ��Ă͐��E�ő�ŁA12,000��߂���肩�琬��B ��������ł̓��V�A�v���Ƃ����厖�����N�����B1917�N3��8���Ƀ��V�A�̖��O���I�N���A3��15���ɂ͍c��j�R���C2�����ވʂ��ă��}�m�t�����͖ŖS�A�Վ����{���ݗ����ꂽ(���V�A��ɂ��v��)�B�Վ����{�͐푈�s�������A�h�C�c�R��9���Ƀ��K���A10���ɂ̓��g�r�A�̑唼�ƃo���g�C�̏������̂����B 11��7���A���[�j���̎w������{���V�F�r�L�̓P�����X�L�[�̗Վ����{�͂őœ|(�\���v��)�A�\�r�G�g���������������B12��3���A�\�r�G�g�����͓������w�c�Ƌx������J�n����B ��1918 1918�N3��3���Ƀ��V�A�i�\�r�G�g�j�͒P�Ƃōu�a���(�u���X�g�E���g�t�X�N���)������A�푈���痣�E�����B3��5���ɂ̓��V�A�̌㉇�����������[�}�j�A���~���B��������͏I�������B���V�A�̒E���ɘA�����͑傫�ȏՌ����A�A�����J�̎Q��ƃ��V�A�̐푈���E�͑�풆�̍ő�̎����ƂȂ����B �h�C�c�̓��V�A�ƍu�a�������ƂŁA��������̑啺�͂𐼕��ɂ܂킷���Ƃ��\�ɂȂ�A�ƌR�Q�d�������[�f���h���t�̓A�����J���{�i�Q�킵�Ă���O�ɍŌ�̍U���������A�p���R�ɉ�œI�ȑŌ���^���ċx��ɒǂ��������ƍl�����B������3���`6���ɂ����Đ�������ň�čU���u�c��̐킢�i�J�C�U�[�V�����n�g�j�v���J�n�����B���̍U���ɍ��킹�āA�j�㏉�́u�Z�@�֏e�v�Ƃ��ĊJ�����ꂽMP18 ��10,000���ƁA�h�C�c�R���̐�Ԃł���uA7V�v20�q�A�������ԖC�̃p���C�i�J�C�U�[�����B���w�����C�j�Ȃǂ̐V���킪�������ꂽ�B�������A�A�����R�͐�Ԃ��v6,000�q���܂�������\�ł������B 3��21���A���[�f���h���t�w���̃h�C�c�R���Ō�̑�U���ƂȂ�~�q���G���������s�B�h�C�c�R�͑O�N�ɘA���R���x���M�[�̃p�b�V�F���f�[���Ŋl�������y�n���قڑS�ĒD���B�A���R���D�ɂ܂݂�Ȃ���45���l�̑��Q��5�������₵�ē����y�n���A�킸��3���Ŏ���ꂽ�̂��B�h�C�c�R�͊J��ȗ�����8����65km�Ƃ�����O�̉��i�����ʂ������B�����ăp����120�L�������i���������A�i�����x�ɕ⋋�����ǂ������U���͎~�܂��Ă��܂��B �h�C�c�R�̖ړI�̓p���i���̋��_�Ƃ��Ėk���̃A�~�A�����̂��邱�Ƃɂ��������A4��4���A�C�M���X�R�ƃI�[�X�g�����A�R�ɂ���ăA�~�A���̎�O�A��15km���Ői�����~�߂�ꂽ�B���̌�̃h�C�c�R��100���ԂقǍU���������A�C�M���X�A�t�����X�A�x���M�[�A�A�����J4�J���A���R�ƌ�����d�˂Ȃ���A6�����߂Ƀp�������̃}���k��ɓ��B�������A7�����ɐ�͂��g���ʂ������B7��18���A�A���R���i�ߊ��̃t�F���f�B�i���E�t�H�b�V�����R�i�t�����X�R�j�͔��U�𖽂��唽�����J�n�A�u��}���k�̐킢�v�ŏ��������߃h�C�c�R���}���k�삩���ނ������B 8��8���u�A�~�A���̐킢�v���n�܂�B�p�R�̓\�����̖k���Ŋ�P�U�����J�n�A�I�[�X�g�����A�R�ƃJ�i�_�R��������x�����A��� 580 �����������ꂽ�B�A���R�͉������A�S����œ˔j�ɐ�������B���́u�A�~�A���̐킢�v�Ńh�C�c�R�͌���I�Ȕs�k���i���A�ŏI�I�ɑ�ꎟ���E���̏I���ɂȂ������B���[�f���h���t�͂��̊J�평�����u�h�C�c���R�Í��̓��v�Ə̂����B �A���R��8��27���܂ł�50,000�l�߂��̕ߗ���500��̖C��ߊl�����B 8��21������9��3���ɂ����āu��2���\�����̐킢�v���s��ꂽ�B�C�M���X�R30�t�c�ƃt�����X�R15�t�c���h�C�c�R100�t�c�ƌ�킵�A�C�M���X�R�͖�20���l�̎����҂�19���l�̕ߗ����o�����B�h�C�c�R�̎����҂͖�18���l�������B 9�������A�A���R�̓h�C�c�R���\������w��̍ŏI�h�q�w�n�q���f���u���N���܂Ō�ނ����A10���ɓ���ƃh�C�c�R�͑S��������őދp���J�n����B 1918�N9�����A�o���J���ł͘A���R���u���K���A�R����ł������B�C�^���A����уI�[�X�g���A�E�n���K���[����ł́A�C�^���A�R�̍U�����Â��A10���ɂ̓I�[�X�g���A�E�n���K���[�����̃`�F�R�X���o�L�A�A�n���K���[�A���[�S�X���r�A���Ɨ���錾����B �h�C�c�̍ɑ��}�N�V�~���A���͎��E����������Ȃ���c�郔�B���w����2���Ƀ��[�f���h���t��C�����߁A10��26�����Ƀ��[�f���h���t�͎Q�d�{�������������A�����X�E�F�[�f���ɖS�������B �����ł̓C�M���X�R�卲�������X(�A���r�A�̃������X)�̗�����A���u�R�ƃC�M���X�R�������A1918�N10���ɂ̓_�}�X�J�X�A�A���b�|�Ȃǂ̃I�X�}���鍑�̗v�Ղ�D�悷��ԁA�t�����X�C�R�������x�C���[�g���̂����B10��30���A�I�X�}���鍑�͋x�틦��ɒ��A�������w�c����E�������B 11��3���A�I�[�X�g���A�E�n���K���[�͒P�ƂŘA�����Ƌx��B�������A�h�C�c�k�݂̃L�[���R�`�Ő����������N���A������_�@�Ɋv���̗����h�C�c�S�y���������A11��9���ɍc��E�B���w����2���͑ވʂ��ăI�����_�ɖS���A�鐭�͏u���ɕ����B���̍����̒��ŎЉ��}�̓}��G�[�x���g����ǂƂ��鋤�a�����{���������ꂽ�B�푈���I��点�A�������������邽�߁A���a�����{�͘A�����Ƃ̋x������Ƃ߁A�x��g�ߒc��h�������B 11��11���A�h�C�c�g�ߒc��\�G���c�x���K�[�̓p���k���̃R���s�G�[�j���̐X�ɐݒu���ꂽ��Ԃ̒��ŁA�h�C�c�ƘA�����̎g�߂��x�틦��ɒ��A4�N3�J���]��ɂ킽������������ł̐퓬�̓h�C�c�̖������~���������ďI�������B�����A�c��J�[��1�����ވʂ��Ē鐭�����A���̗����ɃI�[�X�g���A���a�����������ꂽ�B 2013�N5���A���F���_����K��Ă����h�C�c�l�ό��q���l�����B���ӂ̔��@���s��ꂽ���ʁA26�̂̈�̂��������ꂽ�B 7000���l�ȏ�̌R�l���������ꏉ�̑��͐�ƂȂ�����1�����E���́A�폟���ɂ��s�퍑�ɂ��c��ȑ��Q�������炵���B�S��퍑�̐��z��1860���h���ɂ̂ڂ�A�n���ł̎����҂�3700���l�]��i�������҂͐퓬��900���l�ȏ�Ɣ�퓬��700���l�ȏ�j�ɒB�����B�܂��A��1000���l�̎s�������������B���̂��߁A����A�P�v���a�̎����ɐ��E�I�Ȋ��҂��悹��ꂽ���A�A�����J�哝�̃E�B���\���́u14�J���̕��a�����v�̑唼�́A���ۘA���̑n�݂��̂����A�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ̐폟���ɖ������ꂽ�B ����̃��[���b�p�̐��͐}�͌��ς����B�h�C�c�A�I�[�X�g���A�E�n���K���[�A���V�A��3�̒鍑�͉�̂��A�鍑�̋��̓y���疯�������̌����ɂ��ƂÂ��ăt�B�������h�A�G�X�g�j�A�A���g�A�j�A�A���g�r�A�A�|�[�����h�A�`�F�R�X���o�L�A(���`�F�R���a���A�X���o�L�A���a��)�A�n���K���[�A���[�S�X���r�A(���N���A�`�A�A�X���x�j�A�A�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i�A�Z���r�A�A�����e�l�O���A�}�P�h�j�A)��8�J�����V���ɒa�������B�A�W�A�ł̓I�X�}���鍑������B�s�퍑�����łȂ��A�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ̐폟�����������v��̔�J���琊�ނ��A�A�W�A�A�A�t���J�ł̔��A���n��`�^�������������邱�ƂɂȂ����B����A�V�����A�����J�Ǝj�㏉�̎Љ��`���\�r�G�g�A�M���䓪���A���̐V���ȍ��ۊW�̊�������邱�ƂɂȂ����B ��㏈���̂��߂ɊJ���ꂽ�p���u�a��c�̓h�C�c�����O���ĐR�c�������߁A�I�ȃx���T�C��������(1919�N6��28��)���h�C�c�ɋ��v�����B�����x�����`���A�S�C�O�A���n�̕ԊҁA����I�R�k�Ȃǂ́A�h�C�c�ɂƂ��Ă���߂ĉՍ��ȓ��e���ӂ���ł����B�h�C�c�����͎Љ�I�������������A�i�`�X�����̒a���Ɍq����A21�N���1939�N�ɑ���E��킪�u�������B �y�揄��z ��ꎟ���E���̃��F���_���̐킢�ł́A1916�N2��21������1916�N12��19����300���ԂŁA20�����L�����[�g���ɖ����Ȃ�����70���l���̎����҂��o�āA������23���l�����S�����B ���݁A���Ŕ������ꂽ13���l�̃t�����X�l�ƃh�C�c�l�̖������m�̈⍜��[�߂��u�h�D�I�[�����[�����v�i1932�N�����j���A�Ð��̏�ɍ������т������Ă���B��O�ɂ�1923�N�ɊJ�݂��ꂽ16,142����̕��i�����ꎟ���E���ő�̃t�����X�R�P�ƕ�n�u�h�D�I�[����������n�v������B ���F���_���̓t�����X�ƃh�C�c�ɂƂ��ċ��ʂ̋ꂵ�݂��v���N�����a���̏ے��ƂȂ�A��ꎟ���E���J��70�N��1984�N�A�h�D�I�[�����[������9��22���ɍs��ꂽ�ƕ���v�ҒǓ����T�ɏo�Ȃ����w�����[�g�E�R�[���Ǝi���̓��F���_���ߍx�Ő펀�j�ƃt�����\���E�~�b�e�������哝�́i���͑���E��펞�Ƀ��F���_���ߍx�ŕߗ��ƂȂ����j�́A�J���~�肵����Ȃ��Ńh�D�[�����[�����̑O�Ő����Ԏ�����荇�����B����A���̏u�Ԃ��L�O����v���[�g���ݒu����A�蕶�ɂ������܂ꂽ�B�u1984�N9��22���A�t�����X���a���哝�̂ƃh�C�c�́A�������̗��j�㏉�߂Ă��̃t�����X�R��n�ʼn�k�����B��̑��̐�v�҂��ÂсA�ނ�͉ԗւ�����A�����錾�����F�s�u��X�͘a�������B��X�͂��݂��𗝉�����悤�ɂȂ����B��X�͗F�l�ƂȂ����v �t�����\���E�~�b�e���� �w�����[�g�E�R�[���t�B 2023�N�̉āA�����^�J�[�Ń��F���_����K�ꂽ�B������n�̖����̏\���˂��ʐ^�Ō������Ƃ͂��������A���ۂɖڂ̑O��1��6���̕��ڂɂ���ƌ��t���������B���E�̔ޕ��ŕ�W���������сA�܂��ɕ�̊C�������B�����ăh�D�I�[�����v�ǂƃ��H�[�v�ǂ̐Ւn�ɑ����^�B�r���ɂ͚͍��Ղ��c���Ă���B���v���ő��ɒN�����炸�A���͂͐Â܂�Ԃ�A���܁A�Q����ɋA�钹�̐����������邾���������B��������Ƃ��n�߂��푈�ɋ��o����A�������Ȃ�����ƎE�������͂߂ɂȂ�A�̋��ɋA�ꂸ���n�ɖ��������܂�ɂ��s���Ȑl�X�̂��߂ɁA�S����ٓ���������B ����A��ꎟ���E���̍ő�̌���n�\�����ɂ��A����ȁu�e�B�[�v���@���L�O��v�������藧�B���̋L�O���1932�N8��1���A�t�����X�哝�̃��u�����̗���̉��A�G�h���[�h�c���q�i��̃G�h���[�h8���j�ɂ���ď������ꂽ�B�c�����i�������낷�ꏊ�Ɍ����A���G�Ȍ`���̃��C���A�[�`�������ɕ��сA�ǖʂ�72,246�l�̏��Z�ƕ��m�̖��O�����ށB�A�[�`�̏㕔�ɂ́A�t�����X��� "Aux armees Francaise et Britannique l'Empire Britannique reconnaissant"�i�t�����X�ƃC�M���X�̌R���ɑ�p�鍑�͊��ӂ��Ă���j�ƒ����A�������ɂ�1914�N��1918�N�̔N�������܂�A���E�ɕ����ꂽ���ʂ̃A�[�`�̏�[�ɂ́A�u�\�����̍s���s���ҁv�ƍ��܂�Ă���B��ƃT�L�͖{���w�N�^�[�E�q���[�E�}�����[�iHECTOR HUGH MUNRO�j�ŕǖʁu16 A�v�ɁgMUNRO H.H.�h�ƍ��܂�Ă���B ���n�ł͖��N7��1���i�\������̊J����j�ɋL�O��ő�K�͂Ȏ��T���s����B�L�O��̂ӂ��Ƃɂ́A�p�A�M�R300�l�A�t�����X�R300�l�̕���܂ރe�B�v���@���p����n������B�������ꂽ���m�̑啔���i�C�M���X�A�M�R239���A�t�����X�R253���j�͐g���s���A�C�M���X�̕�ɂ́u���̕��m/�_�ɒm��ꂴ��ҁv�ƍ��܂�A�t�����X�̏\���˂ɂ́uInconnu�v�i�u�s���v�j�̈ꕶ�������܂�Ă���B��n�̉��ɗ��u�]���̏\���ˁv�ɂ́A�s250���̐펀�҂̋��ʂ̋]���𐢊E���L�����邽�߂ɁA�����Ƀt�����X�Ƒ�p�鍑�̕��m���i���̓��u�Ƃ��ĕ���Ŗ���t�Ƃ���B �u�e�B�v���@���L�O��v��2023�N�Ɂu��ꎟ���E���̐�v�ҕ�n�Ɛ�v�ҒǓ��{�݁i��������j�v�Ƃ��ă��l�X�R���E��Y�Ɏw�肳�ꂽ�B ����1�����E���ɏ]�R�����C�M���X�̎��l�E�B���t���b�h�E�I�[�G�� (Wilfred Owen, 1893-1918) �́A10�Ŏ�����n�߁A���}���h�̎��l�����A���Ƀ��[�Y���[�X�ƃW�����E�L�[�c���D�B18�����w�ŐA���w���w�сA��������Ă���l�X���������Ȃ����ƂɌ��ł����B20����t�����X�̃{���h�[�ɂ��鍑��w�Z�ʼnp��ƃt�����X���������ƒ닳�t�Ƃ��ē����B��1914�N�A��ꎟ���E��킪�u������B�I�[�G����1915�N�ɂQ�Q�œ������A1917�N1���ɏ��Z�Ƃ��ăt�����X����ɔz�����ꂽ�B�C�e�̌��ɗ����Ĕ]�k�Ƃ����N�����A�͍��Ŕ����C�̔����Ɋ������܂�A�����Ԉӎ��s���̂܂ܒ��Ԃ̈�̂̒��ɉ�������Ă����B�I�[�E�F���͏d�x�̐_�o�ǂƐf�f����A���Â̂��߃G�f�B���o���i�X�R�b�g�����h�j�̃N���C�O���b�N�n�[�g�푈�a�@�ɑ���ꂽ�B�×{���ɂV�ΔN��̎��l�W�[�O�t���[�h�E�T�X�[���i1886-1967�j�ƒm�荇�����B�ނ͎t�T�X�[���ɗ�܂���A1917�N�̉Ă���͍���K�X��̋��|��`�����푈���������n�߁A��n�֑����Ă������m�B�̎p��`�����u������v��A�킢�̔ߎS����`�����u�����ׂ���߂̎�҂̂��߂̎^�́v (Anthem for Doomed Youth) �Ȃǐ푈�̌������ɂ����B�����͈�ʂ̈����I�Ȏ��Ƃ͑ΏƓI�ł������B�I�[�G���͓ŃK�X�ɂ���Ď��ɕm�����ЂƂ�̕��m�ɂ��Ă̎���ʂ��āA�Ñネ�[�}�̎��l�z���e�B�E�X�̃I�[�h�W�u�̏́v�ɂ����߁A�u�c���̂��߂Ɏ�����͊Â��A�����Ė��_������̂Ȃ�v�Ɉًc���ƂȂ����B1918�N7���A�I�[�G���̓T�X�[���̔���������A�����ɐ�������ɕ��A����B10���A2�����т̔ނ͑�2����̒����������������ہA�����ȃ��[�_�[�V�b�v�����Ďw��������A���̗E�C�Ǝw���͂��F�߂�����\���M�͂���͂����B�����đ�ꎟ���E���x��̂��傤�Lj�T�ԑO�ɂ�����1918�N11��4���ɃT���u�����I���[�Y�^�͉��f���ɂQ�T�Ő펀���A�������тɏ��i�����B�I�[�E�F���̓t�����X�k���I���X�ɂ���I���X������n�ɖ������ꂽ�B�x�퓖���A�ނ̐펀�������I�[�G���̕�̋��ɓ͂���ꂽ�B�I�[�G���̎��̂����A���O�ɏo�ł��ꂽ�̂͂킸��5�ҁB���E2�N��A�F�l�T�X�[������e���W�߂ăI�[�G���́u���W�v(�P�X20)�𐢂ɏo�����B��ȉƃx���W���~���E�u���e���i1913-1976�j�́w�푈���N�C�G���x�i�P�X�U�Q�j�ɃI�[�G���̎�9�҂������ꂽ�B �s�����ׂ���߂̎�҂̂��߂̎^�́t �ǂ�Ȓ����̏�������Ƃ����̂��@�ƒ{�̂悤�Ɏ���ł䂭�ҋ��ɁH ������C�̉������̂悤�ȓ{�肾���� �������Ȃ�Ԃ����C�t���̂��₢�e�������� ���킵�Ȃ��F��������Ă��� �ނ�̂��߂ɋU�P�͂���ʁ@�F��������� ���݂̐�������ʁ@���̍����̑��ɂ́c ���̋��萺�@�������ԖC�e�̂����ꂽ�悤�ȍ����� �����Ĕނ�ɔ߂����ً����Ăъ|����i�R���b�p�̑��ɂ́@ �ǂ�ȃ��E�\�N���ނ����x�ɒ������߂Ɍf�����悤���H ���N�������̎�̒��ł͂Ȃ��@�ނ�̓��̒��� ���ʂ̐��Ȃ�����P���̂��낤 ���������̊z�̑����߂��@�ނ�̊��̕����z�ƂȂ邾�낤 �ނ�̉Ԃɂ́@�Â��ȐS�̗D���� �����Ă������Ƃ���Ă��鉩�����@�u���C���h�ƂȂ��č~�낳��� �i�Q�l�jhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~lyricssongs/TEXT/SET4074.htm �sAnthem for Doomed Youth�t What passing-bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns. Only the stuttering rifles' rapid rattle Can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them; no prayers nor bells, Nor any voice of mourning save the choirs, ? The shrill, demented choirs of wailing shells; And bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes Shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall; Their flowers the tenderness of patient minds, And each slow dusk a drawing down of blinds. ��1919�N�A���{�C�R�̐���L���i�Ђ�̂�j�卲�i1875-1945/����44�j���A�s�퍑�h�C�c�����@���邽�ߖK�������B�o���O�A����́u�푈�}�~�͂Ƃ��Ă̌R���͋��͂ł���ׂ��v�Ƃ���R����`�҂ł������B�܂��k�t�����X�ɓ���Ós�����X��K�ꂽ�B�폟���Ȃ̂ɁA���ׂẲƉ�����Q���A�z�e�����匀������ꗎ���A���I�����߁A�p�Ђ��̂��̂������B�t�߂̑����͉�ł��A�c���͍r��ʂāA�������̎p���Ȃ��B�͍��i�����j�̒��ł̓h�C�c�������������܂ܔ��������Ă����B���̎���Ƃ���ɏ\���̕�W�ƁA����オ�����y�\�����������B����͂��̏Ռ����L���B�u�܂�ŕ�̊C�̂悤�ł��B�����ɐ푈�Ƃ͂����A���܂�ɂ��l�Ԃ̖��̈������Ƃł͂���܂��B���ꂪ�����ł���A�N����l�E����Ă��A�Љ�̑厖���Ƃ��āA�������A�ٔ����Ƃ��������ɂȂ�ł��傤�B���ꂪ�푈�̂��߂Ȃ�A���̑�ʎE�l���s���Ă������̂ł��B�l�͍r��ʂĂ����l�̑����ɗ��ꗧ�\���̕�W�߂A�푈�̓������l�Ɛl�Ԃ̐������l���l������܂���ł����v�B�����Đ���́A��ꎟ���E���ɂ�����ő�K�͂̌���n���F���_����K�ꂽ�B���̓y�n�ɂ͕��R�̗v�ǂ����������߁A��P�O�J���ɂ킽�范�����U���������A���R���킹��30���l�ȏオ�펀���Ă����B���I�푈�̓��{�R�̐펀�҂͂W���l�ł���A���̂S�{�߂������̐��Ŏ���ł����B��т̘V�l�A�����A�q�ǂ��������Y���ɂȂ��Ă���B �u�s�X�n�͊��S�ɔj��A�l�̏Z�މƂ͂Ȃ��A�܂�Ń|���y�C�̔��@�Ղ̂悤�ł����B�ƌR��50���̕��𓊓����āA��x�͂��̒n���̂��܂������A���R�ɂ���đS�ł������܂����i�����݂̐��ł͓ƌR�����Җ�35���l�A�������Җ�15���l�j�B�ނ�͌����Ď��ɂ����Ď��̂ł͂Ȃ��B�������Ƃ̂��߂ɌȂ̖����̂Ă��̂ł��B�ނ�͍��Ƃ̗v���ɂ���āA���≞�Ȃ��ɖ������グ��ꂽ�̂ł��v�B����͐펀�҂ɂ��āA���Ƃ̂��߂ɖ����̂Ă��̂ł͂Ȃ��A�L�������킳���������グ��ꂽ�ƌ��Ȃ��悤�ɂȂ����B ���e���ł͑��͐�̐��ւ̈ڍs�ƂƂ��ɐ����������z�����ƂȂ�A���������͋��R�̈�r�����ǂ����B1916�N11���̃��V�A�̎�s�y�g���O���[�h(�T���N�g�y�e���u���N)�ł̑�K�͂Ȗ��O�X�g�A17�N4���̃h�C�c�ł̐H�Ǝ�����P�Ɣ��핽�a�����Ƃ߂��K�͂Ȗ��O�X�g�A5���̃t�����X�ł̕��m�����A7�`8���̃h�C�c�͑��ł̐����\���Ȃǂɂ݂���悤�ɁA���O�̉}��C���͍��܂�A�u�a�����Ƃ߂�^�����䓪�����B ��1917�N7���ȍ~�A��������ł̐��̓C�M���X�Ɉڂ����B���N11���ɂ̓A�����J�̍q���͂́A�q��@800�@�Ɠ����1200�l�ɂ܂ő�������Ă���B ���\������ł͓`�ߌޒ��������Q�V�̃q�g���[�i1889-1945�j�͓ŃK�X�U���ňꎞ�������Ă���B ��1918�N4��28���i�I��̖N�O�j�A�I�[�X�g���A�c���q�̈ÎE�ƃK�������E�v�����c�B�v���č��ɂ����Č��j�̂���23�ő��E�B�T���G�{��������3�N10������ł������B���j���Ғŏǂ̈����̂��߂ɉE�r��ؒf�A�h�{�������d�Ȃ莀�S���ɂ͑̏d��40kg�����Ȃ������B��͖̂�����`�҂̐��n�ɂȂ邱�Ƃ�����邽�߃T�������R��n�ɔ閧���ɖ������ꂽ���A�����ɗ���������`�F�R�l���m�ɂ����1920�N�Ɂu�Z���r�A�l�̉i���̉p�Y�v�Ə����ꂽ�L�O�肪��n�ɗ��Ă�ꂽ�B ���}���k���⃔�F���_���h�����w�����ĘA���R�������ɓ��������I�p�Y�ƂȂ����t�B���b�v�E�y�^�����R�i1856-1951�j�͗��P�X17�N�ɗ��R���i�ߊ��ɏA�C���A�O���̕��m�̊ԂɍL�����Ă����m�C�̒ቺ��s���]���������Č�������^����ꂽ�B�P�X34�N�ɗ��R��b�A�C�B�P�X�R�X�N�A�W�R�ő���E��킪�u���B���N�h�C�c�R���p���ɐi�����A6���t�����X���{�̓{���h�[�֔����B���m�[���t�̕��������y�^���̓��m�[���E��ɎƂȂ�A�U��22���h�C�c�Ƌx�틦�������B���{�y��5����3���h�C�c�ɐ�̂���A7��2���A���̒n�тɃr�V�[����s�Ƃ���u�t�����X���v�������A�y�^���͓ƍٓI�Ȍ����������Ǝ�ȂɏA�C�����B�y�^���̓��_���l�̘A�s�A���W�X�^���X�̓E���A�h�C�c�ւ̘J���͂̒ȂǑS�ʓI�Ƀh�C�c�ɋ��͂��A1944�N�̘A���R�̃t�����X�㗤��i�m���}���f�B�[�㗤���j�Ƀh�C�c�֓���A����ɃX�C�X�ɓ��������B���t�����X�ɘA�s���ꎀ�Y��鍐���ꂽ���V��𗝗R�Ɏ��s�������Ȃ��Ȃ��܂܂P�X51�N�ɑ吼�m���݁A�i���g���̃��[���̊č��ɂĂX�T�şf���B |
�y�푈�w���҂����z
�u���l�揄��v�Ƃ�����|����O��邯�ǁA�������҂Ƃ��ăX���[�s�\
������ �p�@/Hideki Tojo 1884.7.30-1948.12.23 �i�����s�A�L����A�G�i���J�쉀 64�j2010
 |
 |
| ��O�Łu���ɕ��@�͂Ȃ������̂��v�Ɩ₢������ | �u�����ƔV��v |
 �@ �@ |
| �j�����R����O�ł��낢�ł��� |
| ��40�㑍����b�B���R�叫�B�����m�푈�J�n���̎B�������܂�B���͗��R�����B���R�m���w�Z�A���R��w�Z�𑲋ƁB1928�N�i44�j�A���R�R���ǒ��E�i�c�S�R�̗��R���������_�ɉe�����ė��R�Ȃɓ��ȁB���R���Ɉ�吨�́g�����h�h���i�c�ƍ��グ���B�����h�́g�c���h���}�i�I�N���Z�h�̓����ɔ������A�N�[�f�^�[�Ȃǂ̒��ڍs���ł͂Ȃ��A�@�ɏ]���č��Ɖ������s�����Ƃ����B�����A1935�N�i51�j�A�i�c�͍c���h�ɈÎE�����B���N�A��E��Z�����ōc���h�����N�Ɏ��s����ƁA�����瓝���h����C�ɌR�����̌��͂��������B�����֓��R�i���B�j�̌����i�ߊ������������́A�S���i�c�̒�������Ŗ��B�̍c���h�R�l��Ђ��[����č��ɑ������B���킭�u����ŏ����͋����������v�B 1937�N�i53�j�Ɋ֓��R�Q�d���ɂȂ�ƁA���B����ʂ��Ē����x�z�ɖz���������푈���g��B�߉q���t�ŗ����ɂȂ�ƁA���ĊJ�����������߉q�ɋt�炢�A���ƈɎO�����������═�͓�i����������i�ߓ��t���E�ɒǂ����B 1941�N�i57�j�A�߉q�̑ސw��A�����R�l�̂܂ɏA�C���A�Εĉp�J������s�����c�Ƃ����̂��]���̐������A�ߔN�̌����ł͓������푈����鍑����f�B�A�ɒǂ����܂�Ă������Ƃ����炩�ɁB�J��O�Ɏ��@�֓͂��������͂R��ʁB���̑唼�����ĊJ������߂Ă����B��O��c�œ��ĊJ�킪���肵����̓����Ɣ鏑���̉�b�B�鏑���u���̍��͑����ɑ��ĉ����O�Y�O�Y���Ă���̂��Ƃ��������������Ȃ�܂����v�����u�g�����͍��������h�ƌ����Ă���̂��낤�c�v�B ���a�O����]���a�V�c���A�����ă^�J�h�̓����ɑg�t�𖽂����̂́A�푈����Ɍ����ė��R�ɓ����������l�Ԃ������������Ȃ���������B�ɂȂ�Ώd�ӂ���T�d�ɂȂ�̂ł͂Ƃ������҂��������B����b�E�،ˍK�ꂢ�킭�u�����𐄑E�����͎̂��B�����Ƃ͂ǂ��ɍs�������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��B��͑傫���Ȃ��Ă������������Ȃ��v�B����A���@���فE��ؒ�ꂢ�킭�u�����͊C�R������ς��ɕs���ӂƌ������ƂɂȂ�A���R�����Ă���Ȑ�͋����Ď咣���Ȃ��ƌ����Ă����v�B���̂悤�ȏ،�������A���d�h�Ƃ���铌���ɂ������͂������悤���B�������킭�u�i�����Łj���ꂾ���̐l�ԁi���{���j���E���ċ����g���āA��Ԃ�ŋA���Ă����ƌ������Ƃ͏o���Ȃ��v�B ���R�ȌR���ے��E�����������킭�u�ƍٓI�ȓ��{�̐����ł͖��������B������푈����͏o���Ȃ�������ł��B�����������{�l�̎コ�A���Ƃɍ��Ƃ��x�z�����]�A��������͂��߉�X�̎���Ɖ��̋C�͂�����Ȃ��������Ƃ��A���̐푈�ɓ������ő�̗��R���Ǝv���v�B�܂�A������푈�Ɉ������荞�q�g���[�ƈقȂ��āA���{�̏ꍇ�A�ƍَ҂����Ȃ��������炱���A�푈���������Ȃ������B���{�̃g�b�v����{�c���{�A����c�݂͂�ȐӔC���̂��C���ŁA�㍘�Ƃ݂Ȃ��ꎸ�r����̂��|���āA�푈�͋����ƋC�t���Ă��Ȃ���푈�Ƃ�������I��ł��܂����B �J���A�����͓����E�O���E���R�E�����E���H�E�R���̊e��b�����C���A����ɎQ�d�����܂Ŗ��߂Č��͂̏W�����v��B�����āu�哌�����h�����݁v���������Đ푈�𐋍s�������A�⋋�y���̂�����ȍ��ő����̕��m���쎀�B��ǂ͂ǂ�ǂ����A1944�N�i60�j�ɂ̓}���A�i���C��Ŕs��ĊC�R�������A�T�C�p�����ח����Ă��܂��B����Ŗ{�y��P������I�ɂȂ����B���̎��Ԃ��A�������t�͑����E�B1945�N�i61�j�A���{�~���B�����̖����A�É�G�������͋ʉ������J�n�Ɠ����Ɏ��������B�������g��A����Ɨe�^�őߕ߂���钼�O�Ƀs�X�g�����E�����݂�������ɏI���A�����ٔ��Ŏ��Y�ƂȂ����B���N64�B�]��ʁB�M�ꓙ�B |
| �����t�[���┠�p���`��� �p�D�����p�@���ǂ����Ă������l�Ɏv���Ȃ��̂ł����ǂ��ł��傤���B�s�k�̐ӔC������Ď��E�Ȃ�č��̐����Ƃɔ�ׂ����قǐӔC��������悤�Ɏ��܂����A�����������h�ł͂Ȃ��ƕ����܂����B�����p�@�����Ƃ����̂̓A�����J�Ɛ��̓��{�̋��炪�A���t�����C���[�W�ł����H����Ƃ�����ς舫���l�ł����H �`�D�����p�@��ٌ삷��l�͂��������܂��A�u���������Ă��A���͂�J��̗�����~�߂鎖�͏o���Ȃ������v�ƁB���������́u����v����������{�l�͓������������Ƃ��䑶�m�Ȃ��B�܂��A�u�����p�@�͂��܂��܂��̎����Ɏ������̂ő��������v�ƌ����l�����܂���������C�����ƌ��������ǂ����������A�g�b�v�̒n�ʂ̎҂̌����A�ӔC�Ƃ͂ǂ��������̂��𗝉����Ȃ��ӌ��ł��B �푈�ɔ��ł���u������b�E���R��b�Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��v�ƌ�������ł����̂ł��B���ꂪ�����Ȃ������Ƃ����琭���ƂƂ��Ė��\�A���ӔC�����A�����̏ꍇ�́u�����Ȃ������v�̂ł͂Ȃ��āu����Ȃ������v�̂ł��B�V�c����u�푈�͔�����l�Ɂv�v�������������푈����ׂ̈ɕK���̓w�͂������ƌ����L�^�͂���܂���B�Ȃ����H����ȓw�͂͂��Ȃ���������ł��B �C�R�̕ē������A�R�{�\�Z�͂����������B���R�̈ÎE�̋�����C�R�����̍D��h�̓˂��グ�ɕ������A�ނ炪���{�̗v�E�ɂ��������͎O���������Εĉp�푈����点�Ȃ������B���C������Ώo�����̂ł��B �푈���n���Ă���A�V�c�͑��߂Ɂu�ē��̓��t�����̂܂ܑ����Ă�����푈�ɂȂ�Ȃ����������m��Ȃ��ˁv�ƌ����������ł��B �������͊֓��R����͌����i�ߊ��A�Q�d���Ƃ��Ĕ_���l�Y�ȂǂƊ��Ŗ��B�ŃP�V���K�͍͔|���A����̈��ЂB�A�����ő�ʂɖ����B���z�̃J�l��ׂ��ė��R���h�̔閧�����ɂ����B ���֓��R�Q�d���A���R�����A���R��b�ƈ�т��Ă��Ē����嗤�N���𑣐i�A�����m�푈�̎����������B ����O���߉q���t�ł́A�߉q�����͎R�{�\�Z�Ȃǂ̉e�������蕽�a�H����̍����Ă����B����������ĊW���������ē��{�̐j�H�����߂�ɂ�����A�߉q�̍l����m���Ă����C�R��b�́u�����Ɉ�C�v�ƁB�߉q�u���ɔC���ꂽ��x�߂���͓P�ށB�A�����J�Ƃ͊W�����v�Ɠ������B����ɓ������R��b�͌��{�A�u��������͐�ΓP�ނ��Ȃ��B�A�����J�Ƃ͐푈����v�Ƌ���ȉ�������ꂽ�B�����ĉ�c�̂��ƁA�����͋߉q�̂Ƃ���֓�x���g���𑗂�A�u���̌��ł͗��R�͂���ȏ�b����������͂Ȃ��v�ƃg�h�����h�����B���ׂ̈ɑ�O���߉q���t�͑����E�ɒǂ����܂�܂����B�߉q�������E�ɍۂ��ēV�c�ɏo������t���ɂ͋߉q�̉����������o�Ă��܂��B �����Ď���������b�ɂ͖،ˍK�����b�̋������E�œ����p�@���C������܂����B�߉q�����t�����o���ē����Ɋۓ��������ƌ����l�����܂�������͑傫�Ȍ���ł��B �u�����ł����̂��ˁv�ƐS�z������͂ɖ،˂́u�I���ɔC���Ă���B�����Ȃ�A�����J�ƌ��o����v�A�ƁB���A�،˂́u����͎��s�������v�ƌ����������ł����A�����Ԃ�310���l�̓��{�l�������Ƃł���Ȏ��������Ă��x���B �������ɂȂ��������́A�V�c����u���܂ł̌o�܂͔����ɖ߂��A�ĉp�Ƃ̐푈�͔�����悤�Ɂv�Ɨv�]���ꂽ�ɂ��S��炸�A������b�E���R��b�Ƃ��ĊJ������F�����B�u���{�͌����ȗ�2600�N�A�푈�ɕ����������Ȃ��B���̐��_������Εĉp�ƌ����ǂ��|���ɑ���Ȃ��v�ƌ����āB�����̓A�����J�Ƃ̌��͂��Ȃ��������A�������V�c�̈ӂ��ĊJ���h���ׂɕK���ɓw�͂������ƌ����L�^�͑��݂��܂���B ���푈���n�܂�ƁA�����͑�����b�A���R��b�ɉ����ē����E�R���E���H�E�O���E�����̊e��b�A�X�Ɍ��@�ᔽ�̗��R�Q�d�����܂Ō��C�A��C�B���������������A�S���ɃX�p�C�Ԃ�~���ē������{�ƌĂꂽ�ꐧ�������s�����B �����̂��C�ɓ���̍��В��Ŏ�����ł߁A�C�ɓ���Ȃ����̂͗��R�̍����ł���O���֍��J�B���Ԑl�̏ꍇ�͒����N���啝�ɒ����Ă���l�����������Ŏ��n�ɑ��荞�B ���������ʂ����Ă��Ȃ������ׂ�ƌ����ĉƁX�̃S�~�����̂����ĕ�������A�z�n�̋��s��֍s������A�A�A��푈�����Ă��鍑�̑�����b�ł��傤���H�������푈�̓{�������B�]��ɂЂǂ��ɗ��R�A�C�R�o���ɋ�̓I�ȈÎE�v�悪����܂����B �����͂��Ⴍ�����ŁA�t�c�ł������n���𗧂Ă�̂ł݂�ȍ����������ł��B�ӂ����ڂɂ́u���͓V�c�É��ɐM�C���ꂽ������b���B���̎���ᔻ����͕̂É���ᔻ���鎖�ɂȂ�v�A�ƁB�q���ł��ˁi�j�v ���V�c�ɑ��钉���S���E�\�ł��ˁB�T�C�p���ח��Ŏ��E������ꂽ���̕����ւ̌P���ŁA�����́u�V�c�ւ̒��`�ɂ͍L�`�Ƌ��`������B���`�̒��͓V�c�̈ӎv���Ɏ��s����B�������L�`�̒��`�͓V�c�̈ӎv��������̍l���ƈ���Ă����炻��𐳂��B����ł��ς��Ȃ���������Ăł�������̈ӌ���ʂ��B�����͌�҂�I�ԁv�ƁB����ł͒����S�ǂ��납�V�c�ւ̔����ł���B �������͌R�l�Ƃ��Ă����\�B�푈�{�������̏��a20�N2��26���A�V�c�̎���ɓ����āu�푈�͂܂��ܕ��ܕ��B�{�y���킪�����Ă��ČR�̎O���̈�̕��͂ŏ��Ă܂��v�ƌ����ēV�c����ꂳ�����B �����Ĕs��B�����͎������n�߂��푈�ō����Ԃ�Ă��܂����ӔC������ē��{�̕��m�炵����������ǂ��납�A�����ٔ����Ȃ���ΐ����������т���肾�����B�����̏o������w�P�ׂ̈Ɏ��E���R�̃o���U�C�ˌ���Q�����ɂ������m�����͓����_�Ђ��J��Ċ��ł��܂����B �����{���~���������A���̓��������ɂ��������܂����i������j �u���{�A����������ȂɊȒP�Ɏ��������悤�ȈӋC�n�Ȃ��Ƃ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ������B����ȍ��������Ăɂ��Đ푈�w�������������n���������v �u�������̌����ō~�����Ă��܂����v�A�ƁB �����Ȃ�ƋC�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ���v���܂��B �����Ȏw���ɖفX�Ə]���Ď����E�ȕ��m������16����̓��U���̎�҂����A�ꂵ���������䖝���������J�����������ł��菺�a�V�c�̐��f���o�J�ɂ����R�����g�ł��B �����Ď������n�߂��푈�ō��������S���̓��{�l�����ƌ����̂ɁA����{�鍑���R�叫�Ƃ��ē��X�Ǝ�������o���Ȃ������ڋ��҂ł��B ���Ȃ݂ɁA�����͓����ٔ��œV�c��������ƌ����ӌ�������܂����A�傫�Ȍ���ł��ˁB�A�����͓V�c���Ƃɂ��Ȃ����͊��Ɍ��߂Ă������A����ł͂��̎��E�����͂Ȃ����̂��H����ł��܂�����V�c�����܂���ˁi�j�B�܂��������E���������玀�ɂ܂���ł������B�i�����N�j |
�k���̑��@�����ւ̋��P�l
�����c�� ����/Renya Mutaguchi 1888.10.7-1966.8.2 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 77�j2010
 �@
�@
| ���R�����Bḍa��������A�����m�푈�J�펞�̃}���[����C���p�[�����ɂ����ĕ������w���B�⋋���y���������߁A�C���p�[���ł͓��{�R�W���U��l�̂��������҂V���S��l���펀�R���Q��l�i�唼���쎀�j�A�����҂S���Q��l�i�������Q�삩�炭���a�j�Ƃ������\�L�̋]���҂��o�����B���{�R�̍s�R���[�g�͉쎀�҂��A�Ȃ�A�g�����X���h�ƌĂꂽ�B���C���p�[�����E�O�ꌟ�� |
�����h���t�E�w�X/Rudolf Hess 1894.4.26-1987.8.17�i�h�C�c�A�����W�[�f�� 93�j2015
Friedhof Wunsiedel[original burial site], Wunsiedel, Wunsiedel im Fichtelgebirge Landkreis, Bavaria (Bayern), Germany
 |
 |
 |
| �h�C�c�����̋��� | 2011�N�܂ł��̏ꏊ�ɕ悪������ | �⑰�̓l�I�i�`�̐��n�ƂȂ�̂����ꂽ |
| �����ƁB�����̃i�`�X�������B�p�Ƃ̊J�������邽�߁A�q�g���[�ɖ��f�ŒP�Ɠn�p���a�������݂����A�i�`�����̓w�X�_�ُ�Ɣ��\�B�p�`���[�`���̓w�X�����ƕߗ��Ƃ��A�w�X�̓����h�����ɗH���ꂽ�Ō�̐l���ƂȂ�B���ɐ�ƂƂ��čق���A���_���l�s�E�́u�l���ɑ���߁v�ɂ��Ă͖��߂Ƃ��ꂽ���A�u�����d�c�v�u���a�ɑ���߁v�ŏI�g�Y�ƂȂ����B93�܂Œ������A��ƍٔ��̍Ō�̐����c��ƂȂ������A1987�N�ɌY�����̓d�C�R�[�h�Ŏ��݂����B�悪�l�I�i�`�̐��n�ƂȂ邱�Ƃ����O������n�Ǘ��l�ƃw�X�̐e���͕��P�����邱�Ƃō��ӁA2011�N7���A�[��ɓP�����ꂽ�B�⍜�͉Α�����C�ɎU���B |
�����C���n���g�E�n�C�h���q/Reinhard Heydrich 1904.3.7-1942.6.4�i�h�C�c�A�x������ 38�j2015
Invalidenfriedhof, Berlin-Mitte, Mitte, Berlin, Germany//Plot: Section C, between the large plots of Oven and Scharnhorst.
 |
 |
 |
| �x�������ɂ� | ��͂��͓P������Ă��� | �i�`�X�����͌����݂��̂悤�� |
�i�`�X�̍��ƕۈ��{���iRSHA�j������̏��㒷���B�q�����[�Ɏ����e�q���iSS�j�̎��͎ҁB���_���s�E�̎����I�Ȑ��i�ҁB
�⍓������u�����̖�b�iDie blonde Bestie�j�v�ƌĂꂽ�B�`�F�R�������Ƀ`�F�R�l�����ɈÎE���ꂽ�B
| �u�i�C�R�́j�~�b�h�E�F�[�C��łȂ����������Ƃ����唽�ȉ������Ă��Ȃ��B�X��C�C��ł�����Ă��Ȃ��B���{�͑��͖{���ɂ��Ȃ��B�C�R��������Ȃ��B���s�̌����Ƃ����̂͗��R������Ă��Ȃ��B����A���{�l�S�̂������Ȃ̂��B�{���ɒ��ǂ���`������A�����܂ł�肽���Ȃ��A�Ƃ����̂�����̂ł́B ���s�̋��P���A�����Ƃ��A������Ƃ����L�^�Ƃ��A�؋��������W�߂Ďc���Ă������Ƃ������_�́A���悻�Ȃ���Ȃ��ł��傤���B�A�����J�͕������ł��B�A�����J�͓O��I�ɂ��܂�����B���{�l�͐푈�Ƃ������̖̂{���̍����Ƃ����܂����A�c�����Ƃ����܂����A�����������̂ɂ�����ƌ����������Ƃ��Ȃ������v�i�����ꗘ�j |
���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���
���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���
���W�������ʌ����̖ڎ���
��i���j�Agrave�i�p�j�Atombe�i���j�Agrab�i�Ɓj�Atomba�i�Ɂj�Atumba�i���j�Asepultura�i�|���j
��n�i���j�Acemetery�i�p�j�Acimetiere�i���j�Afriedhof�i�Ɓj�Acimitero�i�Ɂj�Acementerio�i���j�Acemiterio�i�|�j
|
